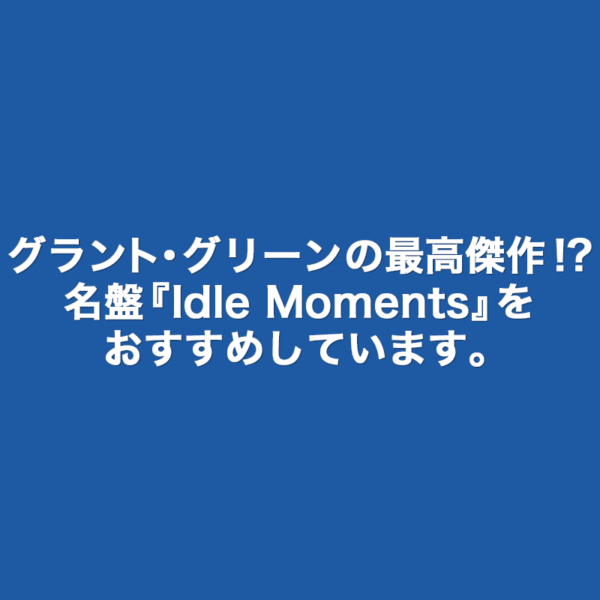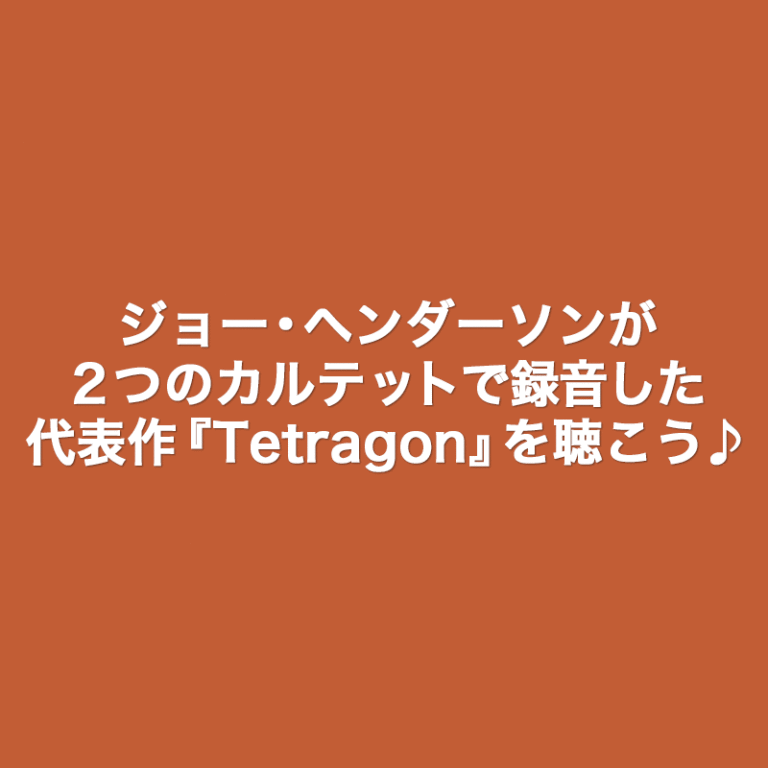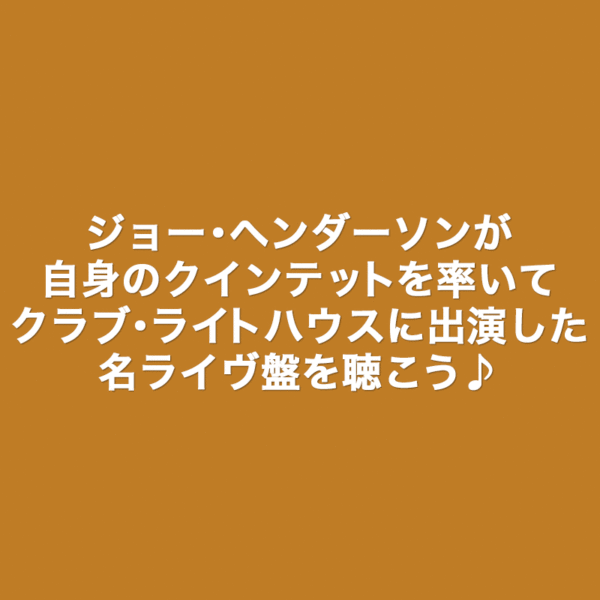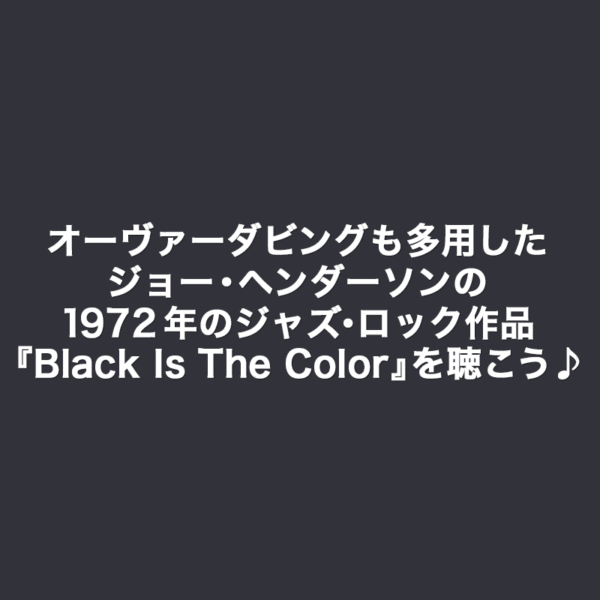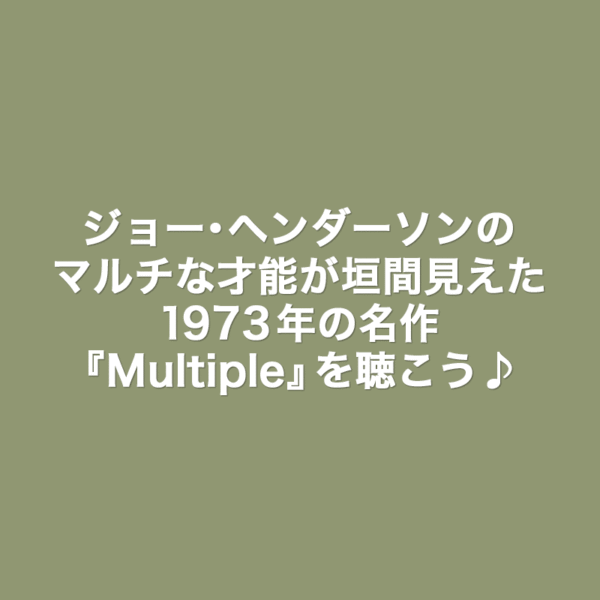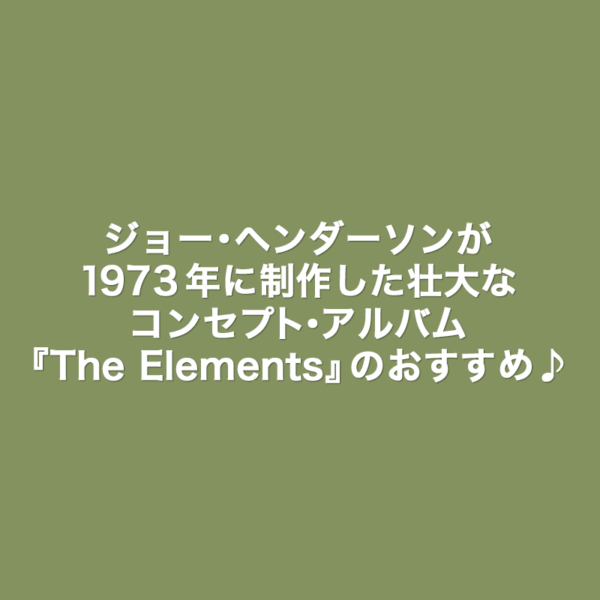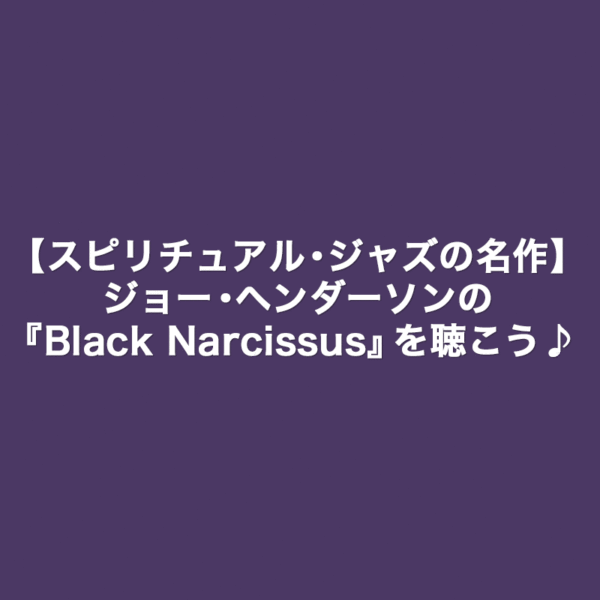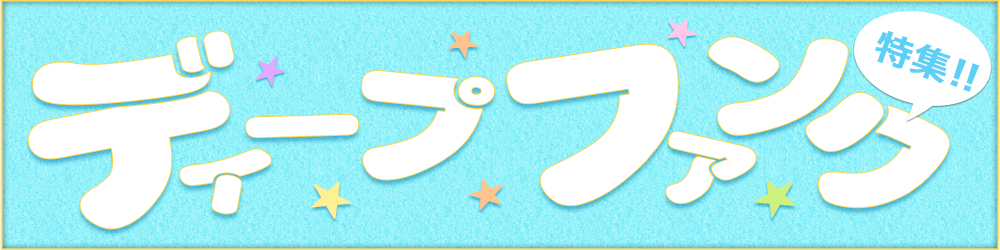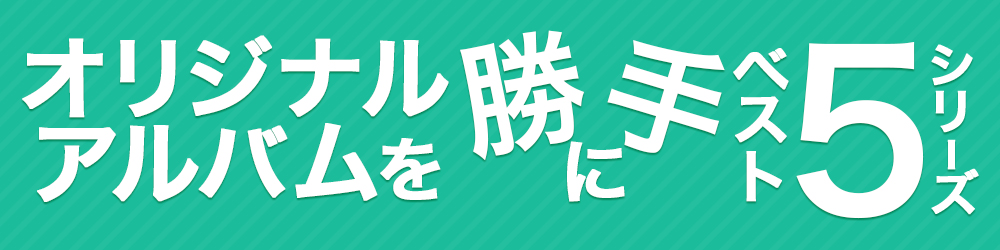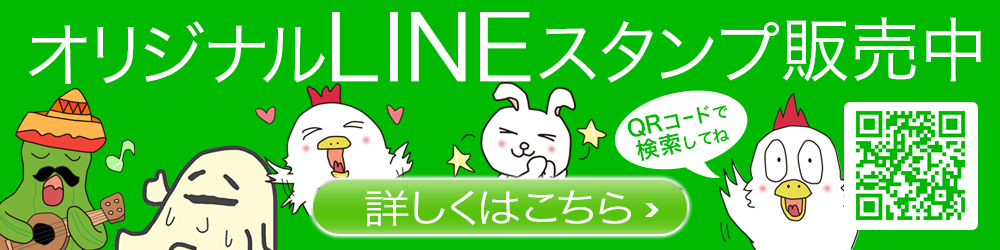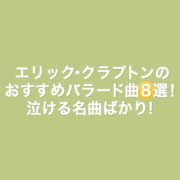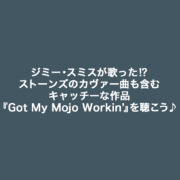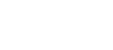
2018/10/19
ジョー・ヘンダーソンがブルーノート・レーベルに残した5枚のリーダー作!
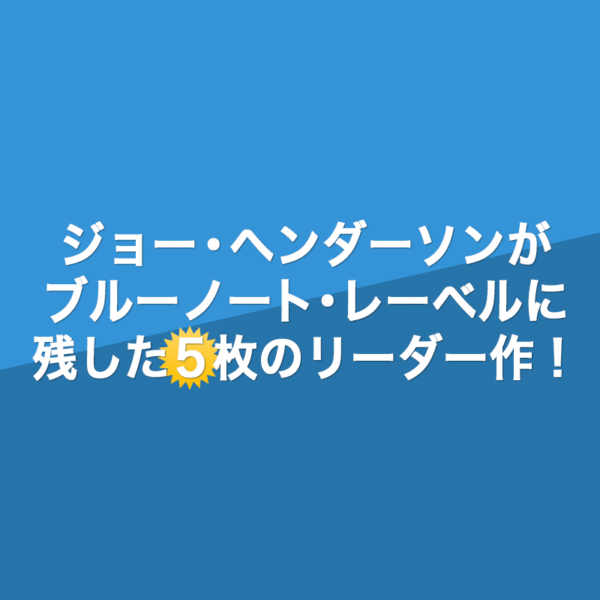
新世代と旧世代を繋ぐ名サックス奏者のジョー・ヘンダーソン!
新主流派のサックス奏者ジョー・ヘンダーソンがブルーノート・レーベルに残した5枚のリーダー作品をご紹介!
このところロック系のブログ記事が続いていたので、今回は正統派のジャズのご紹介にいきたいと思います。
今回は1963年に名門ブルーノート・レーベルにて初リーダー作を吹き込んだ新世代のジャズサックス奏者のジョー・ヘンダーソンについてです。
ジョー・ヘンダーソンというサックス奏者
旧世代のビ・バップやハード・バップから新世代のモード・ジャズやフリー・ジャズまで守備範囲に入れた名サックス奏者です。
当時マイルス・デイヴィスやハービー・ハンコックらが中心となっていた『新主流派』と呼ばれる新しい世代のジャズを演奏できる期待の新人としてデビューしたのがこのジョー・ヘンダーソンでした。
この『新主流派』と呼ばれるジャンルの明確な定義って難しいとは思いますが、ジョー・ヘンダーソン以外では、ヘンダーソンと同じくテナ-サックス奏者のウェイン・ショーターにアルト奏者のジャッキー・マクリーン、トランペット奏者のフレディ・ハバードやヴィブラフォン奏者のボビー・ハチャーソンやドラムのトニー・ウィリアムスなんかが思い浮かびます。
それまでのハード・バップと呼ばれる旧式のジャズではなく、より難解な理論で高度な演奏技術が必要とされるモード・ジャズを中心に演奏できるミュージシャンばかりです。
かくいう僕もジャズの中では、ジャズファンクの次にこの『新主流派』の時代が好きだったりします。
基本的に先に挙げたミュージシャン全員作曲も出来て高度な演奏技術も持ち合わせているので、ジャンルは違えど音楽をやっている人であれば誰しもが憧れるような存在であって然るべきだと感じます。
さて、ここで本題に入る前にブルーノート・レーベルの創始者であるアルフレッド・ライオンのジョー・ヘンダーソンに対する言葉を引用してみたいと思います。
「60年代になると、伝統から離れたスタイルの持ち主がデビューしてきた。ジョーは、のちに登場してくるもっと新しいスタイルの持ち主と旧世代との掛け橋だ。時代の交錯から次なるものが生まれる。それを彼のアルバム、とくにデビュー作では追求したつもりだ。」
このようにライオンのこの発言から、彼がこの新人サックス奏者に多大なる期待を寄せていたのが感じられますね。
それでは、僕も大好きなジョー・ヘンダーソン(以下:ジョーヘン)がブルーノート・レーベルに残したリーダー作5枚をご紹介したいと思います。
ちなみにザ・ニュー・マスターサウンズのギタリストのエディ・ロバーツもジャズを勉強する際にジョーヘンを参考にして練習をしていたとか!?
ブルーノート・レーベルに残した5枚のリーダー作
今回ご紹介したいのは、1963年~1966年の間にブルーノート・レーベルに吹き込まれた『Page One』、『Our Thing』、『In ‘N Out』、『Inner Urge』、『Mode For Joe』の5作品です。
どれもアルバムジャケットのデザインまでかっこいい名盤ばかりです!
リード・マイルスのデザインセンスって本当にすごいですよね!
僕も一応デザイナー職をしているのですが、60年近く経った今見ても色褪せるどころかいまだにオシャレなデザインだと思います。
っていうか、デザイナーがデザインについて勉強する際に読むレイアウトなどの本にブルーノート・レーベルの作品が載っていたりもするんですよ!
デザインを勉強しているときに、ブルーノート・レーベルのアルバムが「参考にすべきタイポグラフィー」という項目で載っていました。
ジャズに興味がない人にとっては、「こんなタイポグラフィーもあるんだな~」程度の事でしょうが、その当時すでにジャズオタク歴10年以上だった僕は「おぉ!これはジョーヘンのアルバムにホレス・パーランのアルバムにラリー・ヤングの名盤!家帰ったら今日はこの作品聴こう♪」とデザインの勉強よりもジャズに夢中になっていました。
まぁデザイナーってセンスや感性が必要だと思うのですが、ジャズのアドリヴ演奏を聴いたり、実際に自分で演奏してみることでそういった芸術面でのセンスや感性を磨くことも出来ると思いますので、あながち間違ってはいないのかな~?と個人的には思います。
何もないところからWebサイトを作り上げるのと、何も用意していないセッションでいきなりアドリヴでギターソロを弾く感覚は、僕にとってはどちらも似ていますし、とても大事なことだと思っています。
そんなアルバムジャケットのデザインもオシャレで手元に飾っておきたくなるジョーヘンの5枚の作品を1枚ずつご紹介いたします。
Joe Henderson – 『Page One』
なにはともあれ名曲”Blue Bossa”が1曲目に収録されていることが、この作品の一番の魅力ですね!
今ではセッションでも定番のボサノヴァ風ジャズ曲です。
この曲はトランペッターのケニー・ドーハムが書いた曲です。
この当時のジョーヘンは、ケニー・ドーハムに見出された後輩サックス奏者という感じでブルーノート・レーベルに初のリーダー作を吹き込むことになりました。
それがこの『Page One』です。
吹き込みに参加したメンバーは、リーダーのジョーヘンに先輩格のケニー・ドーハム、それ以外にはジョン・コルトレーン一派のピアニストのマッコイ・タイナーにベース奏者のブッチ・ウォーレン、ドラム奏者のピート・ラロカのクィンテット編成になります。
1曲目の”Blue Bossa”が歴史に残る名曲であることは疑う余地ありませんが、僕個人としては3曲目以降のジョーヘン作の斬新な曲の方が好きです♪
ケニー・ドーハムは、僕も大好きなトランペッターではあるのですが、いかんせん「保守的」な演奏は、もはやこの時代の新主流派のジャズにおいて「古くさい」演奏に聴こえてしまいます。
“Blue Bossa”でも美しテーマメロディーの後にまずは作曲者のケニー・ドーハムがファーストソロを吹くのですが、それまでのハード・バップ系の作品から年代を追ってジャズを聴いてきた人ならドーハムのトランペットソロは、もはや古くさい音使いだと感じることでしょう。
次にソロを吹くジョーヘンの、それまでのサックス奏者にはないリズミックで流れるようなメロディーラインの構築技術はとても斬新です!
ヘンダーソンに続くマッコイ・タイナーのピアノソロもこの時代としては斬新で、もはやケニー・ドーハムは時代に取り残されたように感じます。
年功序列で「おじさん」がお手本を見せるつもりでトランペットソロを吹いてみたけれども、その後に続く「若手」の斬新な演奏に驚きもはや自分が時代に取り残された旧世代の人間になっていた…と気づいてしまう感じでしょうか?
先のアルフレッド・ライオンの言葉ではないですが、そんな旧世代のジャズと、これから始まる新世代のジャズとの間を繋いだのがこのジョーヘンだったんだと感じます。
そういった点も僕がジョーヘンというサックス奏者が好きな理由です。
古いものから新しいものへ…しかし全てを捨てるのではなくって、古き良き伝統も残しつつ新しいジャズを構築していくそのスタイルがかっこいいと思います。
2曲目”La Mesha”もケニー・ドーハム作のバラード曲です。
そしていきなりマッコイの斬新なピアノのイントロで始まる3曲目の”Homestretch”から6曲目の”Out Of The Night”までの4曲は全てジョーヘンの書いた曲になります。
先の2曲と比べて「新しい」ジャズの曲という感じが聴きとれます。
個人的には4曲目の”Recorda Me”が素晴らしいと思います。
“Blue Bossa”と同じようなボサノヴァ風ジャズ曲なのですが、どこか古くさいテーマメロディーの”Blue Bossa”と違い、より洗練されたテーマメロディーを持っている曲だと感じます。
…が、しかし”Blue Bossa”のようにジャズスタンダードにはなれなかった惜しい曲だと思います。
1963年に吹き込まれたジョーヘンにとっての初のリーダー作『Page One』は、名曲”Blue Bossa”だけでなく、ジャズが新しい世代へと変わっていく過程のようなものが垣間見れる名盤ですのでおすすめの名盤です♪
Joe Henderson – 『Our Thing』
先ほどの『Page One』が吹き込まれてから約3ヶ月後に制作されたジョーヘンのリーダー作第二弾『Our Thing』です。
メンバーはドーハムとピート・ラロカは同じままで、ピアニストはマッコイ・タイナーからアンドリュー・ヒルに、ベーシストはディ・カーンに代わっています。
アンドリュー・ヒルは当時売り出し中の新人ピアニストでした。
ジョーヘンと同じようにアルフレッド・ライオンが期待を寄せる新世代のピアニストです。
今となっては新主流派を代表する2人のジャズマンが初顔合わせをした作品にもなります。
もちろんこの2人は目指す音楽性が似ているため悪くなるはずがなく、相性もピッタリです!
発売は前後するのですが、この吹き込みの2ヶ月後にアンドリュー・ヒルの初リーダー作『Black Fire』にジョーヘンが参加しています。
録音日とは関係なく『Black Fire』が先にリリースされ、この『Our Thing』が後を追うようにリリースされています。
さて、今回もケニー・ドーハムという「保護者同伴」作品になるのですが、1曲目は前作のようなドーハム作の”Blue Bossa”ではなく、いきなりジョーヘン作の斬新な曲”Teeter Totter”で始まります。
今の時代に聴いてもかっこいい曲です♪
ファーストソロこそ年功序列でドーハムが吹きますが、その後のジョーヘンやアンドリュー・ヒルのソロを聴いていると、もはや時代遅れのドーハムのソロのことを忘れてしまいそうです。
曲調にあっていないというか…ドーハム抜きのカルテット編成で吹き込んだ方が良かったんじゃないの?と感じるぐらいです。
…と思った矢先、2曲目のドーハム作の”Pedro’s Time”が、なかなか良い曲だったりします。
こういった曲ではドーハムの渋いトランペットソロが栄えます!年季の違いでしょうか?
少し吹きすぎのジョーヘンよりも少ない音でソロを構築するドーハムの方が、より大人な雰囲気で曲にマッチしています。
続く3曲目のタイトルトラック”Our Thing”はジョーヘン作の勢いのある曲です。先ほどの曲とは一転して、こういった曲調だとやはりドーハムは古くさく感じますね…。
残りの2曲”Back Road”と”Escapade”もドーハム作の渋めの曲です。
収録曲を全て聴いてみて、もはやジョーヘン作の2曲の方が強く印象に残ることを考えると、そろそろ若手のサックス奏者が保護者の元を巣立つときが近くなっていることを感じさせてくれます。
やはり”Teeter Totter”と”Our Thing”の2曲がおすすめの作品です♪
Joe Henderson – 『In ‘N Out』
アルバムのジャケットの斬新なタイポグラフィー・デザインが今の時代に見てもオシャレな、ジョーヘンにとっての1964年の3枚目のリーダー作『In ‘N Out』です。
大胆な文字入れは見る者に強烈な印象を残します。
僕もこの作品は、アルバムの中身の音楽だけでなくジャケットのデザインも含めて大好きな作品です。
このジャケットデザインのTシャツまで買いました。
たまに夏に着てます。
オシャレなんで全然恥ずかしくないです。
今作は、過去2作と同じくまだまだケニー・ドーハムが参加している保護者同伴作品ではあります。
ピアニストはアンドリュー・ヒルからマッコイ・タイナーに戻っています。そしてベースにリチャード・デイヴィスとドラムにエルヴィン・ジョーンズが参加しています。
あれれ?このリズム隊の3人ってジョン・コルトレーン一派じゃね?…とジャズ好きの方なら気づきますよね。
もちろん例のカルテットのこともあってか、マッコイ・タイナーとエルヴィン・ジョーンズの相性が抜群過ぎて、マッコイのソロ中は誰の作品か忘れそうになります。
1曲目のジョーヘン作の斬新な曲”In ‘N Out”で、ジョーヘンのソロの後にマッコイが長めのピアノソロを弾きます。
その間、マッコイのピアノソロとエルヴィンのドラムがあまりにも息が合いすぎていて、他のメンバーのことを忘れそうになります。
その後、ついつい「このピアノソロの後にコルトレーンがバリバリ吹いてくれるんだな!」って期待しちゃいます。
しかしピアノソロの後には、ケニー・ドーハムがゆる~~くトランペットソロを吹き始めて落ち着かせてくれます。
危ない危ない…危うくコルトレーンの作品と勘違いするところでした!
しかしジョーヘンの作曲能力がもはやコルトレーンが演奏していてもおかしくないような域に達していると言えなくもないですね。
この”In ‘N Out”はそれぐらい素晴らしい曲だと感じます。
サックスとトランペットのユニゾンで始まるイントロのかっこよさは一聴の価値ありです!
続くジョーヘン作の”Punjab”も2管のユニゾンのテーマメロディーがかっこいい佳曲です。
前作の『Our Thing』と同じように3曲目までがジョーヘン作で4、5曲目の2曲はドーハム作です。
トランペットソロは、少し古く感じますが曲作りに関しては、なんだかんだで良い曲を書けるのがドーハムの良さでもありますね。
作曲者は2人いますが、5曲全てに一定の統一感があってアルバムを通して聴いても違和感がなくまとまりがあります。
前2作よりも全体のまとまりがあるため、「”Blue Bossa”を聴くため」や「”Teeter Totter”と”Our Thing”を聴くため」なんていうことをしなくて良いと思います。
アルバムのジャケットデザインも含めて、真の名盤とでも言うべきジャズ好きなら絶対に聴くべき作品だと思います♪
Joe Henderson – 『Inner Urge』
4枚目のリーダー作にして初の1管編成による作品です。
前3作のように保護者同伴ではなく管楽器はジョーヘン1人のみです。
そこに例のコルトレーン一派のマッコイ・タイナーとエルヴィン・ジョーンズが加わり、ベーシストにボブ・クランショウが参加したカルテット編成による作品です。
『In ‘N Out』から約7ヵ月後の吹込みで1964年に制作された4枚目のリーダー作『Inner Urge』です。
ジョーヘンの代表作と言ってもよい出来で、5曲の収録曲全てが名演です!
「ジョーヘンの作品で何が一番好きですか?」ともし聞かれたら、僕は『In ‘N Out』と『Inner Urge』のどちらかを選びます。
しかしそのどちらか?についてはその時の気分で変わります。
ジャケットのデザイン的には『In ‘N Out』の方が好きですが、中身の音楽的にはこの『Inner Urge』の方が上をいっていると感じます。
やはりジョーヘンは「独り」の方が似合っています。
ケニー・ドーハムやリー・モーガンやウディ・ショウの助けなどいらないのです。
1曲目のタイトル曲”Inner Urge”に2曲目の”Isotope”と3曲目の”El Barrio”の3曲は、前作同様にジョーヘンの書いた曲になります。
どの曲もジョーヘンを代表するような名曲です。
特にサックスのオーヴァートーンから始まる攻撃的なイントロの”El Barrio”は斬新極まりないです!
何と言ってもこの前半の3曲がおすすめです!
そして4曲目の”You Know I Care”は、ピアニストで名作曲家でもあるデューク・ピアソン作のバラード曲です。
まるでジョン・コルトレーンの『Ballads』に収録されていそうな感じがするのは、マッコイのピアノの優しいコンピングから来るものでしょうか?
最後の5曲目、コール・ポーター作のスタンダード曲”Night And Day”も斬新なイントロから始まります。
この時代のジョーヘンは、次から次へとアイデアに溢れていたんでしょうね。
数多くある”Night And Day”の演奏の中で僕が一番好きなのは、このジョーヘンの演奏です。
他に管楽器が参加していないので、じっくりとジョーヘンのサックス演奏を聴くことが出来るので、もしかしたら彼の最高傑作はこの『Inner Urge』なのかもしれませんね。真っ先に聴くべき名盤です♪
Joe Henderson – 『Mode For Joe』
最後にご紹介するこのアルバムは、ジョーヘンにとって5作目のリーダー作で1966年に吹き込まれました。
この『Mode For Joe』にはこれまでの作品と違ってリー・モーガンやカーティス・フラーなどブルーノート・レーベルお抱えのジャズマンが多く参加しています。
ボビー・ハッチャーソンのヴィブラフォンまで咥えた豪華なセプテット編成です。
それだけに1曲目のジョーヘンの曲”A Shade Of Jade”から始まるテーメロディーの分厚い音に驚かされます。
しかしこれまたジョーヘンを代表する名曲だと言える演奏です。
この”A Shade Of Jade”のジョーヘンのソロは本当に素晴らしいです。
またソロの2番手のリー・モーガンもさすがの演奏です!
ケニー・ドーハムとは違い溌剌としたリー・モーガンの演奏はジョーヘンに引けを取らない名演です!
続く2曲目の”Mode For Joe”と3曲目の”Black”は、本作に参加しているピアニストのシダー・ウォルトンの作曲です。
シダー・ウォルトンもジョーヘンと同じくケニー・ドーハムに見出されたジャズマンになります。
ジョーヘンと同じようにハード・バップに軸足を置きながらも新世代のモード・ジャズを演奏する名手です。
そのためかこの2曲でのジョーヘンのソロは生き生きとしています!
そして4曲目のジョーヘンの曲”Caribbean Fire Dance”も聴き所です。
ラテン調のイントロ部分ではリー・モーガンが大活躍です!
確かにこういった曲にはテナーサックスよりもトランペットの高音が似合いますね。
ぶっちゃけジョーヘンのソロよりもリー・モーガンのソロの方がかっこよかったりもします!
5曲目のは、イントロのアンサンブルがとってもかっこいい曲です。
この曲もリー・モーガンのソロがやたらとかっこいい曲です!
最後の6曲目の”Free Wheelin'”は、そのリー・モーガン作の楽しいテーマメロディーの曲です。
ケニー・ドーハムと比べると、どうしてもリー・モーガンは目立ちますね!
ジョーヘンの作品なのに、リー・モーガンがすごく目立ってます!
僕もリー・モーガン大好きなのですが、一応主役はジョーヘンですよ!と言いたくなります。
前4作と比べると、大人数の編成ってのもありジョーヘンの影が少し薄くなっている気がします⁉
しかし収録曲や演奏陣の力量は超一流です!
名盤ではありますが、ジョーヘンというよりもリー・モーガンが目立っているので、もしかしたらリー・モーガン・ファンにおすすめすべきアルバムなのかもしれませんね?
でもだからってジョーヘンのサックスソロがショボいわけでは決してありませんので、ジョーヘン聴くなら外せない作品でもあります!
以上、『ジョー・ヘンダーソンがブルーノート・レーベルに残した5枚のリーダー作!』のご紹介でした。
ブルーノート・レーベル在籍時のジョーヘンにハズレはないと言いたくなるような名盤ばかりですので、これからジャズをもっと深く聴いていきたい!と思っている方は、5作品とも全て必聴ですよ♪
ジョーヘンやボビー・ハッチャーソンなど、新主流派が参加したグラント・グリーンの名盤『Idle Moments』も必聴です!
グラント・グリーンの最高傑作!?名盤『Idle Moments』をおすすめしています。
【PR】Amazonギフトカードのご紹介
Amazonギフトカードは、Amazonサイトのお買い物でご利用できるプリペイド式のカードです。
お買い物をする際に現金と同様に利用できるためクレジットカードの登録なしにAmazonでお買い物が出来ます。
クレジットカードの登録をしたくない方や、クレジットカードでのお買い物をしたくない方にもおすすめです。
他に関連するお勧め記事
ジョー・ヘンダーソンが2つのカルテットで録音した代表作『Tetragon』を聴こう♪
ジョー・ヘンダーソンが自身のクインテットを率いてクラブ・ライトハウスに出演した名ライヴ盤を聴こう♪
オーヴァーダビングも多用したジョー・ヘンダーソンの1972年のジャズ・ロック作品『Black Is The Color』を聴こう♪
ジョー・ヘンダーソンのマルチな才能が垣間見えた1973年の名作『Multiple』を聴こう♪
ジョー・ヘンダーソンが1973年に制作した壮大なコンセプト・アルバム『The Elements』のおすすめ♪
【スピリチュアル・ジャズの名作】ジョー・ヘンダーソンの『Black Narcissus』を聴こう♪
※このブログに掲載しているイラストや写真、テキスト等の無断引用・無断借用・無断転載・無断使用は固くお断りしております。ご利用はご遠慮ください。