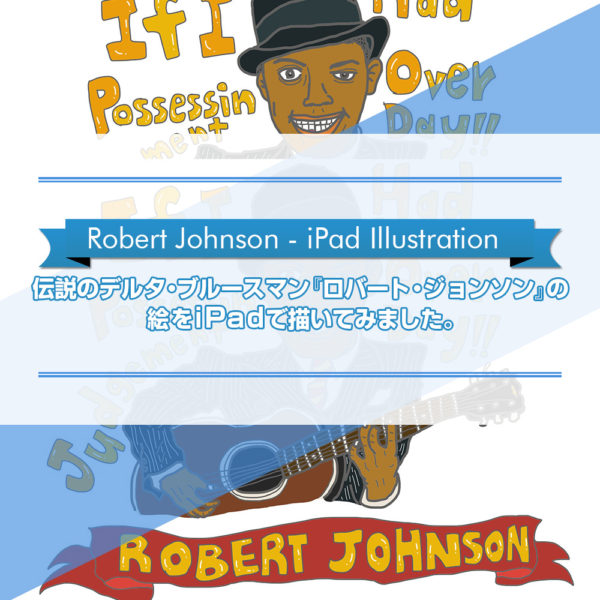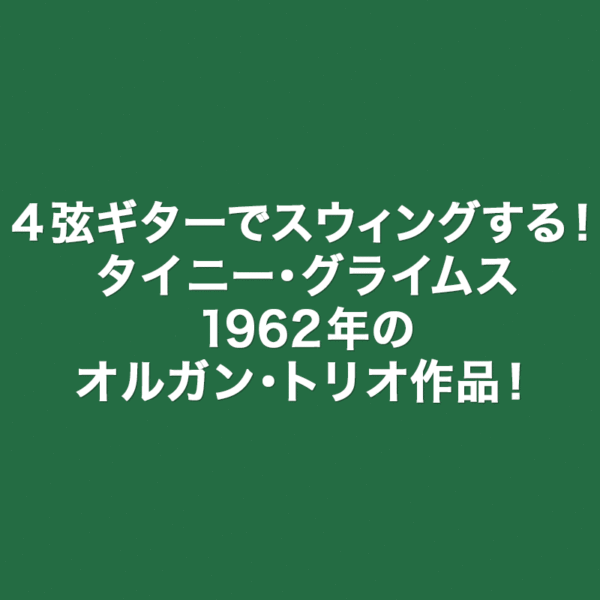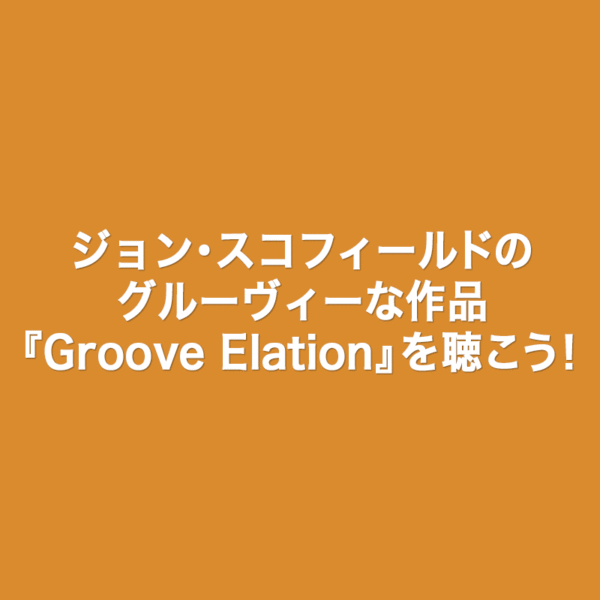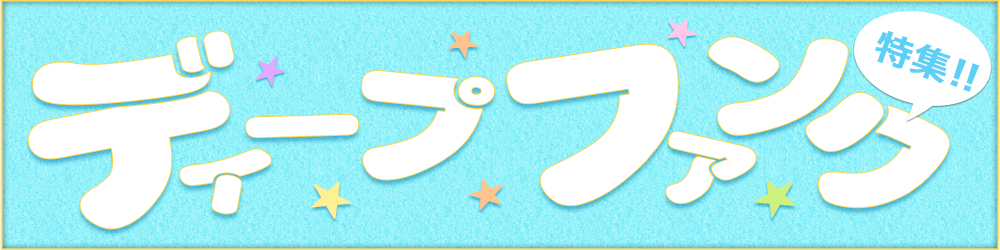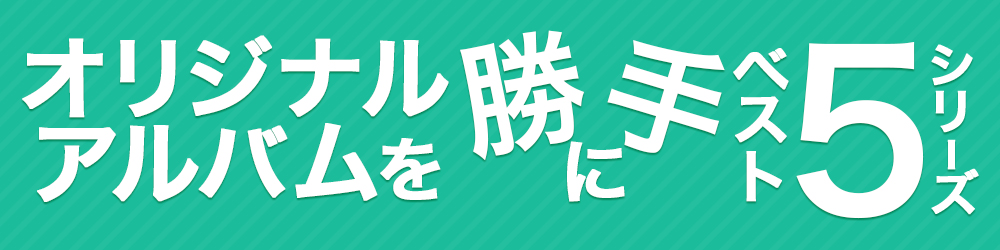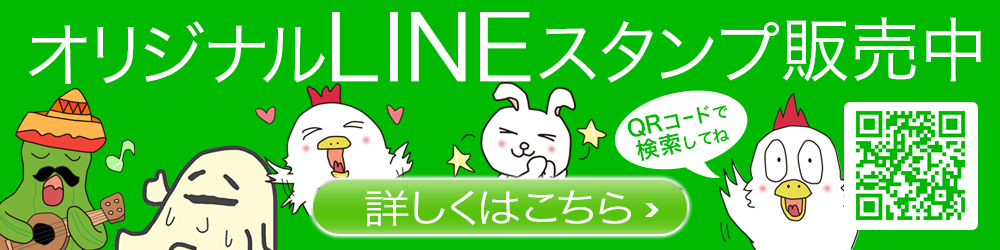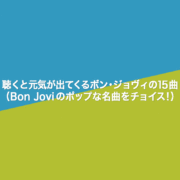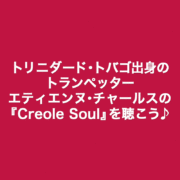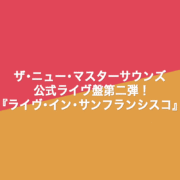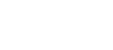
2019/04/15
ロックな気分のチャーリー・ハンターの2作品『Copperopolis』と『Mistico』を聴こう♪
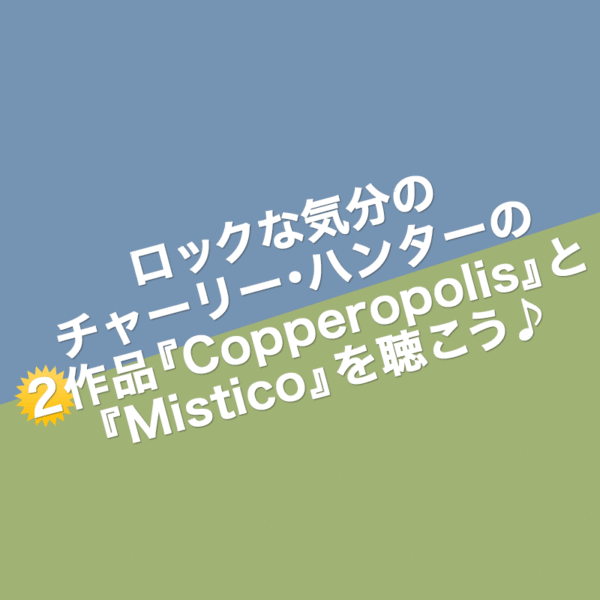
チャーリー・ハンターが2006年と2007年に制作したロックな気分の2作品『Copperopolis』と『Mistico』をご紹介します。
特殊な仕様の8弦ギターを用いて一人二役でギターとベースを同時に演奏する名手チャーリー・ハンター
実はこのブログでも何回か名前だけは登場していたギタリストのチャーリー・ハンターです。
ギタリストと言っても特殊なのですが、通常の5本のギター弦と、6弦の代わりにベース弦が3本付いた特殊8弦ギターを使用しています。(※最近は7弦のギターも使っているようです。)
これはギター1本で「オルガンのような厚みのあるサウンド」を表現するためだとも言われています。
5本のギター弦は上から(A→D→G→B→E)レギュラー・チューニングで使用しているようです。
本来であれば、6弦の(E)弦が必要なのですが、チャーリー・ハンターは代わりにベースの2~4弦の(E→A→D)を付与した特殊な8弦ギターを使っています。
そのギターをギター・アンプとベース・アンプに繋いで、ギターのパートとベースのパートを同時に一人二役で弾く特殊な奏法です。
といっても、ベース・パートを同時に演奏するギタリストは、100年前から存在していました。
それこそブルースの歴史上の人物ロバート・ジョンソンなんかがそうです。
伝説のデルタ・ブルースマン『ロバート・ジョンソン』の絵をiPadで描いてみました。
ロバジョンもギターの5~6弦を使用してベース・パートを弾きながら残りの4本の弦でコードを奏でていました。
初めてロバジョンのギターを聴いた若かりし頃のキース・リチャーズは「もう1人のギタリストは誰だろう?」と思ったという話はローリング・ストーンズ・ファンには有名な話ですね。
もちろんロバジョンが一人二役でベース・パートとコード弾きをしながら歌っています。
それと同じようにチャーリー・ハンターも、ベース・パートを弾きながらコード演奏をして、更に曲のテーマ・メロディーやギター・ソロも弾きます。
ちなみに特殊なギターを使用していたといえば、こちらのブログでも過去に4弦のみのギターを弾くタイニー・グライムスを取り上げています。
4弦ギターでスウィングする!タイニー・グライムス1962年のオルガン・トリオ作品!
但し、タイニー・グライムスの場合はベース・パートを弾くことはありません。
あくまでもコード演奏をテーマ・メロディーやギター・ソロを弾く、通常のギタリストと同じ演奏方法です。
チャーリー・ハンターは完全に一人二役で演奏するので、バンド内に彼がいるとベーシストが不要になります。
なので、今回ご紹介する2作品はどちらもトリオ編成で制作されているのですが、ベーシストは参加していません。
ドラムとサックスもしくはピアノだけで済みます。
また別の作品ではドラムとのデュオ作品も存在するのですが、チャーリー・ハンターの場合は1人でギター+ベースなので、自動的にギター・トリオと同じ音の厚みが生まれます。
特殊な演奏家ですが、共演する方としたらなかなか便利ですよね。
そのためなのか、多くのミュージシャンの作品にもゲストで参加していたりします。
例えばディアンジェロの名盤『Voodoo』に収録されている”The Root”や”Spanish Joint”に”Greatdayndamornin’ / Booty”などの曲でギターとベースのパートを演奏しているのは、このチャーリー・ハンターになります。
また最近ではスナーキー・パピーのライヴに参加したりもしていました。
そういった客演作品でも聴けるのですが、チャーリー・ハンターは普通のファンク系ギタリストとは違った変わったリズム感でカッティングをすることがあります。
これはベース・パートも同時に演奏するためこういった変拍子的なカッティングをするようになったのかな?と感じられますが、おそらく本人は自然とこういったリズムで弾いているんでしょうね。
こういった通常のギタリストにない感覚が、同じギターを弾く僕としてもチャーリー・ハンターを聴いていて面白い部分だったりもします。
ジャンル分けの難しさ…『ジャム・バンド』という曖昧なジャンル分け
さて、そんな特殊な演奏方法を持つチャーリー・ハンターの作品は、基本はギターのメロディーが中心のインスト作品ばかりです。
なので、ジャズ系のギター作品がお好きな方におすすめしたいのですが、なかなか難しい部分もあります。
というのは、作品ごとにかなり雰囲気が違うからです。
チャーリー・ハンター自体の演奏面での一貫性はあるのですが、作品によってジャズっぽかったりロックぽかったりファンクぽかったり、更にはフリー・ジャズ的な作品も存在しています。
一応、ジャンル分けする場合は大まかには『ジャズ』に分類されることが多いと思います。
といっても、アメリカとかだったら割と適当に「グルーヴィーなインスト作品」は、まとめて『ジャズ』に分類されていたりもします。
必ずしも「スウィングする4ビートのストレート・アヘッドな音楽」だけが『ジャズ』にカテゴライズされるわけではありません。
その中には「ロックの要素」や「ファンクの要素」に「ヒップホップの要素」までも混じっていることがあります。
だから『ジャズ・ロック』や『ジャズ・ファンク』に『ジャジー・ヒップホップ』なんていうジャンルが存在しているのですが、これらの音楽性も全てひっくるめて『ジャズ』に分類されています。
と言ったわけで、例えば大型のCD屋さんなんかでチャーリー・ハンターを探す場合は『ジャズ』コーナーを探してみて下さい。
ほとんどのCD屋さんではそちらにチャーリー・ハンターの作品が置かれています。
稀にロックやポップスのコーナーに置かれている場合もありますが、まぁ気にしてはいけません。
ちなみにマニアックなお店だと『ジャム・バンド』というコーナーに設置されていることもあります。
これは間違いではなくって、そのお店の店主がマニアックな音楽好きってことです。
この『ジャム・バンド』というのも定義が難しいのですが…
僕が思うに、「グレイトフル・デッドを始祖とする様々な音楽的要素が混じったバンドで、ライヴなどで長尺のアドリヴ・ソロを得意とするミュージシャン」なのかな?と思います。
『ジャム・バンド』にカテゴライズされるアーティストの多くは、アドリヴ・ソロを弾くのが得意なミュージシャンばかりです。
このチャーリー・ハンターもそうですが、グレイトフル・デッドのジェリー・ガルシアもそうですし、ジミー・へリングなんかもそうです。
彼らはライヴではかなり長めのアドリヴ・ソロを延々と弾くことが出来ます。
また『ロック』だけでなく『ジャズ』や『ブルース』に『ファンク』や『カントリー音楽』までも幅広い音楽性が混じった楽曲を演奏します。
そういった音楽性から”jam”=「即興演奏」というジャンル名になったのではないかと思われます。
よくアメリカのミュージシャンが「この曲はスタジオでジャムってるうちに出来た曲だ!」とかインタビューで応えていたりするのですが、その「ジャム」とは細かい打ち合わせもなく即興でその場で演奏することを言います。
こういったジャム演奏は、ジャズ・ミュージシャンであれば「出来て当たり前」のことなんです。
なので、『ジャム・バンド』にカテゴライズされるミュージシャンの多くは『ジャズ』の要素を持っていたりします。
と、そうなってくると「グレイトフル・デッドってロックじゃないの?」と言われそうなのですが、「はい、ロックです。」
グレイトフル・デッドは『ロック』コーナーに置かれています。
しかし『ジャズ』からの影響も受けています。
これはデッドのベーシストのフィル・レッシュがインタビューで語っていたのですが、彼らも若い頃1965年にリリースされた『至上の愛』を聴きまくっていたようです。
この作品は、当時の音楽好きのヒッピーたちに受けが良かったらしく彼らはイケナイお薬でトリップしながらコルトレーンのアドリヴ演奏を聴いて瞑想の世界に旅立っていたようです。
ジェリー・ガルシアステージで長尺アドリヴ・ソロを弾くようになったのも、そういった経験からジョン・コルトレーンの影響があるんだと感じられます。
プレイ・スタイルこそ『ジャズ』ではありませんが、おそらくその『アドリヴ演奏における精神性』から影響を受けているのでしょう。
そういう音楽を最初にやった歴史上のバンドがグレイトフル・デッドなので、デッドは『ジャム・バンド』始祖扱いをされていたりします。
他にもフィッシュやウォーレン・ヘインズのガヴァメント・ミュールなんかも『ジャム・バンド』扱いされることもあります。
しかし彼らは正確には『ジャズ』ではなく『ロック』だと思います。
この辺が曖昧で分かりづらいのです、大まかには『ジャズ』にカテゴライズされるチャーリー・ハンターも『ジャム・バンド』と言われることがあります。
またメデスキ、マーチン&ウッドやジョン・スコフィールドのウーバー・ジャムなんかも同じく、大きくは『ジャズ』に分類される『ジャム・バンド』です。
他にはソウライヴまでも『ジャム・バンド』扱いされることもあるんです!
個人的にはソウライヴは『ジャズ・ファンク』だと思うのですが『ジャム・バンド』の要素もあるので何とも言えません。
と、ここまで長いこと『ジャム・バンド』について書いてきたのですが、なぜ書いたかというと僕のブログでは「MUSIC」のカテゴリー内に”Jazz”や”Blues”のよう更に細かいタグでジャンル分けしているんです。
その際にチャーリー・ハンターを”Jazz”のタグをつけて大まかに分類すると…「この作品どこがジャズなの?」となっちゃうので別で“Jam Band”というタグを設置しました。
これからこのブログでチャーリー・ハンターの作品も取り上げていきたいと思ったので、“Jam Band”にジャンル分けしたんです。
長くなりましたがこのブログに“Jam Band”というタグが存在するのは上記のような理由からです。
それでは今回のチャーリー・ハンターの作品をご紹介したいと思います。
2006年と2007年にリリースされたロックな気分の2作品『Copperopolis』と『Mistico』
今回ご紹介したいチャーリー・ハンターの作品は、2006年にリリースされた『Copperopolis』と2007年にリリースされた『Mistico』の2作品です。
チャーリー・ハンターの作品は、アルバムごとにかなり違った雰囲気の物が多いんです。
中には2004年にリリースされた『Latitude』のように、かなりアヴァンギャルドで聴きづらいアルバムもあります。
もしこういったフリーキーな作品を最初に聴いてしまって、「チャーリー・ハンターってすごく聴きにくい…。」というイメージを抱いてしまって、その他の作品も聴かず嫌いになってしまったらもったいないな~と思いました。
そこでまずは聴きやすい2作品をご紹介して、チャーリー・ハンターのことを知ってもらいたいと思い今回この2作品をご紹介しようと思いました。
なぜこの2作品にしたのか?というと、この2作品には共通点がいくつかあります。
まずアルバム・ジャケットの雰囲気も似たような感じです。
どちらもコラージュ作品のようでアーティスティックな仕上がりです。
アルバムをインテリアとして飾ってもオシャレです♪
またこの作品を制作する時期のチャーリー・ハンターは、「今、オレはロックな気分なんだ!」とのことです。
当時のチャーリー・ハンターは、少年時代に戻ったかのようにジミ・ヘンドリックスやレッド・ツェッペリンにザ・フーなんかを聴き直していたようです。
そういったロック・バンドからインスパイアされて制作されたこの2作品は、それまでの『ジャズ/フュージョン』的な作品よりも『ロック』な感触が強く感じられます。
そのため、聴きづらい作品も多いチャーリー・ハンターの中では比較的耳馴染みの良い作品だと思います。
最初からアヴァンギャルドな作品を好きになる方もいらっしゃるとは思いますが、でもやはりこういった『ロック』で聴きやすい作品の方が、より好きになってくれる人の数は多いと思います。
もちろん僕自身も、アヴァンギャルドな作品よりもこういった『ロック』で聴きやすい作品の方が好きです♪
一応、僕自身はそこそこ色んな音楽を聴いてきた方だとは思うのですが、しかしそれでも「アヴァンギャルドなで難解な音楽の方が上だ!」なんてことは一切思っていません。
むしろ、人口に膾炙できるような『ロック』でキャッチーな作品のどこが悪い?と思うぐらいです。
僕は『ジャズ』と同じぐらい『ロック』も大好きです。
どちらが上とか下なんてことはありません。
どちらも同じくらい重要な音楽ジャンルです!
なので、こういった『ジャズ』と『ロック』が混じった作品をもっと多くの人におすすめしたいと思うんです。
このブログの”Jazz”のカテゴリー内も、どちらかというと『ジャズ・ロック』系の作品ご紹介が多いのもそういった理由です。
『ロック』を聴く人にも、もっと『ジャズ』も聴いて欲しいので、聴きやすい『ジャズ・ロック』作品を特におすすめしています。
というわけで、今回このブログで初めてご紹介するチャーリー・ハンターの作品は『ロック』のダイナミズムを感じられるこの2作品にしました。
それでは、1枚ずつご紹介したいと思います。
Charlie Hunter – 『Copperopolis』
01.Cueball Bobbin’…
02.Frontman
03.Swamba Redux
04.Copperopolis
05.Blue Sock
06.The Pursuit Package
07.A Street Fight Could Break Out
08.Drop The Rock
09.Think Of One
Personnel:
Charlie Hunter – Guitar [8-string]
John Ellis – Bass Clarinet, Tenor Saxophone, Organ [Wurlitzer], Melodica
Derrek Phillips – Drums
アルバムの内容
2006年にリリースされた『Copperopolis』というアルバムです。
1993年にデビューしたチャーリー・ハンターにとって14枚目のアルバムになります。
本作は、チャーリー・ハンターの他にジョン・エリスとデレク・フィリップスの3人でニューオーリンズのスタジオにて制作されています。
ギターとベースのパートを担当するのはチャーリー・ハンターですが、ジョン・エリスはテナー・サックスにバス・クラリネット、メロディカにウーリッツァと色々な楽器を担当しています。
デレク・フィリップスのみドラムだけを担当していますが、しかし彼の叩き出すビートが本作では重要な役割を果たしているとも言えます。
それはチャーリー・ハンターのロックに歪んだギターによる過激なイントロから始まる1曲目”Cueball Bobbin'”から聴くことが出来ます。
60年代風ロックのようなファズで激しく歪んだギターの音色にロックなドラムビート、そこに絡むメロディカのオモチャのようなユニークな音色…アヴァンギャルドな感触を持たせつつも、ロックのリズムの持つ聴きやすさも併せ持ってます。
チャーリー・ハンターのギターのサウンドは、基本はジョンスコのようにコーラス・エフェクターを使うぐらいであまり歪ませないのですが、ロックな気分の本作では歪ませたトーンで弾いていることがほとんどです。
次の2曲目”Frontman”も同じく、それまでのチャーリー・ハンターとは違ったディストーション・サウンドのギターがロックしています!
しかしギター・ソロに関してはホールトーン・スケールなんかを用いたアウト・フレーズを積極的に使用するので、やはりそこには『ジャズ』の要素を垣間見ることが出来ます。
3曲目の”Swamba Redux”のギター・ソロからようやくいつものコーラス・エフェクターを深く掛けたギター・サウンドを聴くことが出来ます。
もはやこの音色は「あ、チャーリー・ハンターだ!」と一聴してわかるぐらい彼のトレードマークになっていますね。
3~5曲目そしてセロニアス・モンクのカヴァー曲である10曲目の”Think Of One”では、ジョン・エリスによるサックスを聴くことが出来ます。
こういった楽曲では、ジャズ・ロックなサウンドを楽しむことが出来ます。
T.J.カーク時代からなのですが、チャーリー・ハンターはセロニアス・モンクの楽曲をよく取り上げることがあります。
その辺はやはり彼の本質はジャズ・ギタリストなんだろうな~と感じさせてくれる部分ですね。
ちなみにその10曲目の”Think Of One”は、デレク・フィリップスのドラム・ソロもあります。
これがまた凄いドラム・ソロなので必聴です♪
本作は「ロックな気分」のチャーリー・ハンターを支えるデレク・フィリップスのドラミングがあるからこそ、他の作品よりも聴きやすいアルバムに仕上がっていると言えます。
やはり何だかんだで、ロックの持つダイナミズムは耳馴染みが良く聴きやすいですね♪
上記でも「聴きやすいアルバム」と何度か書きましたが、「チャーリー・ハンターの作品群の中では聴きやすいアルバム」ということですのでお間違いないように。
キャッチーなリフがあったり、盛り上がりのあるサビがあるわけではありません。
そもそも『歌』が入っていません。
ビートルズやローリング・ストーンズのような「ロック」を想像して聴くと、碌なことが起きません。
あくまでもギターやサックスが中心のインスト物です。
しかしそういったロック・ファンにも比較的聴きやすいと思われる「ロックの要素を持ったジャズ作品」を聴いてもらえたら…と思います。
Charlie Hunter – 『Mistico』
01.Lady!
02.”Speakers Built In”
03.Estranged
04.Balls
05.Wizard Sleeve
06.Drop A Dime
07.Spoken Word
08.Special Shirt
09.Mistico
10.Chimp Gut
Personnel:
Charlie Hunter – Guitar [8-string]
Erik Deutsch – Piano, Electric Piano [Fender Rhodes], Keyboards [Casio Tone]
Simon Lott – Drums
アルバムの内容
『Copperopolis』から1年後の2007年にリリースされた『Mistico』です。
本作も前作同様に「ロックな気分」のチャーリー・ハンターの作品なので比較的聴きやすいアルバムに仕上がっています。
しかし『Copperopolis』と同じトリオ編成でも、本作ではチャーリー・ハンター以外のメンバーが入れ替わっています。
ドラムにはサイモン・ロットが、そして鍵盤奏者としてエリック・ドイッチュが参加しています。
エリック・ドイッチュは本作であらゆる鍵盤楽器を駆使していますが、リード楽器を演奏することはありません。
なので、本作では華やかなホーンがない分よりチャーリー・ハンターのギター・ソロを集中して聴くことが出来ます。
基本路線は前作の『Copperopolis』と同じように1曲目”Lady!”からロックに歪んだギターのサウンドを聴くことが出来ます。
2曲目の”Speakers Built In”なんかは、60年代サイケデリック・ロックからの影響を感じられなくもないです。
メインのギター・リフが終わると1分5秒辺りからエリック・ドイッチュによるカシオトーンを使ったと思われる幻想的なソロが始まります。
この音色がなんとなく60年代サイケデリックですね♪
またギター・ソロではオートワウを使用しているようです。
最近ではあまりワウを使うことがなくなりましたが、初期の頃はチャーリー・ハンターも積極的にワウを使っていました。
4曲目の”Balls”なんかは、ジミヘンやレッド・ツェッペリンの影響を受けたようなキャッチーなロック・ギターのリフで始まる曲です。
5曲目の”Wizard Sleeve”は、まるでメデスキ、スコフィールド・マーティン&ウッドも取り上げそうないかにも『ジャム・バンド』といった曲調です。
重心の重いドラムのビートから始まる6曲目の”Drop A Dime”や7曲目の”Spoken Word”のドラム・ソロを聴いていると、やはりこういったロック系の楽曲にはドラムによるダイナミズムが重要なんだと感じさせてくれますね。
「ロックな気分」のチャーリー・ハンターを支えてくれるのは、やはりドラムのロック・ビートにあります。
以上、【ロックな気分のチャーリー・ハンターの2作品『Copperopolis』と『Mistico』を聴こう♪】でした。
『ジャム・バンド』のお話なども含めて長くなりましたが、変則8弦ギター使いのチャーリー・ハンター僕のお気に入りのミュージシャンです。
この他にもまだまだチャーリー・ハンターの面白い作品はありますので、今後もご紹介していきたいと思います。
そんな数多くあるチャーリー・ハンターの作品群の中にあってもこの『Copperopolis』と『Mistico』が僕のお気に入りの作品になります。
やはりこういった『ロック』の要素のある作品は普段から日常的に聴くことが出来ます。
アヴァンギャルドな作品は、どうしても毎日聴きたいとは思えません…聴く方もシンドイですよね。
でもこの『Copperopolis』と『Mistico』なら毎日でも聴くことが出来ます。
その一番の理由はなんといっても2作品に共通するドラムによるロックなリズムがノリやすいからだと思います。
音楽において、ジャンルを決定づけるようなリズムって本当に大事ですよね!
「ロック好きだけれども今後はもっと音楽性を広げてジャズなんかも聴いてみたいな~」といった方にもおすすめしたい2作品です♪
他に関連するお勧め記事
『チャーリー・ハンターの代表曲のひとつ”Mestre Tata”が収録された名盤『Right Now Move』を聴こう♪
ジョン・スコフィールドのグルーヴィーな作品『Groove Elation』を聴こう!
ブラック・アイド・ピーズのバックでもギターを弾くジョージ・パホーンJr.のジャズ・ファンク作品『Fried Plantains』を聴こう♪
※このブログに掲載しているイラストや写真、テキスト等の無断引用・無断借用・無断転載・無断使用は固くお断りしております。ご利用はご遠慮ください。