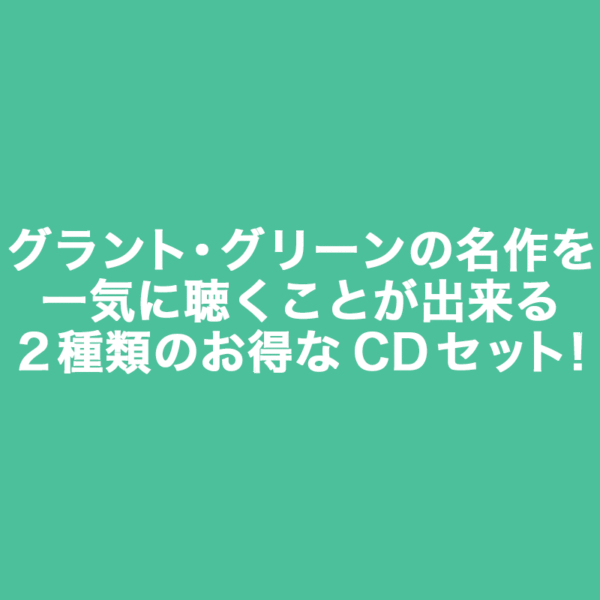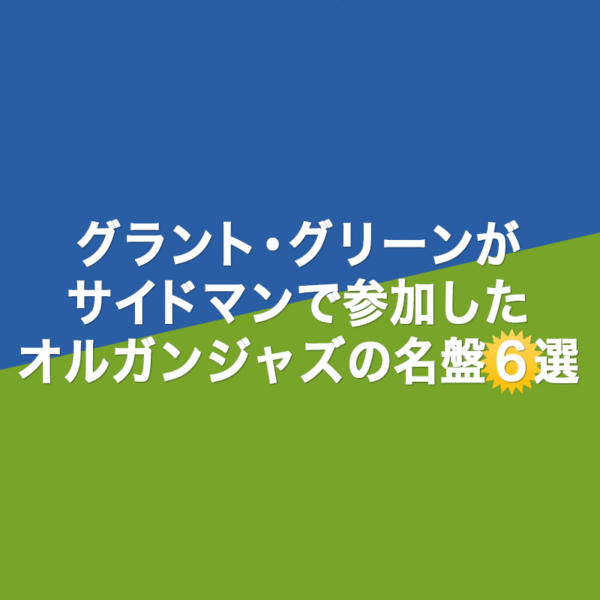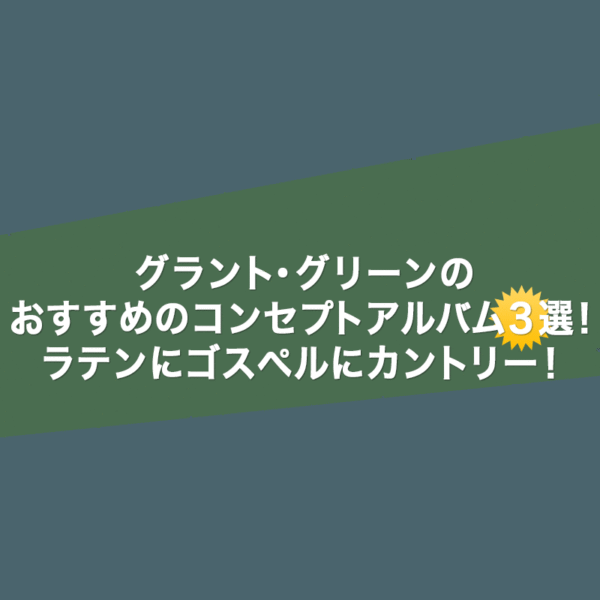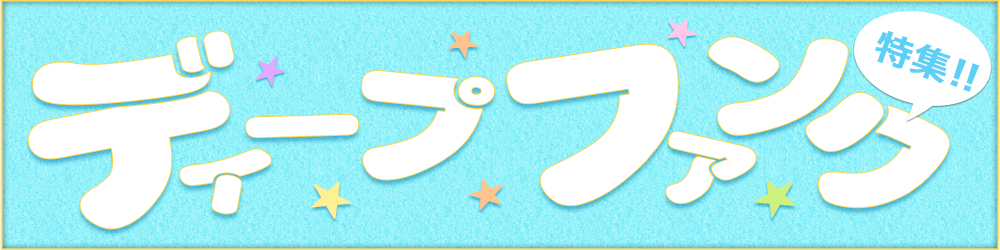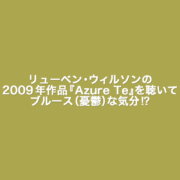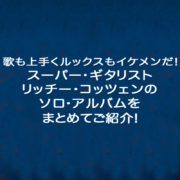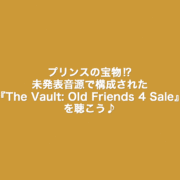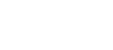
2018/01/10
グラント・グリーンの記念すべき初リーダー作品『Grant’s First Stand』を聴こう!

グラント・グリーンの記念すべき初リーダー作品
グラント・グリーンがブルーノート・レーベルと契約するまでの歩み
この作品は僕の一番好きなギタリストであるグラント・グリーンの初リーダー作品になります。
アルバムタイトルの「ファースト・スタンド」の通りにこのアルバムからグラントの輝かしいキャリアは始まりました。
ミズーリ州セントルイスに1931年6月6日に誕生したグラントは、13歳の頃から様々なローカルバンドでプレイをしていた早熟なギタリストでもありました。
そんなグラントが正式にプロとしてのキャリアを歩み始めたのは同じセントルイス出身のテナー奏者ジミー・フォレストに見いだされてからです。
シカゴで録音し、同地のデルマークレーベルからリリースされた『All The Gin Is Gone』がグラントのプロギタリストとしてのレコードデビューになります。
その後、オルガン奏者のサム・レイザーやドラムのデイヴ・ベイリー等のアルバムでサイドマンを務めた後、たまたまグラントの演奏を耳にしたアルト奏者のルー・ドナルドソンに気に入られてブルーノート・レーベルに紹介されました。
ブルーノートの創始者アルフレッド・ライオンはもともとブルージーなジャズ演奏が好きな人物でした。
それも古いトラディショナルな曲のカヴァー曲だけでなく、新しく独自性のあるジャズ・ブルース調の曲です。
そのためブルーノートの初期の作品群には彼のリクエストで、リーダー作を作るミュージシャンは必ずのように自作のジャズ・ブルース曲を1曲用意しなければいけないぐらいでした。
そういった環境に最も適したジャズ・ギタリストであるグラントは直ぐにライオンに気に入られました。
グラントの最も得意とする演奏はブルージーなジャズですので願ったりかなったりだったんでしょうね。
ライオンに大いに気に入られたグラントは、この初リーダー作をリリースした1961年だけでも立て続けに5枚のアルバムを制作しています。
またサイドマンとしても9枚のアルバムに参加しています。
ライオンの待ち望んだ黒人ジャズギタリスト
ブルージーでソウルフルな黒人特有の粘っこさのあるジャズギタリストが好きなライオンでしたが、チャーリー・クリスチャン以降、黒人のジャズギタリストが中々登場しませんでした。
それまでの白人ジャズギタリストと言えば、バーニー・ケッセルにハーブ・エリスにタル・ファーロウやルー・メッカにサル・サルバドールなど…スウィンギーで洗練されてはいるけれども、やはり黒人ギタリストの腰のあるタメたリズム感などがないのも事実なんですよね。
そんな中、1950年代後期についにライオンの待望のブルージーなギタリストがデビューを果たします。
それがケニー・バレルでした。
そしてそのちょっと後にグラント・グリーンが上記のいきさつでライオンに出会いました。
2人とも黒人特有のタメを効かせたブルージーさを持ち、ホーンライク(管楽器の様な)で骨太なシングルトーンのギターソを得意としていました。
まさにライオンの探し求めていたジャズ・ギタリストが彼ら2人だったのです。
そういったわけで、デビューから間もなくこの2人はたくさんのアルバムに参加することとなりました。
それではそんなグラント・グリーンの初リーダー作のご紹介です。
Grant Green – 『Grant’s First Stand』
01.Miss Ann’s Tempo
02.Lullaby of the Leaves
03.Blues for Willareen
04.Baby’s Minor Lope
05.’Tain’t Nobody’s Bizness If I Do
06.A Wee Bit O’Green
Personnel:
Grant Green – guitar
Baby Face Willette – organ
Ben Dixon – drums
Recorded January 28, 1961.
『Grant’s First Stand』の聴き所
グラント・グリーンの魅力を最大限に引き出す編成はなんと言ってもオルガンとのトリオです。
このアルバムではグラントと同時期にデビューをしたオルガン奏者のベイビーフェイス・ウィレットが参加しています。
またベイビーフェイス・ウィレットの初リーダー作には逆にグラントがサイドマンで参加もしています。
この頃の2人の相性は抜群なんですが、その後ベイビーフェイス・ウィレットは短期間の華やかな活動から身を引き、ローカル・ミュージシャンに戻りシーンから消えていきました。
ドラムのベン・ディクソンは、この後も長きにわたりグラントと活動を共にします。
オルガン奏者のビッグ・ジョン・パットンと ベン・ディクソンとのオルガントリオでグラントは何作も名演を残しています。
その辺のお話はまた今後取り上げていきます。
まずはこの記念すべき初リーダー作です。
1曲目はグラントが自分の妻に捧げた曲です。
デビューアルバムの最初の曲を奥さんに捧げた曲から始めるというなんとも憎い演出です。
スウィンギーで軽快なテンポの中、楽しげなテーマメロディーをシンプルに奏でます。
「さぁ始めるぞ!」という感じのする勢いのある曲調です。
デビュー曲にピッタリですね!
この頃から既にグラントのシグネチャー・リックとも言うべき「シーケンス・フレーズ」による繰り返しがギターソロで聴けます。
続く2曲目の”Lullaby Of The Leaves(木の葉の子守唄)”はジョー・ヤングとバーニス・ペトケレが1932年に書いた曲です。
エラ・フィッツジェラルドなんかもこの曲を歌っています。
どこか物哀しくも聴こえるテーマメロディーをミディアム・テンポで歌心たっぷりに弾いています。
グラントの特長として、こういった渋い曲調のテーマメロディーを弾くのが得意なところです。
しかも他のジャズ・ギタリストであれば、コードを混ぜたりダブルストップで音圧を増したり複雑にアレンジしてテーマを弾きがちですが、グラントはシングルトーンでオリジナルのテーマメロディーを全く崩さずにそのまま弾きます。
本来ならつまらない演奏になりそうなところなのですが、独特のタイム感を持ったグラントが弾くとシンプルなフレーズでも歌心が感じられるんです。
こういったグラントの演奏を聴いていると難しいアレンジなんて必要ないんだなって感じます。
シンプルなフレーズでもリズムに乗って歌うように弾くことが最も重要なんですね。
さて、次の3曲目はグラント作のジャズ・ブルース曲です。
コール・アンド・レスポンス(応対形式)によるテーマメロディーは教会音楽のゴスペルからの影響でしょう。
グラントは幼い頃から教会に通い、そこで音楽に触れあっていたようです。
たまに演奏もしていたとも聞きます。(その頃はギターだけでなくバンジョーも演奏!)
いかにもオルガントリオで演奏するのにピッタリの曲なので、グラントのギターソロも伸び伸びとしています。
グラントのルーツが垣間見える名演ですね。
4曲目はオルガン奏者のベイビーフェイス・ウィレットによるアーシーな香りが漂うこれまたジャズ・ブルース曲です。
テーマメロディーはオルガンとのユニゾンです。
ベイビーフェイス・ウィレットの作曲ですが、ギターソロはその後のグラントの作品でも聴くことのできる彼の手癖フレーズ満載です。
続く5曲目の”‘Tain’t Nobody’s Business If I Do”は、ブルース好きならフレディ・キングの名演が思い浮かびますね。
ブルースの女帝ベッシー・スミスが歌い有名になったトラディショナルな曲です。
ジャズシンガーではビリー・ホリディも歌っています。
オルガンのホーリーな響きがまるで教会に礼拝に来ているかのような気分になります。
グラントは、1音1音に魂を込めて美しくギターソロを弾きこなしています。
最後の6曲目はグラント作のけだるいムードが漂うジャズ・ブルース曲です。
アップ・テンポな1曲目で始まり、アルバム最後の締めはスロー・テンポな曲で終わる見事な選曲です。
全6曲中グラントは半分の3曲を自身で作曲しています。
そのどれもが彼のお得意のジャズ・ブルース曲です。
しかも相性の良いオルガンがピッタリ合う様な曲調ばかりです。
初リーダー作にして「グラント・グリーンとはこういうギタリストだ!」とはっきりとわかる名刺代わりの名盤と言えるでしょう。
ジャズ・ギタリストによるジャズ・ブルース系の曲が聴きたい方には絶対にお勧めのアルバムです!
ちなみにアルバムタイトルの『Grant’s First Stand』という曲は別のアルバムに収録されていたりもします。
他に関連するお勧め記事
グラント・グリーンの名作を一気に聴くことが出来る2種類のお得なCDセットのおすすめです♪
グラント・グリーンがサイドマンで参加したオルガンジャズの名盤6選
グラント・グリーンのおすすめのコンセプトアルバム3選!ラテンにゴスペルにカントリー!
※このブログに掲載しているイラストや写真、テキスト等の無断引用・無断借用・無断転載・無断使用は固くお断りしております。ご利用はご遠慮ください。