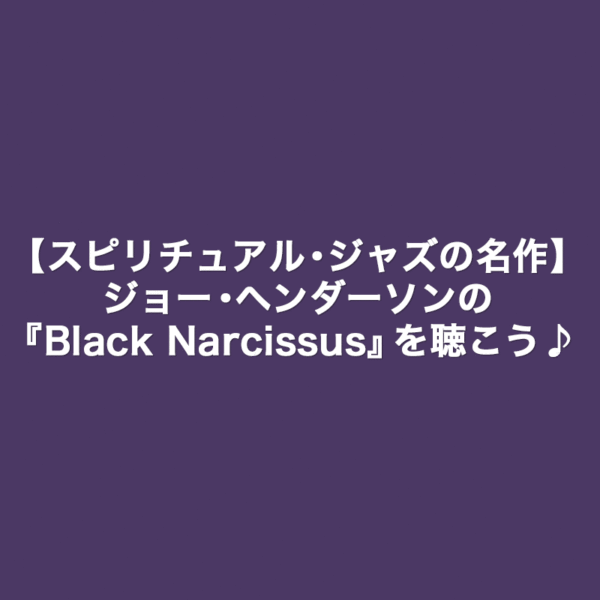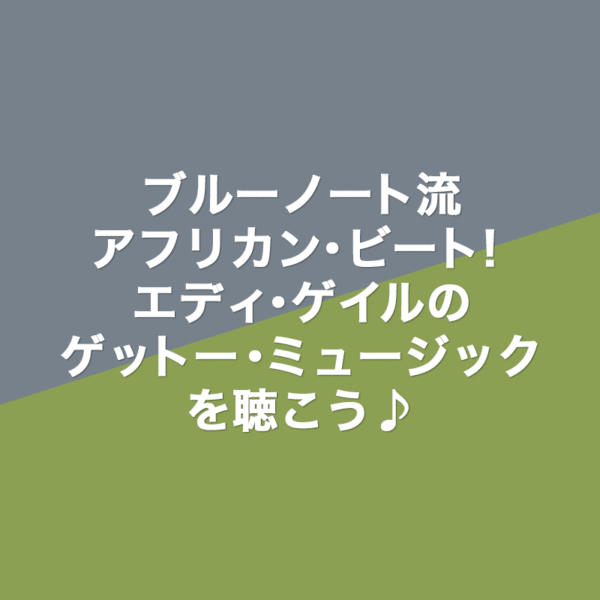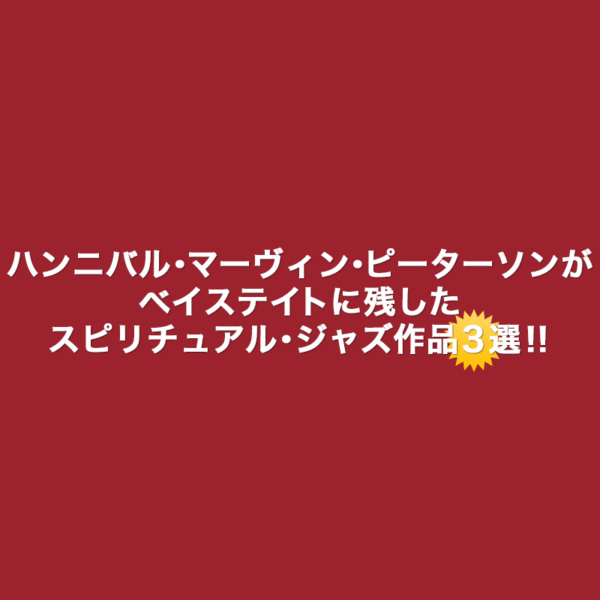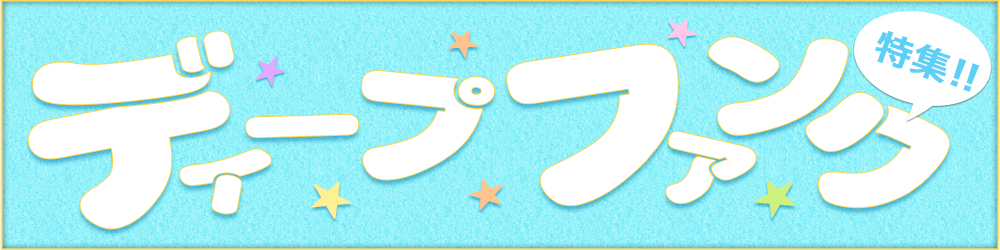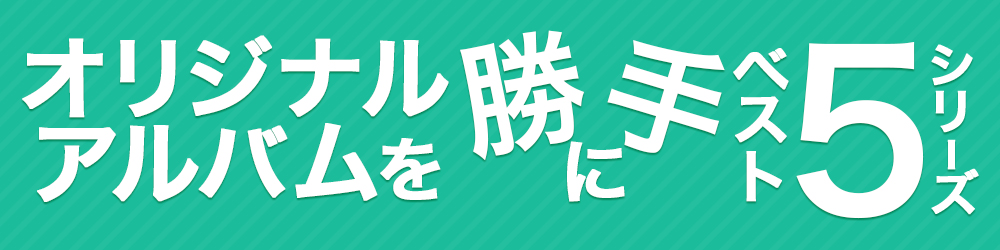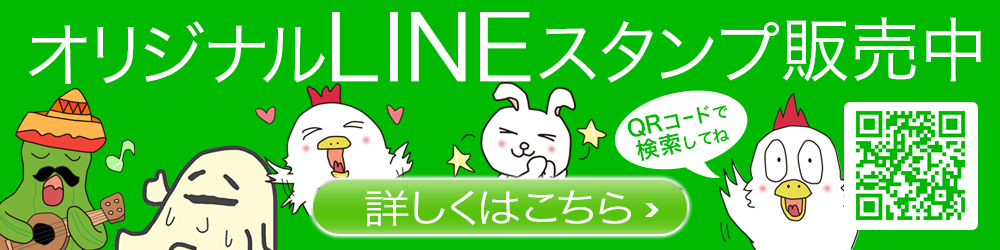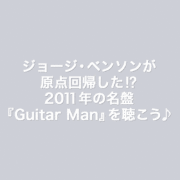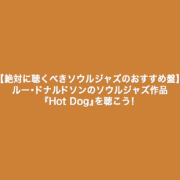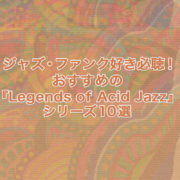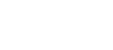
2021/06/12
オルガンのコルトレーン!ラリー・ヤングがブルーノート・レコードに残したおすすめの6作品
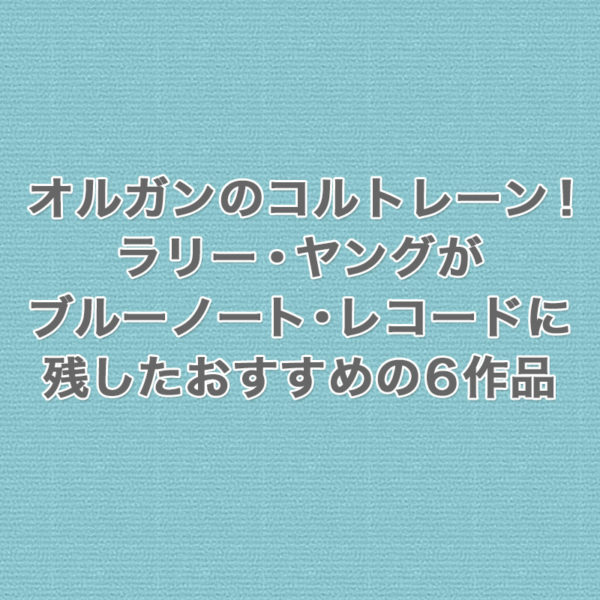
モード系オルガン奏者ラリー・ヤングがブルーノート・レコードに残した6作品をご紹介!
ありきたりなオルガン演奏に飽きたらラリー・ヤングを聴こう!
僕は、ギター以外の楽器では特にテナー・サックスとオルガンの音色が好きなのですが、そんな中でもラリー・ヤングは僕の好みに適したオルガン奏者でした。
高校生の頃にジョン・コルトレーンを聴いてジャズに目覚めた僕は、コルトレーンの演奏するテナー・サックスの音色が今も変わらず大好きです。
もちろんサックスの音だけでなく、他の演奏者にはみられないような、コルトレーンの鬼気迫る白熱のアドリヴ演奏にハマったからこそ、十代にしてジャズ好きに目覚められたわけです。
それから様々なジャズ・マンを聴いていくうちに、オルガン奏者のジミー・スミスを聴くことになりました。
それまで僕の中でのオルガンと言えば、ドアーズのレイ・マンザレクのクラシカルなロック演奏のイメージが強かったのですが、ジミー・スミスの演奏するジャズ・オルガンはあまりにも衝撃的でした!
そこからジャズ・オルガンにハマっていったのですが…
ジミー・マクグリフにリチャード・グルーヴ・ホームズ、 ブラザー・ジャック・マクダフにロニー・スミスにフレディー・ローチや”ビッグ”・ジョン・パットン、リューベン・ウィルソンにレオン・スペンサーにチャールズ・カイナードやチャールズ・アーランド等…
誰を聴いてもジミー・スミス、強いてはワイルド・ビル・デイヴィスやビル・ドゲット等のソウルフルでブルージーなジャズ・オルガンという共通した点がありました。
もちろんそういった演奏が悪いわけでもなく、嫌いなわけでもないのですが…オルガンという楽器はこういったアーシーな演奏しか出来ないのかな?と勘違いしていました。
その時、既に聴いていたマイルス・デイヴィスのエレクトリック期を聴いてみると、キース・ジャレットが革新的なプレイをオルガンで演奏していることに気付きました。
これは!と思った僕は、『Bitche’S Brew』を引っ張り出してきて聴いてみると…ここにも革新的なオルガン奏者が参加していたことに気付きます。
そこにクレジットされていた名前がラリー・ヤングでした。
あれ?どこかで聞いた名前だな?と思い、調べてみるとグラント・グリ-ンのアルバム『Talkin’ About!』や『Street of Dreams』に『I Want to Hold Your Hand』といった3作品に参加していたオルガン奏者でした。
ジョン・コルトレーン好きの僕は、コルトレーンを題材とした『Talkin’ About!』というアルバムが大好きでした。
このアルバムで、まるでジョン・コルトレーンになったかのように、革新的で熱いアドリヴ・ソロを演奏していたのがこのラリー・ヤングでした。
実はジャズを聴き始めた最初期の頃に、僕は既に『Bitche’s Brew』でラリー・ヤングを聴いてはいたのですが、意識するようになったのは、それから10年以上経った20代半ばになってからでした。
これまでにこのブログで取り上げたどのオルガン奏者よりも意識して聴くようになったのは遅かったものの…今となってはそのどのオルガニストよりも好きなのがこのラリー・ヤングになります。
やはりジョン・コルトレーン好きの僕としては、まるでコルトレーンのサックスをオルガンに置き換えたかのようなラリー・ヤングを好きになるのは当然の流れだったんです。
前置きが長くなりましたが、これが僕のラリー・ヤングとの出会いです。
ちなみにラリー・ヤングは、1960年に『Testifying』というアルバムで初リーダー作をリリースしています。
それから『Young Blues』と『Groove Street』といったリーダー作を残してはいますが、この3作品ではそこまで革新的な演奏を聴くことは出来ません。
個人的にもこの3作品は、特に印象もなく思い入れもありません。
でも、もしこの3作品をまとめて聴いてみたいな~と言う方には、こちらの『Four Classic Albums』がおすすめです。
上記の3作品に加え、ラリー・ヤングがテナー・サックス奏者のジミー・フォレストのリーダー作に参加した『Forrest Fire』を加えた4作品を2枚のCDにまとめたお買い得盤です。
初期の初々しいラリー・ヤングの演奏を聴くのには適していますが、僕としてはラリー・ヤングのおすすめとしては、その後のブルーノート・レコード時代の方を強く推薦します。
1962年、プレスティッジ・レコードに3作目のリーダー作となる『Groove Street 』を残した後、ラリー・ヤングはグラント・グリーンのリーダー作『Talkin’ About!』に参加した後、『Into Somethin’』でブルーノート・レコードからリーダー作をリリースします。
そこから併せて6作品分のリーダー作を残しています。
今回は、その6作品を順番にご紹介したいと思います。
Larry Young – 『Into Somethin’』
グラント・グリーンのリーダー作『Talkin’ About!』から2ヵ月後に、ドラムのエルヴィン・ジョーンズを含む同じ録音メンバーに、怪人サックス奏者サム・リヴァースを交えたカルテットで録音された『Into Somethin’』です。
ラリー・ヤング自身の作曲による1曲目”Tyrone”から、既にジミー・スミスの影響下からいちはやく脱却しています。
この時代のほとんどのオルガン奏者は、ジミー・スミスを真似たような演奏ばかりで少しばかり飽き飽きしてしまうのですが、ここでのラリー・ヤングの演奏はもはやジミー・スミスの影響を感じさせない自己のプレイ・スタイルを確立しています。
アーシーなオルガンのイメージが、新主流派の時代を感じさせるモードな演奏に変わります。
殆どの場合、ブルージーなジャズ・ギターを弾くとイメージ付けされているグラント・グリーンは、オルガン奏者との相性が良いことでも有名です。
しかしなぜかジミー・スミスとの相性はあまりよくなく、共演作も1作のみとなっていました。
そんなグラント・グリーンが、モードなラリー・ヤングと相性が良いというのは、ブルージーなイメージしか持っていない方からしたら不思議に感じることかも知れませんが…実はグラント・グリーンもジョン・コルトレーンから大きな影響を受けたギタリストです。
また代表作の『Idle Moments』に於いて”Jean de Fleur”というモードな難曲を書いています。
そう考えると、ラリー・ヤングウェス・モンゴメリーと相性が良いのも頷けます。
本作2曲目の曲”Plaza De Toros”もグラント・グリーンによる作曲で、”Jean de Fleur”を彷彿させるモードな楽曲です。
アフリカをルーツ持つドス黒いオルガン演奏ではなく、格調高いヨーロッパの気品を感じさせるのがラリー・ヤングのオルが演奏だと感じます。
例えばアルバム最後の曲”Ritha”も、どことなくヨーロッパを感じさせる楽曲です。
アーシーなだけでない、オルガンという楽器の可能性を更に開いたのがラリー・ヤングにして、この『Into Somethin’』だったのではないだろうか?と僕は感じます。
今聴いてもオシャレな作品です♪
Larry Young – 『Unity』
まず、ジャズがお好きでしたら必ず聴いておいた方が良い名盤です!
白の背景に”Unity”のデカイ文字が印象的なアルバム・ジャケットは、デザイン的にもインパクトがあります!
僕はWebデザインを本業としているのですが、駆け出し時代に呼んだいくつかのデザインの教科書で本作のタイポグラフィが例として取り上げられていたのを見たことがあります。
“Unity”=「統一」「一致団結」の意味なのですが、本作にはラリー・ヤング以外に、トランペットのウディ・ショウ、テナー・サックスのジョー・ヘンダーソン、ドラムのエルヴィン・ジョーンズといったカルテットで録音されています。
その4人を表すかのように、アルバム・ジャケットの”U”の文字に、4つのオレンジの●が描かれています。
ひとつの器に、4つの楽器、そして4つの魂(=●)が集まり、ひとつの名盤が出来上がりました。
ハンガリーの作曲家コダーイ・ゾルターンの組曲『ハーリ・ヤーノシュ』を題材とした1曲目”Zoltan”からして、他のオルガン奏者のアルバムとは一線を画しています。
「皇帝と延臣たちの入場」のメロディーをそのまま拝借した”Zoltan”も、ヨーロッパの香りが漂う演奏です。
まるで初期のファイナル・ファンタジーのBGMのようなメロディー・ラインなのですが、実はこの楽曲を取り上げたのは、ウディ・ショウになります。
革新的なアルバムではありますが、面白いことにこれだけラリー・ヤングの個性が溢れた代表作でもあるにも関わらず、本作にはラリー・ヤング自身が作曲した曲はひとつもありません。
セロニアス・モンクのカヴァー曲”Monk’s Dream”と、ジョー・ヘンダーソン作”If”と、スタンダード曲の”Softly As In A Morning Sunrise”以外は、ウディ・ショウの作曲になります。
…と、考えると、本作に於ける革新性はウディ・ショウによるところが大きいんだな~といった感じではありますが、しかしこういった革新的な楽曲に合ったオルガンを演奏できる人物はラリー・ヤングをおいて他にはいない気がします!?
数ある”Softly As In A Morning Sunrise”のカヴァーの中でも、本作に於けるジョー・ヘンダーソンの軽く崩したテーマ演奏と、後半のラリー・ヤングの燃え上がるようなオルガン・ソロは屈指の出来です!
本作は、オルガン・ジャズが好きな人だけが聴くべきアルバムではありません。
全ジャズ・ファン、いやそれだけでなく全音楽好きが聴くべき名盤なのかもしれません。
もちろん僕と同業にあたるデザイナーのみなさんも、このアルバム・ジャケットのタイポグラフィーはどこかで見かけたことがあるはずです。
デザイナーだからこそ、感性が揺さぶられるジャズを聴きましょう!
とにかく文句の付け所がない歴史的名盤です!
ちなみに2016年に『In Paris: The ORTF Recordings』という発掘アルバムもリリースされています。
本作は『Unity』録音前後のフランス滞在時の放送用音源で、ジョー・ヘンダーソンの代わりにネイザン・デイヴィスがテナーを吹き、エルヴィン・ジョーンズの代わりにビリー・ブルックスがドラムを叩いています。
グラント・グリーン抜きの”Talkin’ About J.C.”や”Luny Tune”に、コルトレーンの精神世界を思い描いたようなネイザン・デイヴィス作の”Trane of Thought”、そしてウェイン・ショーター作の”Black Nile”等、凄まじい演奏が繰り広げられています。
そして何と言っても目玉は、20分以上にも及ぶ狂乱の”Zoltan”です!
オルガンの鍵盤が溶け出すんじゃないだろうか?という程の熱い演奏をラリー・ヤングが披露しています。
こちらも必聴です!
Larry Young – 『Of Love And Peace』
デザイナブルだった『Unity』と比べると、どこか不気味なアルバム・ジャケットが損をしている『Of Love And Peace』ではありますが、こちらも革新的な作品です!
トランペットのエディ・ゲイルにテナー・サックスのハーバート・モーガンにアルト・サックスのジェームス・スポールディングがフリーキーに暴れ回る1曲目”Pavanne”から、その域は最高潮に達しています!
こんな革新的な演奏を収めたオルガン奏者の作品が他にあるでしょうか?
いや、ありません!
もはや「オルガンのコルトレーン」の喩えすら必要ないぐらいにラリー・ヤングは、時代の先を行ってしまっていたんですね!
今聴いても過激で革新的です!
ヴィクター・フェルドマン作の”Seven Steps To Heaven”と先の”Pavanne”以外の2曲は、ラリー・ヤングのオリジナル曲で、アルバム自体はたったの4曲しか収録されていません。
しかし中身の演奏の濃さは相当で、一般的な聴きやすさからは程遠い内容でもあります。
キャッチーなメロディーなどほとんどなく、フリーキーな演奏が続きます。
「ジャズ最初の1枚」としては、絶対に聴いてはいけないアルバムのひとつです。
初っぱなからこのアルバムを聴いてしまうと…「ジャズって聴きにくいな~…。」と嫌いになってしまうかも知れません。
それどころか、ジャズの美しい旋律が好きだって人からしたら、本作は駄作と感じるかも知れません。
なので、まずはオーネット・コールマンやエリック・ドルフィーを聴いてみて、フリーなジャズも悪くないな~と感じてから本作を聴くことをおすすめします。
ジミー・スミスのオルガン・ジャズが好きだって人がいきなりこのアルバムを聴いてしまうと…「なんだこれ!」ってなっちゃうと思います。
しかしここには、イナタくアーシーなだけではない「オルガンの可能性」が示されています。
こんなオルガン・ジャズ作品は、他にありません!
聴く人を選びそうな聴き辛いアルバムではありますが…僕は好きな作品です。
後期ジョン・コルトレーンがお好きな方は、ぜひ!
Larry Young – 『Contrasts』
前作のフリーキーな感触を残しつつも、ちょっぴりファンキーなノリが加わった1曲目”Majestic Soul”がやたらとかっこいいブルーノート・レコード4作目『Contrasts』も素晴らしいアルバムです。
タイトル通りに夕暮れ時に聴きたいオシャレな”Evening”や、コルトレーンとラシッド・アリのドラム・デュオを彷彿させる”Major Affair”、そしてアルセア・ヤングがアンニュイに歌う”Wild Is The Wind”と、バラエティに富んだ楽曲が収録されています。
ただ、後半”Tender Feelings”と”Means Happiness”2曲なんかは、管楽器隊がフリーキーに暴れ回ったりと、なかなかに聴き辛い箇所があったりもします。
ある程度、色んなジャズを聴いてから本作に辿り着きましょう。
間違っても「ジャズ最初の1枚」で選んではいけないアルバムです。
Larry Young – 『Heaven On Earth』
実質ブルーノート・レコード最終作となる『Heaven On Earth』は、これまでの作品になかったアーシーなジャズ・ブルース曲”The Infant”から始まる驚きな内容です。
ここにきて、キャッチーな曲が多く収録されたアルバムなのですが、それはギターにジョージ・ベンソンが参加しているからなのかも知れないですね。
ギタリスト、ジョー・ヘンダーソンは僕も大好きなプレイヤーなのですが…本作はラリー・ヤングらしさがあまり感じられない作品だという残念な印象が僕の中ではあります。
それならジミー・マクグリフや”ビッグ”・ジョン・パットンを聴くわ~って感じちゃうアルバムです。
今回ご紹介する6作品の中では、最も聴きやすいアルバムですが…おすすめ度は5番目です。
Larry Young – 『Mother Ship』
1969年に録音されておきながら1980年になるまで未発表だったアルバムがこの『Mother Ship』です。
そりゃお蔵入りになるよね…と言った内容です。
おすすめ度は、『Heaven On Earth』よりも低い6番目です。
なんなら聴かなくってもいいぐらいかも?…と極論を言えなくも内ですが、まぁこれもラリー・ヤングがブルーノート・レコードに残したおすすめ作品と言うことで…。
トランペットにリー・モーガンが参加してはいますが、精彩に欠けラリー・ヤングと噛み合っていません。
ラリー・ヤング自身も、更に新しいことにチャレンジしようとして道に迷っている感じです。
『Unity』の凄さはどこに行った?
先の5作品を聴いた後で、最後に時間に余裕があれば聴いてみて下さい。
以上、【オルガンのコルトレーン!ラリー・ヤングがブルーノート・レコードに残したおすすめの6作品】のご紹介でした。
最後の2作品は、あまりおすすめとは言えない物かも知れませんが…それでもラリー・ヤングが名門ブルーノート・レコードに残した作品ということで、興味ある方は6作品全てを聴いてみて下さい。
必ず聴いておきたいアルバムとしては、やはり『Unity』が一番です!
ジャズがお好きな方で『Unity』はまだ未聴だという人は、まずはこのアルバムからラリー・ヤングを聴いてみましょう!
他に関連するお勧め記事
【スピリチュアル・ジャズの名作】ジョー・ヘンダーソンの『Black Narcissus』を聴こう♪
ブルーノート流アフリカン・ビート!エディ・ゲイルのゲットー・ミュージックを聴こう♪
ハンニバル・マーヴィン・ピーターソンがベイステイトに残したスピリチュアル・ジャズ作品3選‼
※このブログに掲載しているイラストや写真、テキスト等の無断引用・無断借用・無断転載・無断使用は固くお断りしております。ご利用はご遠慮ください。