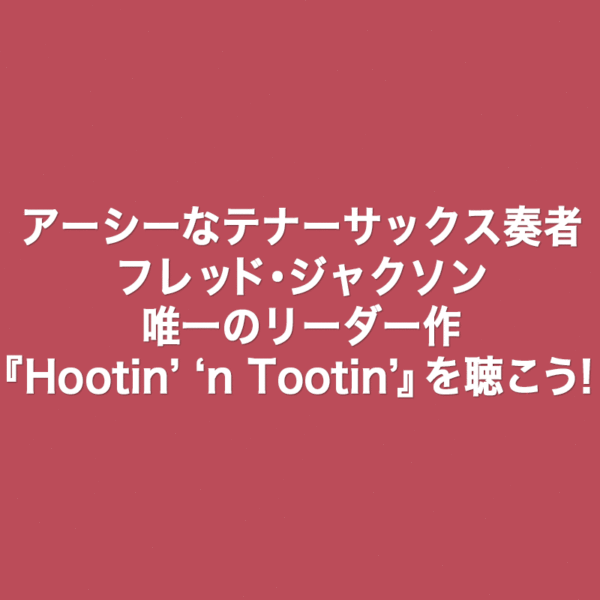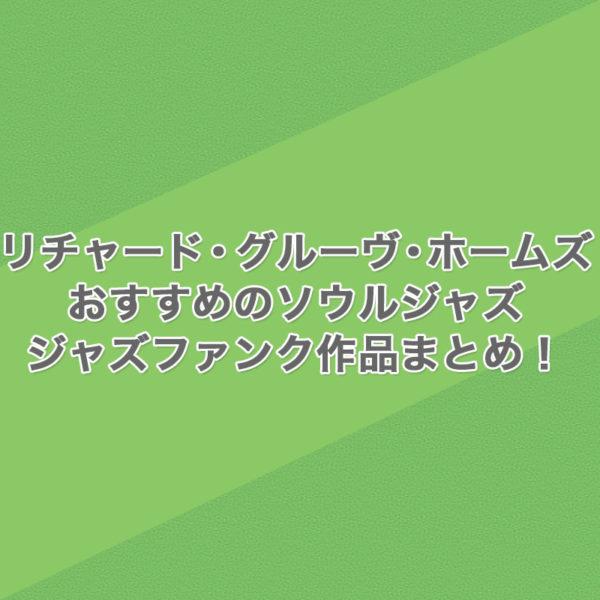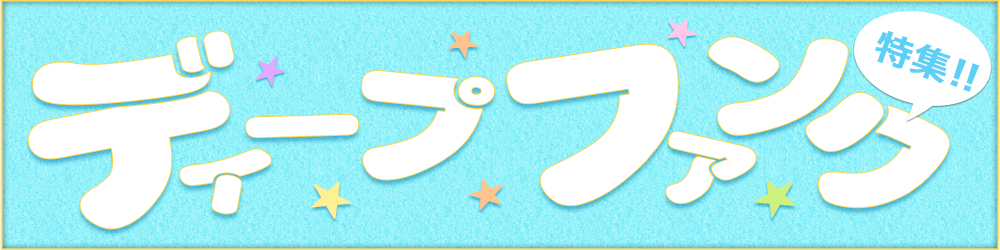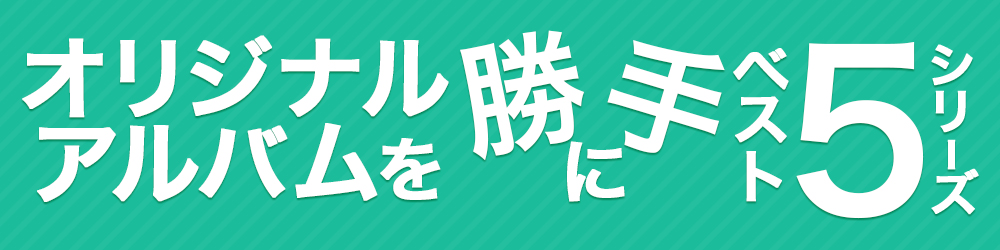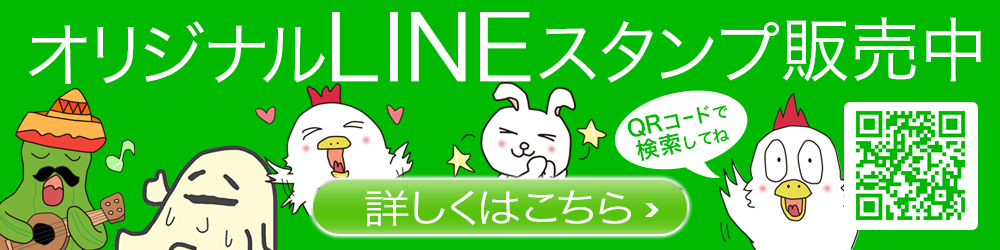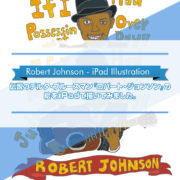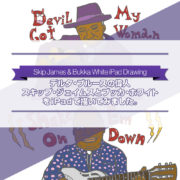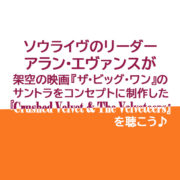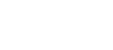
2021/03/11
グラント・グリーンも参加したビッグ・ジョン・パットンのブルーノート作品おすすめ盤まとめ
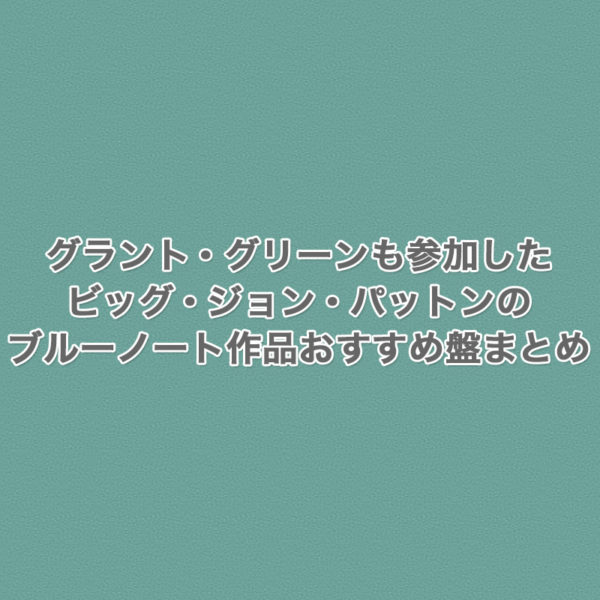
ブルーノート・レコードに多くの名作を残したオルガン奏者ビッグ・ジョン・パットンをご紹介します。
グラント・グリーンも参加したソウル・ジャズの名作もあります。
今回は、ジャズの名門ブルーノート・レコードに数多くのオルガン作品を吹き込んだオルガン奏者のビッグ・ジョン・パットンの作品をまとめてご紹介したいと思います。
1935年7月12日に米国ミズーリ州カンザスシティに生まれたジョン・パットンは、8歳の頃からピアノを始め、その頃からラジオで聴いた楽曲を何でも演奏する才能を持っていました。
母親も教会でピアノを弾いていたため、パットンの才能にいち早く気づき、母自ら楽譜の読み方を教えたといいます。
その後、ハイスクール在籍時からセミ・プロとして活動していたパットンは、R&Bシンガーのロイド・プライスに見出され、プロ・ミュージシャンとして正式なキャリアをスタートすることとなります。
ロイド・プライスのバンドに在籍していた時代から、パットンはピアノだけでなくオルガンも弾くようになりました。
このバンドから離れ、ジャズ・ミュージシャンを目指してNYに向かう頃には、完全にオルガン奏者になっていたとのことです。
NYに住むようになってからは、ソニー・スティットやジーン・アモンズ、ジョニー・グリフィンやエディ・ロックジョー・デイヴィス等のオルガンと相性の良いミュージシャンと共演を果たしています。
それから後に、アルト・サックス奏者のルー・ドナルドソンの目に留まり、ジャズ・ギタリストのグラント・グリーンとドラム奏者のベン・ディクソン共々、ドナルドソンのバンドに所属することになります。
そしてパットンが27サイを迎えた頃、ついに名門ブルーノート・レコードからリーダー作を発表するチャンスを手にするのでした。
今回は、そのビッグ・ジョン・パットンがブルーノート・レコードに残したおすすめの作品をまとめてご紹介したいと思います。
Big John Patton – 『Along Came John』
1963年4月5日に録音されたビッグ・ジョン・パットンにとっての初のリーダー作となる『Along Came John』は、パットンにとっても気心の知れた仲間内で録音されたようなくつろいだ作品です。
ギターにグラント・グリーン、ドラムにベン・ディクソンと、ルー・ドナルドソン・バンドの仲間達を迎え、更にオルガン作品と相性の良いフレッド・ジャクソンとハロルド・ヴィックという2名のテナー・サックス奏者も参加しています。
まずベン・ディクソンの書いた1曲目”The Silver Meter”からアルバムは幕を開けます。
どこか間の抜けたようなメロディー・ラインがなんともB級感を漂わせますが、演奏に関してはしっかりとしています。
曲の進行はありがちなジャズ・ブルースの進行で、パットンとグラント・グリーンが弾くリフに、2名のホーン隊がオブリガートのフレーズを重ねる程度です。
この曲で登場するグラント・グリーンのギターソロは、いつも通りの手癖フレーズで弾ききっています。
2分46秒で聴くことが出来るマイナー・ペンタトニック・スケールの1~2弦を利用したフレーズは、グラント・グリーンの手癖フレーズです。
B.B.キングがよく弾くフレーズと似ていますが、ポジションは同じで、弾く音の順番やリズムが違っているだけです。
2曲目”I’ll Never Be Free”は、シングル・カットもされたバラード曲で、1950年にケイ・スターが歌ったスタンダード・ナンバーです。
全編でエモーショナルなパットンのオルガン演奏が聴ける名演です!
なぜこの曲がシングル・カットされたのか?は、この曲を聴けば分かることだと思います。
本作の中に於いても、最も熱いオルガン演奏を披露している楽曲ですからね。
3曲目”Spiffy Diffy”は、1曲目と同じくベン・ディクソンのオリジナル曲になりますが…これはそのまま親分のルー・ドナルドソンの”Funky Mama”をなぞったような楽曲です。
“Funky Mama”の録音にも、パットンを含むグラント・グリーンとベン・ディクソンも参加していましたからね。
親分のいないところで、子分達が物真似をした感じに思えてしまいます。
ただ、こちらの楽曲の方が親分がいなくって気が楽になったのか?グラントもパットンもより奔放なソロを披露しています。
やはり親分や先輩に上司などが近くにいると、遠慮してしまって本領を発揮できないものですからね。
タイトル・トラックにもなった4曲目”Along Came John”は、パットンのオリジナル曲です。
これまた間の抜けたテーマ・メロディーを持ったジャズ・ブルース曲になります。
相も変わらずグラント・グリーンは、手癖フレーズでギターソロを弾ききっています。
この金太郎飴的な同じフレーズでキー違いの楽曲を演奏する様は、それこそB.B.キングのようですね。
数多のジャズ・ギタリストの中に於いても、最もブルージーな演奏を得意としたグラント・グリーンならではだと思います。
5曲目”Gee Gee”も同じくパットンのオリジナル曲になりますが、この曲もジャズ・ブルース曲です。
ブルーノート・レコードの創始者アルフレッド・ライオンがブルース曲が好きだったため、所属ミュージシャンがリーダー作を制作する際には、必ずオリジナルのジャズ・ブルース曲を1曲吹き込むことを要求していたらしいのですが、まさにパットンはそんな要望に応えることが出来たミュージシャンだったのでしょう。
同じくジャズ・ブルースを得意としたグラント・グリーンとベン・ディクソンという仲間を率いて、ここでも熱いブルース魂を見せてくれています。
アルバム最後の”Pig Foots”もベン・ディクソンのオリジナル曲になります。
といっても、相も変わらず最後の最後までジャズ・ブルース曲なのですが…。
ほとんどのが曲がブルース調で締められているのが本作の良い部分でもあるのですが、どうしても単調に感じてしまう悪い側面でもあります。
そういった中にあってスタンダード曲の2曲目”I’ll Never Be Free”が異質でもあり、1曲だけ突出しているように聞こえます。
アルバムを通して聴くと…なるほど、どうりでこの曲がシングル・カットされたわけだ!と納得出来るかとおもいます。
ただ僕のようなジャズ・ブルース好きにとっては、どれも退屈ではない名曲ばかりに感じるのですが…聴く人にとっては単調なアルバムと感じてしまう危険性もあります。
クラシックの要素を含んだジャズがお好きな方にはおすすめできませんが…イナタいジャズ・ブルースが大好きだと言う方には自信を持っておすすめ出来る名作です♪
ジャズ・ブルースがお好きな方はぜひ聴いておきましょう♪
Big John Patton – 『Blue John』
1963年7月11日に録音されておきながらも、1986年になるまで正式にリリースされなかった曰く付きのアルバム『Blue John』は、CD化に際して追加されたボーナス・トラックが一番の魅力となる変わった作品です。
本作には引き続きグラント・グリーンにベン・ディクソン、更にはトミー・タレンタインといったジャズ・ブルースがお得意な面子が参加していますが…なかなかに聞きづらいアルバムだと僕は感じています。
というのも、本作には異色のリード奏者ジョージ・ブレイスが参加しているからです。
もしこのブログ記事を読んで下さっている方の中にジョージ・ブレイス好きの方がいらっしゃいましたら、先に謝っておきます。
ごめんなさい、僕はジョージ・ブレイスがどうしても好きになれません。
ジョージ・ブレイスとおいうサックス奏者は、ローランド・カークのように管の曲がりのないアルト・サックスの一種ストリッチを用いて特殊な音色を吹くのですが…どうもこの音色が僕は苦手です。
どことなく音が外れているように聞こえてしまって、とても気持ち悪く感じます。
もちろん人によってはこの音色を心地良く感じられるのもわかりますが、僕は苦手です。
そのため本作が80年代になるまで未発表であったのは、万人受けはしないであろうジョージ・ブレイスが参加していたからなのかな?と勘ぐってしまいそうになります。
ただ本作収録の楽曲に関しては、そのジョージ・ブレイスが書いた”Hot Sauce”や”Bermuda Clay House”のようなジャズ・ブルース好きには堪らない楽曲も含まれています。
プレイ・スタイルはあまり好きにはなれないジョージ・ブレイスなのですが、意外にもオリジナル曲の出来はよかったりするのも複雑な気持ちです。
また本作にはグラント・グリーンのオリジナル曲”Dem Dirty Dues”や”Kinda Slick”等も含まれているのですが…しかし何と言っても一番の聴き所はCD化に際して追加された”Jean De Fleur”の初期バージョンです。
後にグラント・グリーンの名盤『Idle Moments』に収録されることになるあのモード・ジャズの名曲を既に本作で録音していたのです。
『Idle Moments』では、更にテンポを上げて演奏されているのですが、本来はこのぐらいのテンポを想定していたのでしょう。
『Idle Moments』録音中に、他の楽曲が長くなってしまったため”Jean De Fleur”のテンポを上げて収録時間を短くせざるを得なかったのがテンポ・アップの理由です。
この曲、楽曲のテーマ部分こそそこまで難しくはないのですが、実際に演奏してみると、これがかなりの難曲なんです!
かくいうグラント・グリーン好きの僕も、この曲を通っているギター教室の課題曲として2回ほど発表会で演奏したのですが…もう難しいったらなかったです!
テンポは速いは、キーはコロコロ変わるは…。
まぁプロのジャズ・ミュージシャンの方であれば、これぐらいのキー・チェンジは当たり前なのかも知れませんが、僕のような趣味で楽器演奏をしているような素人が、おいそれと簡単に演奏できるレベルの楽曲ではなかったです。
しかし実際に自分でも演奏してみたことで、「やっぱグラント・グリーンってすごいミュージシャンなんだなぁ~。こんな難しくって美しいコード進行の曲を書けるなんて!」と感じました。
その楽曲を理解するには、やはり自分でも実際に演奏してみるのが一番なのだと身を持って知った瞬間でした。
ちなみに本作に収録されている”Jean De Fleur”についてなのですが…まだ未完性な感じが拭えない演奏です。
作曲者のグラント・グリーン自身もテンションが低く、珍しくピッキング・ミスが随所で見受けられます。
また後半にベン・ディクソンの謎のドラムロールがあったり、ソロを吹くトミー・タレンタインとジョージ・ブレイスの力量不足が感じられます。
流石に『Idle Moments』に参加している名手ジョー・ヘンダーソンとボビー・ハッチャーソンと比べるのは酷かも知れませんが、本曲に於けるソロ演奏を聞いていると彼ら2管のレベルの低さを感じてしまいます。
やはりジョーヘンにボビハチの方が一流ですね!
正直、僕のようなコアなグラント・グリーンのファンでもなければ、慌てて聴くようなアルバムではありません。
どうしても”Jean De Fleur”の初期バージョンを聴きたいな!って方におすすめのアルバムです。
Big John Patton – 『The Way I Feel』
1964年6月19日に録音された公式ではパットンにとって2作目のリーダー作となる『The Way I Feel』も引き続きグラント・グリーンとベン・ディクソンが参加したジャズ・ブルース曲中心のアルバムです。
しかも今回は5曲全てがジョン・パットン作のオリジナル曲になります。
本作でトランペットを吹いているのがリチャード・ウィリアムスで、テナー・サックスを吹いているのがフレッド・ジャクソンです。
1曲目の軽快なジャズ・ブルース曲”The Rock”を始め、ゆるいリズムのタイトル曲”The Way I Feel”にバラード曲”Davene”など、パットンの作曲能力の進化を感じさせます。
またどの曲に於いても、これでもか!と繰り返しのシーケンス・フレーズを連発するグラント・グリーンのギターソロも個性たっぷりです!
あまりのしつこい繰り返しにレコードやCDが壊れてしまったのかな?と感じるほどです。
有名なスタンダード曲のカヴァーを含まない地味な印象のアルバムではありますが、その分オルガン奏者ビッグ・ジョン・パットンの本来の姿を存分に味わうことが出来る作品です。
Big John Patton – 『Oh Baby!』
1965年3月8日に吹き込まれた本作『Oh Baby!』は、これより2年前に吹き込まれたハロルド・ヴィックの『Steppin’ Out』と全く同じメンバーで製作されています。
そのメンバーは、いつものグラント・グリーンにベン・ディクソン、そしてテナー・サックス奏者のハロルド・ヴィックにトランペット奏者のブルー・ミッチェルを加えたクィンテットです。
『Along Came John』に収録されていた”The Silver Meter”のように愉快なテーマ・メロディーを持った1曲目”Fat Judy”は、ベン・ディクソンのオリジナル曲です。
バックのホーン隊のオブリガートや8ビートのドラムのリズムなんかが思いっきりリー・モーガンの”Sidewinder”と同じパターンなのですが、同曲のヒットを受けてのことでしょう。
グラント・グリーンはよく「バッキングを弾かないギタリスト」と揶揄されることが雑誌などでも見られるのですが、僕から言わせればそれはちゃんとグラント・グリーンのサイドマンとしての仕事を聴いてないんだなって思ってしまいます。
自身のリーダー作ではサックス奏者のようにホーン・ライクなフレーズを弾くことに徹してはいますが、この曲のようにオルガン奏者のサイドマンでギターを弾く際には巧みなバッキングを弾きこなしています。
さすがにプロを名乗るジャズ・ギタリストで「バッキングが弾けない」人なんていないと思います。
僕自身もギターを弾くのでわかることなのですが、プロを名乗るミュージシャンであれば「ギターソロがいまいちなギタリストでもバッキングは上手い」んです。
逆に「ギターソロが上手いのにバッキングが下手」なギタリストなどいません。
まともにバッキングを弾けないようなギタリストが、上手いソロを弾きこなすことは不可能なのですよ。
バッキングがちゃんと弾けて、初めてソロも上手く弾けるものです。
ソロばかりに注目がいきがちなギターという楽器ですが、そもそもはコード楽器なのでバッキングを上手く弾きこなせるようになることは必須です!
さて、本作は先の1曲目と5曲目のハロルド・ヴィック作の”Night Flight”意外は全てジョン・パットンのオリジナル曲です。
その中でも2本のホーンの絡み合いがかっこいい3曲目”Each Time”なんかは、これまでのジョン・パットン作の楽曲にはなかった凝ったアレンジを聴くことが出来ます。
ジョン・パットンの成長を感じさせつつも、グラント・グリーンのリズムカルなコンピングを存分に楽しめる良作に仕上がっています。
この後にご紹介する名盤2作の次におすすめしたいアルバムでもあります。
ただ、次にご紹介するアルバム2作品があまりに素晴らしいので、その影に隠れてしまいそうな作品ではありますが…悪くないアルバムです。
Big John Patton – 『Let ‘Em Roll』
どこからどう見てもオシャレなアルバム・ジャケットのデザインに、知的でクールなヴィブラフォンを演奏する新主流派のボビー・ハッチャーソンが参加した本作は、今回ご紹介している作品の中で一番最初に聴くべき名盤です。
1965年12月11日に吹き込まれた本作は、前作から引き続きグラント・グリーンこそ参加していますが、ドラムがベン・ディクソンからオーティス・フィンチに変更となっております。
しかしそれが功を奏したのか!?ベン・ディクソンよりも洗練されたオーティス・フィンチのドラミングは、クール・ヴァイヴのボビー・ハッチャーソンとの相性が良いように感じられます。
また本作のグラント・グリーンは特に絶好調で、もはやジョン・パットンのアルバムではなく、リーダーはグラント・グリーンと勘違いしてしまいそうな程のテンションの高さです。
まずはボビー・ハッチャーソンのヴァイヴの音色がさっそく目立つ1曲目”Let ‘Em Roll”は、アルバム・タイトルに選ばれたのも当然と言える名曲です。
ビッグ・ジョン・パットンが生涯に書いた全楽曲の中で、最も素晴らし曲がこの”Let ‘Em Roll”だと言えます。
グラント・グリーンのギターソロも絶好調で、これまでの手癖フレーズ頼りのフレージングよりも更に進化を遂げています。
そして何よりもボビー・ハッチャーソンの知的なヴィブラフォンによるソロが本曲を更に名曲に仕上げています。
これまでのジョン・パットンのオリジナル曲は、クールと言うよりはアーシーという言葉がぴったりでしたが、古くささは否めませんでした。
しかしここに来て、完全に新主流派に呼応した’新しい’楽曲作りに挑戦したことが窺えます。
本作を名盤としているのは、この曲だけではありません!
2曲目”Latona”も同じくジョン・パットンの代表曲と言って良いオリジナル曲です。
この曲のグラント・グリーンのギターリフは一度聴いたら墓場まで持て行けそうなぐらい印象的です。
このダンサンブルなリフの上を、ボビー・ハッチャーソンの洗練されたヴィブラフォンが華麗に飛び回る様は何度聴いてもスリリングです。
この曲はグラント・グリーンを敬愛するザ・ニュー・マスターサウンズのリーダーでギタリストのエディー・ロバーツが、2011年にEddie Roberts & The Fire Eaters名義のソロ・アルバム『Burn!』でも取り上げていた楽曲です。
確かにソウル・ジャズ好きのギタリストであれば一度は弾いてみたいギターリフではありますね♪
またエディー・ロバーツは、2017年に行われたグラント・グリーンのトリビュート・イベント『Green Is Beautiful』というライヴでもこの曲を演奏していました。
この2曲だけでも本作を聴く価値は十分すぎるのですが、その他にも「いそしぎ」の邦題で有名なジャズ・スタンダード”The Shadow Of Your Smile”や、リー・モーガンの”Sidewinder”風ジャズ・ロック曲でハンク・モブレー作の”The Turnaround”等カヴァー曲も素晴らしい出来です。
こちらの”The Turnaround”もエディー・ロバーツがソロ・ライヴでちょくちょく演奏していた楽曲です。
2曲のカヴァー曲を挟んだ後、パットン作の5曲目”Jakey”もこれまでになかったクールな楽曲です。
そして最後にもパットン作で、どことなくスピリチュアルなジャズ曲”One Step Ahead”が収録されています。
ブルーノート・レコード屈指のオシャレなアルバム・ジャケットを含め、参加メンバーの腕もピカイチで、収録楽曲のセンスも最高なので、全く非の打ち所のない名盤に仕上がっています。
ジミー・スミスの『Midnight Special』やリチャード・グルーヴ・ホームズの『Soul Message』と並ぶオルガン・ジャズを代表する名盤がこの『Let ‘Em Roll』です。
オルガン・ジャズがお好きな方で、まだ本作を未聴の方は絶対に聴いておきましょう!
これほどの名盤は、なかなかないですよ!
Big John Patton – 『Got A Good Thing Goin’』
1966年4月29日に録音された本作『Got A Good Thing Goin’』は、アルバム・ジャケットの踊る女性の写真同様にダンサンブルな楽曲が収録された名盤です。
本作にはホーン隊は参加しておらず、ジョン・パットンにグラント・グリーンのメロディー隊以外は、ヒュー・ウォーカーのドラムにリチャード・ランドラムのコンガというリズム隊の参加が本作をダンサンブルなアルバムに仕上げている要因だと言えます。
特にパットンとグラント・グリーンの共作による頭2曲の出来が素晴らしいです。
曲名通りにヨーデル調のメロディーが登場する”The Yodel”からダンサンブルなリズムが目立ちます。
この曲もエディー・ロバーツがソロ・ライヴで演奏していたり、ギャラクティックのドラマー、スタントン・ムーアも参加したロバート・ウォルターズの2000年作品『Money Shot』でも取り上げられていた楽曲です。
現代を代表するジャズ・ファンク/ディープ・ファンク系のミュージシャンにも取り上げられる名曲です。
またこの”The Yodel”と2曲目”Soul Woman”は、どちらもグラッセラ・オリファントの1967年作品『The Grass Is Greener』でも再演されていました。
この『The Grass Is Greener』にも、ジョン・パットンとグラント・グリーンが参加してはいるのですが、本作『Got A Good Thing Goin’』の演奏の方がテンションは高いです。
特に本作に於けるグラント・グリーンの好調ぶりは、ソウル・ジャズ/ジャズ・ファンク系のギター好きなら必聴です!
パットン/グリーン共作の冒頭2曲意外は、カヴァー曲になります。
スモーキー・ロビンソン作でマーヴィン・ゲイガ歌った”Ain’t That Peculiar”や、サム・クックの”The Shake”等は当時の流行のR&B曲を取り上げたカヴァー曲です。
また最後に収録された5曲目”Amanda”は、グラント・グリーンの名盤『Idle Moments』のタイトル曲の作者でもあり、ハービー・ハンコックを発見するまでドナルド・バードのバンドでピアニストを務めた隠れた名手デューク・ピアソンが書いた楽曲です。
これら3曲のカヴァー曲も悪くはないのですが、やはり本作の魅力は冒頭2曲にあります。
現代のミュージシャンにも取り上げられることも多い、時代を超えた名曲”The Yodel”は、ソウル・ジャズ好き必聴です!
Big John Patton – 『That Certain Feeling』
ここでついにグラント・グリーンの参加が途絶えます。
しかしその代わりに参加しているのは、ジャズ・ファンク系の名手ジミー・ポンダーなのでギターの上では申し分ありません。
なのに、本作が地味な作品なのは収録曲に問題があります。
ジミ-・ワトソン作の6曲目”Daddy James”以外は全てジョン・パットンのオリジナル曲になるのですが、これまでのようなアーシーな曲や、ファンキーな曲、また名盤『Let ‘Em Roll』に収録されていたような時代を超越したオシャレな楽曲が皆無なのが問題です。
良くも悪くもない特徴のない楽曲が延々と続きます。
印象に残る曲は特になく、「まぁ時間潰しには良かったんじゃないかな?」と聴いた後の自分に言い聞かせるしかない地味な作品です。
ジミー・ポンダーが特に好きだとかそういった理由でもない限り、慌てて聴くべき作品ではありません。
必ず先に『Let ‘Em Roll』と『Got A Good Thing Goin’』を聴いてから、本作を聴くかどうかゆっくり考えましょう。
Big John Patton – 『Boogaloo』
1968年8月9日に録音された本作『Boogaloo』は、1995年になるまでリリースされることがなかった未発表作品でした。
残念ながらグラント・グリーンやジミー・ポンダーのようなギターの名手こそ参加していませんが、パットン作のファンキーな1曲目”Boogaloo Boogie”から始まるノリの良い楽曲で構成されたアルバムは、地味だった『That Certain Feeling』よりも印象に残ります。
ニューオーリンズ出身のR&B歌手ロバート・パーカーの1966年のヒット曲”Barefootin'”以外は全てパットンのオリジナル曲で、どれもノリが良いのが本作の特徴です。
Big John Patton – 『Understanding』
『Boogaloo』の2ヶ月後に吹き込まれた本作Understanding』は、1968年にリリースされています。
テナー・サックス奏者のハロルド・アレキサンダーをフロントマンに立てた本作は、パットンとヒュー・ウォーカーのドラムが支えるシンプルなトリオで製作されています。
そのハロルド・アレキサンダー作の1曲目”Ding Dong”から始まる本作は、これまでになりアバンギャルドなパットンのオリジナル曲”Congo Chant”が聴ける異色作となります。
他にはソニ・ロリンズの”Alfie’s Theme”や、ケニーバレルの”Chitlins Con Carne”等も収録されています。
ジャズ・ギタリストのケニー・バレルが書いた”Chitlins Con Carne”は、ジュニア・ウェルズ&バディ・ガイ組やスティーヴィー・レイ・ヴォーン等のブルース・ギタリストにもカヴァーされたブルージーな楽曲なのですが、敢えてギターを加えないサックス・トリオで本作では取り上げられています。
またこれまで同様に、サム&デイヴの”Soul Man”や、レイ・チャールズの”Understanding”のようなR&Bのカヴァー曲も取り上げています。
ただ、アバンギャルドなアルバムにしたかったのか?それともブルージーなアルバムにしたかったのか?はたまたこれまで通りにソウルフルなアルバムにしたかったのか?テーマが定まっていない散漫なアルバムにも感じられます。
Big John Patton – 『Accent on the Blues』
これまた珍しいギタリストが参加したアルバムです。
70年代に前衛的なジャズ・ギターを弾き、なぜか近年はブルース・ギタリストに転身したジェームス・ブラッド・ウルマーが参加しています。
ただここで聴けるウルマーの演奏は、グラント・グリーン風の正統派のソウル・ジャズ系のギターになります。
ネチっこいオクターブ奏法こそ個性を感じさせはしますが、70年代のリーダー作で聴けるような前衛的な演奏はここでは聴くことが出来ません。
むしろ不安定な音階が不快にも聞こえるマーヴィン・キャベルのサックス演奏の方が前衛さを感じさせるほどです。
先に登場したジョージ・ブレイス共々、これまた僕の苦手なサックス奏者でもあります。
どうも彼らの調子っぱずれの音色は僕には合わないようです…。
ウルマーが参加した珍しいアルバムではありますが、それなら次にご紹介する当時未発表だった『Memphis to New York Spirit』の方がおすすめかもしれません。
Big John Patton – 『Memphis to New York Spirit』
1969年6月9日と1970年10月2日に録音された2つのセッションをまとめて、1996年になってようやくリリースされた未発表アルバムになります。
1970年に録音された1~5曲目の方に、ジェームス・ブラッド・ウルマーが参加しています。
特にウルマー自身が書いた4曲目”Bloodyun”では、ウルマーの個性が表れた楽曲です。
ウルマー・ファンであればこの曲だけでも必聴です!
また1969年のセッションの方では、7曲目に収録されているミーターズのカヴァー”Cissy Strut”が良い出来です。
日本のセッションでもお馴染みのこの曲を、マイルス・デイヴィスのバンドにも参加した経歴を持つジョージ・コールマンがソロを吹いているのは見逃せません!
ただ、ジョン・パットンのオリジナル曲が名盤『Let ‘Em Roll』の時のような輝きがないのが残念な部分です。
残念ながらジョン・パットンの才能は、『Let ‘Em Roll』と『Got A Good Thing Goin’』で枯れてしまったと感じざるを得ません。
ジェームス・ブラッド・ウルマーやミーターズがお好きな方はどうぞ!といった作品です。
特別におすすめ出来るアルバムではありません。
以上、【グラント・グリーンも参加したビッグ・ジョン・パットンのブルーノート作品おすすめ盤まとめ】でした。
グラント・グリーンとビッグ・ジョン・パットンは、本当に相性抜群でした!
今回ご紹介したアルバムの中でも特に『Let ‘Em Roll』はおすすめなので、ぜひ聴いてみて下さい。
他に関連するお勧め記事
アーシーなテナーサックス奏者のフレッド・ジャクソン唯一のリーダー作『Hootin’ ‘n Tootin’』を聴こう!
リチャード・グルーヴ・ホームズおすすめのソウルジャズ/ジャズファンク作品まとめ!
エディー・ロバーツが2011年にリリースしたハードバップ風ジャズ・ファンク作品『Burn!』を聴こう♪
※このブログに掲載しているイラストや写真、テキスト等の無断引用・無断借用・無断転載・無断使用は固くお断りしております。ご利用はご遠慮ください。