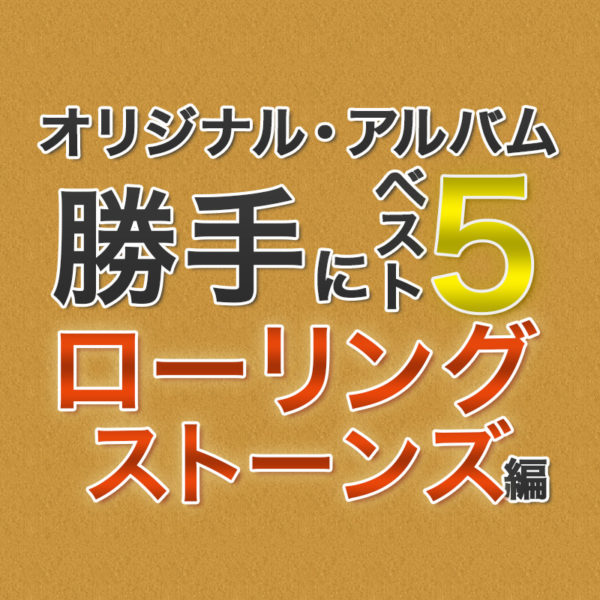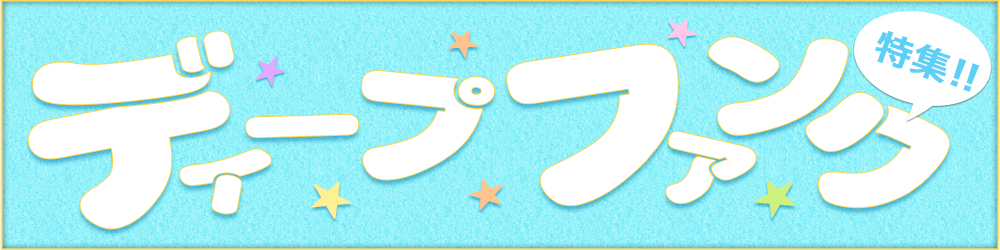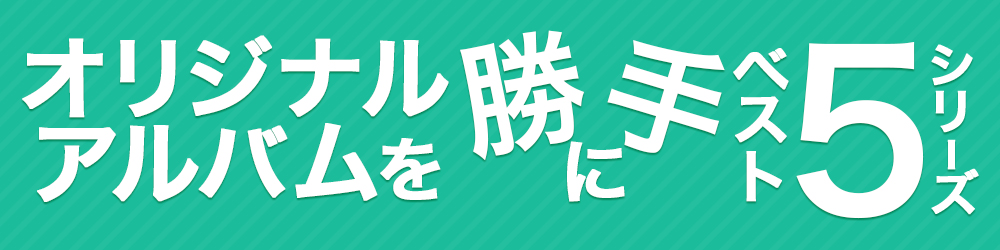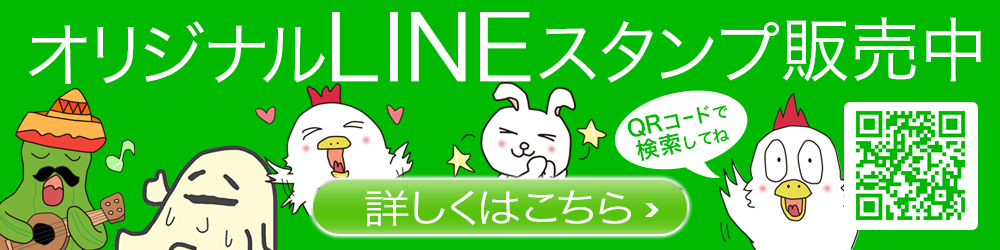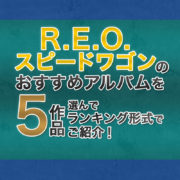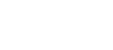2024/10/27
レッド・ツェッペリンのおすすめアルバムを5作品選んでランキング形式でご紹介!

【第50回】おすすめアルバムを5作品選んでランキング形式でご紹介シリーズ
レッド・ツェッペリンのおすすめアルバムをご紹介!
【おすすめアルバムを5作品選んでランキング形式でご紹介シリーズ】の第50回です。
ついにこのシリーズも50回を突破しました!
というわけで、記念すべき50回目にご紹介するのは、ハードロックやヘヴィメタルの先駆者と言われる伝説のバンド、レッド・ツェッペリン(Led Zeppelin)に決めました!
今回はレッド・ツェッペリンのおすすめアルバムを5枚選んでご紹介します。
その前にまずはレッド・ツェッペリンの何がすごいのか?バンドの経歴を含む簡単なご紹介をしたいと思います。
レッド・ツェッペリンについて
レッド・ツェッペリンは、1968年に結成されたイギリスのロックバンドです。
ロック史において最も影響力のあるバンドの一つです。
彼らの音楽は、ロック、ブルース、フォーク、さらにはクラシック音楽や東洋的なサウンドを融合させ、ハードロックやヘヴィメタルの元となるような革新的なサウンドを作り上げました。
レッド・ツェッペリンの4人のメンバー、ロバート・プラント(ボーカル)、ジミー・ペイジ(ギター)、ジョン・ポール・ジョーンズ(ベース、キーボード)、ジョン・ボーナム(ドラム)は、それぞれが高度な技術と独自の音楽性を持ち、バンドとして完璧なハーモニーを生み出しました。
レッド・ツェッペリンは、ジミー・ペイジが元々在籍していた「ヤードバーズ」の解散後に結成されました。
ペイジは新しいプロジェクトのために才能あるミュージシャンを探し、最終的にプラント、ジョーンズ、ボーナムと出会い、レッド・ツェッペリンの原型が完成しました。
デビュー・アルバム『レッド・ツェッペリン I』は1969年にリリースされ、瞬く間に成功を収め、彼らの名を世界中に広めました。
重厚なギターリフ、力強いボーカル、複雑なリズムセクションが特徴のこのアルバムは、ロック音楽の新たな時代を切り開いたのです。
レッド・ツェッペリンの代表曲といえば、1971年に発表された「天国への階段(Stairway to Heaven)」が真っ先に挙げられます。
この曲は約8分にわたる壮大な展開を持ち、ゆったりとしたアコースティックなイントロから、ジミー・ペイジのエレクトリックギターのソロへと移行し、クライマックスを迎えます。
「天国への階段」はロック・バラードの最高峰とされ、多くのリスナーに影響を与え続けています。
また、もう一つの代表曲「移民の歌(Immigrant Song)」は、バンドのエネルギッシュな側面を象徴するナンバーです。
1970年のアルバム『レッド・ツェッペリン III』に収録されており、プラントの力強いボーカルとペイジの切れ味鋭いギターリフが特徴です。
この曲は北欧神話をテーマにしており、レッド・ツェッペリンの音楽に影響を与えた様々な文化的要素の一端を垣間見ることができます。
レッド・ツェッペリンはスタジオでの創造力だけでなく、ライブ・パフォーマンスでも評価を得ていました。
特にジョン・ボーナムのパワフルなドラム演奏は、ライブでは圧巻の迫力を放ちました。
彼のドラムソロは、ただのリズムパートを超え、まるで楽曲全体を支配するような存在感を放ち、多くのファンを魅了しました。
その様子は映像作品「レッド・ツェッペリン DVD」で観ることが出来ます。
レッド・ツェッペリンはその後も数々の名盤をリリースし、1970年代を代表するロックバンドとしての地位を確立しました。
1973年にリリースされたアルバム『聖なる館(Houses of the Holy)』や、1975年の『フィジカル・グラフィティ(Physical Graffiti)』は、彼らの音楽的な幅広さを示す作品です。
これらのアルバムでは、レッド・ツェッペリンがハードロックだけでなく、ファンクやレゲエ、クラシック音楽など、様々なジャンルに挑戦し続けていたことが伺えます。
しかし、1980年にドラマーのジョン・ボーナムが急逝したことにより、バンドはその歴史に終止符を打つこととなりました。
残されたメンバーは、ボーナムなしでの活動は不可能であると判断し、レッド・ツェッペリンは解散を決定しました。
それでもなお、彼らの音楽は色あせることなく、現代のアーティストやバンドに多大な影響を与え続けています。
レッド・ツェッペリンの成功の要因は、メンバーそれぞれの個々の才能が一体となり、他に類を見ない音楽を作り上げたことにあります。
ロバート・プラントの独特なハイトーンボーカル、ジミー・ペイジのギターによるリフとソロの巧妙さ、ジョン・ポール・ジョーンズの音楽理論に基づいたアレンジメント、そしてジョン・ボーナムの圧倒的なドラムプレイ。
これらが一つに結びつくことで、唯一無二のバンドとしてのアイデンティティを確立したのです。
レッド・ツェッペリンは、解散後もライブ再結成を行うことがありましたが、バンドとしての新たな活動は行っていません。
それでも、彼らの音楽は今日もなお世界中で愛され続け、ロックの歴史に輝かしい足跡を残しています。
それでは今回はレッド・ツェッペリンのオリジナル・アルバムから僕が好きな作品を5枚選んでランキング形式でご紹介します。
ベスト盤やコンピレーション・アルバムにライブ盤は除外しています。
まずは第5位からです。
レッド・ツェッペリンのおすすめアルバムを5作品選んでランキング形式でご紹介!
第5位:Led Zeppelin – 『Led Zeppelin』
第5位は、1969年にリリースされたデビュー・アルバムの『Led Zeppelin』です。
邦題は『レッド・ツェッペリン I』でした。
本作は、バンドのデビュー作でありながら、その革新的なサウンドで世界中の音楽ファンを魅了しました。
ブルースをベースにした重厚なギターリフと力強いボーカル、そして圧倒的なリズムセクションが特徴で、聴く者を圧倒します。
シングル曲になった”Good Times Bad Times”や”Communication Breakdown”にワウギターを上手く使ったサイケデリックな”Dazed and Confused”などの楽曲は、当時のロックシーンに新風を吹き込みました。
“Dazed and Confused”は、後にエアロスミスがそのサイケデリックな曲調を”Sweet Emotion”の後半のジャム・パートを作るのに影響を受けています。
こういったロックな曲以外にも、ジョンジー(ジョン・ポール・ジョーンズの愛称)が弾くオルガンが威厳を放つ “Your Time Is Gonna Come”や、ヴィラム・ジャサニが叩くインドのリズム楽器「タブラ」に合せてジミー・ペイジがアコギを弾いたインスト曲”Black Mountain Side”などのように、「単なるロック・ンバンドの枠に収まらない音楽性の広さ」をこのデビュー作からも見られます。
また伝説のブルース・ベーシストでコンポーザーでもあったウィリー・ディクソン作の”You Shook Me”や”I Can’t Quit You Baby”といったブルース曲のカヴァーもツェッペリンのルーツを感じさせます。
ちなみに”You Shook Me”は、マディ・ウォーrターズのバージョンが有名で、”I Can’t Quit You Baby”はオーティス・ラッシュのバージョンが有名です。
ジミー・ペイジのギターワーク、ロバート・プラントのパワフルなボーカル、ジョンジーのしっかりとしたベース、そしてボンゾ(ジョン・ボーナムの愛称)のダイナミックなドラムが融合し、デビュー作から既に他のバンドにはない独自の音楽性を生み出しています。
第4位:Led Zeppelin – 『Physical Graffiti』
第4位は、1975年にリリースされた6作目で2枚組の大作『Physical Graffiti』です。
本作は、ツェッペリンの創造力と音楽的幅広さが全て詰まったような作品です。
収録された全15曲は、ハードロックからフォーク、ブルース、さらにはエキゾチックな要素までを取り入れており、どの曲も非常に多様性に富んでいます。
まさにレッド・ツェッペリンの音楽の真髄を感じられる作品となっています。
インド音楽の要素を取り入れた大作”Kashmir”は、壮大なサウンドスケープと独特のリズムが特徴的で、ツェッペリンの代表作の一つです。
また、シングル・カットもされた”Trampled Under Foot”ではファンク的な要素を取り入れた新しいスタイルが楽しめます。
ジョンジーが弾くファンキーなクラヴィネットの音色は、まさにスティーヴィー・ワンダーを彷彿させます。
前作『Houses of the Holy』のアルバム・タイトルながら、本作に収録された”Houses of the Holy”など、この3曲がベスト盤でも常連曲なので本作の中でも特に有名な曲です。
もちろんそれ以外にもジミー・ペイジが弾くギターリフがかっこいい”Custard Pie”や”Sick Again”といった曲もロックしています!
こういった曲を聴くといかにジミー・ペイジが天才リフ・メイカーだったのかがわかりますね。
さらには、伝説のブルースマン、ブラインド・ウィリー・ジョンソンの曲をロックにアレンジした”In My Time of Dying”では、ジミー・ペイジが弾くスライドギターが宙を裂くように暴れ回ります。
この曲のイントロを聴いていると、エアロスミスが1979年にリリースしたアルバム『Night In The Ruts』に収録されていた曲”Cheese Cake”が似ていることに気付きます。
おそらくジミー・ペイジを尊敬しているジョー・ペリーも本作を聴いて、大いに影響を受けたのでしょう。
“Houses of the Holy”や “Trampled Under Foot”に”Kashmir”が収録されたDisc 1に比べると、Disc 2は少々地味に感じられますが、しかしこちらには3作目の『Led Zeppelin III』以来となるフォーキーな楽曲が収録されていたりします。
そういった意味でも『Physical Graffiti』は、レッド・ツェッペリンの音楽の幅広さを存分に堪能できるアルバムです。
ただ、もっと上位ではなく第4位に決めたのは…ちょっと曲数が多すぎて普段聴くにはしんどく感じることもあるからです。
ちなみにアルバム・ジャケットのアートワークは、ニューヨークのイースト・ヴィレッジにあるセント・マークス・プレイス(St. Mark’s Place)の建物がモデルです。
第3位:Led Zeppelin – 『Houses of the Holy』
第3位は、1973年にリリースされた5作目のアルバム『Houses of the Holy』です。
邦題は『聖なる館』でした。
過去4作と比べて、バンドの更なる進化を示す重要な作品です。
これまでのハードロックの枠を超え、ファンク、レゲエ、プログレッシブ・ロックなど、さまざまなジャンルに挑戦しているのがこのアルバムの特徴です。
斬新なアプローチと多様なサウンドが詰まったこの作品は、レッド・ツェッペリンの音楽的な幅広さを改めて感じさせてくれます。
特に冒頭の”The Song Remains the Same”や”The Rain Song”は、エモーショナルな展開と複雑なアレンジが魅力で、リスナーを深い感動へと導きます。
本作を聴く際は、”The Song Remains the Same”のイントロのダブルネック・ギターの12弦の音が堪らないんですよね♪
この冒頭の2曲が特に好きで、初めてツェッペリンを聴いた高校生の頃は繰り返し何度も何度も聴きました。
この2曲だけでなく、”No Quarter”もロックの枠を越えたような感動的な楽曲です。
もちろん本作はそれだけでなくシングル・カットされた”D’yer Mak’er”ではレゲエ風のリズムを取り入れたユニークなアレンジが楽しめます。
また後にジャズ・サックス奏者のジョシュア・レッドマンがエラスティック・バンド名義でリリースした『Momentum』でもカヴァーしていたファンク曲”The Crunge”も必聴です!
ちなみにジョシュア・レッドマンのカヴァー・バージョンでベースを弾いているのは、レッチリのフリーでした。
天才リフ・メイカーのジミー・ペイジが本作でも”Dancing Days”や”The Ocean”といった曲で良い仕事をしています。
『Physical Graffiti』と比べると収録曲も8曲とコンパクトでちょうど良く、ツェッペリンの音楽性の広さを楽しめる名盤なのですが…第3位となりました。
この後にご紹介する2作があまりにも強力なため…です。
他のバンドの作品だったら間違いなくこのアルバムが1位なのですが…ツェッペリンは本作の前にすんごいのを2作品作っていました!
第2位:Led Zeppelin – 『Led Zeppelin II』
第2位は、1969年にリリースされた2ndアルバム『Led Zeppelin II』です。
このアルバムは、前作『Led Zeppelin』に続くもので、ブルースを基調としながらも、さらに力強く、エネルギッシュなサウンドが特徴です。
ツェッペリン独自の音楽スタイルが確立された重要な作品であり、多くのロック・ファンに愛されている歴史的名盤でもあります。
アルバムを代表する曲”Whole Lotta Love”は、ジミー・ペイジの印象的なギターリフと、ロバート・プラントの力強いボーカルが融合し、ロック史に残る名曲として広く知られています。
この曲のワウペダルを使ったギターソロや過激なエフェクトの使い方は、当時としては非常に斬新で、サイケデリックな要素も感じられます。
また、リリースから半世紀以上が経った今でも、クラシック・ロックの代表曲として多くのファンに聴かれ続けています。
あのプリンスもお気に入りの曲だったようで、ライブでちょくちょくこの曲のギターリフを弾いていました。
ちなみにこのリフの「ジャジャージャジャージャン!」がジョン・コルトレーンの代表作『A Love Supreme(至上の愛)』の1曲目”Acknowledgement(パート1:承認)“のベースのイントロに似ているのは、偶然ではなさそうです。
これはアシュリー カーン 著『ジョン・コルトレーン『至上の愛』の真実 』に書かれていたのですが、サイケデリック・ロックが流行っていた当時の音楽シーンでは、イケナイ葉っぱを吹かしながらコルトレーンの『至上の愛』のレコードを聴きながらトリップするロック・ミュージシャンが多かったとのこと。
グレイフル・デッドのベーシスト、フィル・レッシュ曰く、当時のサンフランシスコではストリートを歩いていると通りすがった家から『至上の愛』のレコードの音が漏れていることがよくあったのだとか。
当時のロック・ミュージシャンは、ジャンルの垣根を越えてジョン・コルトレーンを聴き親しんでおり、それはツェッペリンのメンバーも例外ではなかったのかもしれませんね。
本作に収録されている”The Lemon Song”の中間部分の6度音程のダブルストップを用いたフレーズが、ハウリン・ウルフの”Killing Floor”から拝借したものだったように、”Whole Lotta Love”のギターリフもジョン・コルトレーンの”Acknowledgement”から拝借したのでしょう。
それはそうと、本作には他にも”Heartbreaker”や”Ramble On”といった人気の名曲が詰まっています。
“Heartbreaker”のギターリフは、ロック・ギター奏者なら一度は弾いてみたくなるフレーズで、ジミー・ペイジのリフ・メイカーとしての才能がよくわかる曲です。
僕も高校生の時にこの曲は何度も練習したものです。
そして”Ramble On”は、フォークとロックが融合した楽曲で、フォーキーな次回作『Led Zeppelin III』の布石とも言える一曲です。
後の”Stairway to Heaven(天国への階段)“や”The Rain Song”へと繋がるような感動的なバラード曲”Thank You”も必聴です。
『Led Zeppelin II』は、スタジオでの実験的な要素と、ライブでのエネルギーをそのまま詰め込んだ作品です。
本作の録音はツアー中に行われ、各地でのライブパフォーマンスの合間にスタジオに入り、少しずつ完成されていきました。
そのため、アルバム全体にライブ感が漂っており、まるでレッド・ツェッペリンの熱狂的なステージにいるかのような感覚を味わえます。
ハードロックの基礎を築いたこのアルバムは、今でも色あせることなく、レッド・ツェッペリンのエッセンスを存分に堪能できる必聴アルバムです。
本作も完成度の高いアルバムですが…やはり1位はあのアルバムしかありません!
第1位:Led Zeppelin – 『Led Zeppelin IV(Zoso)』
ベタな選出ですが…第1位は、やはりレッド・ツェッペリンを代表するこのアルバムです!
本作は、1971年にリリースされたレッド・ツェッペリンの4作目のアルバムとなった『Led Zeppelin IV』です。
ツェッペリンのキャリアの中でも最も象徴的な作品の一つとして知られています。
日本では『レッド・ツェッペリンⅣ』と呼ばれることが多いですが、実際には公式にはタイトルがないため、『無題』のアルバムです。
アートワークに記されたメンバー4人のシンボル・マークから通称『フォー・シンボルズ(Four Symbols)』と呼ばれることもあります。
アルバムは印象的なギターリフを持つ”Black Dog”から始まります。
この曲は重厚なリフと複雑なリズム構成が特徴で、ロバート・プラントの力強いボーカルが際立っています。
ギタリストなら一度は弾いてみたいギターリフを持つ曲です。
そういう僕もこの曲のリフが好きで、ギターを試奏する際にたまに弾く曲です。
続く2曲目の”Rock and Roll”は、その名の通り、純粋なロックンロールのエネルギーが詰まった曲で、バンドのライブでも人気のあるナンバーです。
どちらの楽曲も、ボンゾのダイナミックなドラム演奏を存分に堪能できます。
また、本作もバンドの多様な音楽的影響を反映しており、ブルース、フォーク、ハードロックなど、さまざまな要素が絶妙にブレンドされています。
3曲目”The Battle of Evermore”では、マンドリンを使用し、伝統的なフォークの要素を取り入れたユニークなサウンドを展開しています。
そして4曲目の”Stairway to Heaven(天国への階段)“です。
ゆったりとしたアコースティックなイントロから始まり、次第にスピードとエネルギーを増し、壮大なエレクトリックギターのソロへと発展していくこの曲は、ロバート・プラントの神秘的な歌詞と、ジミー・ペイジの技巧的なギターワークが見事に融合し、音楽史に残る名曲となっています。
「天国への階段」は、まさにロックバラードの金字塔として、多くのギタリストや音楽ファンに長年愛され続けており、ツェッペリンのライブでも欠かせない一曲でした。
もちろん僕も高校生の時に初めてこの曲を聴いた時は、感動したのと共に驚きました!
なんせそれまでロックと言えば「騒々しい音楽」といった偏見に満ちたイメージしか持っていなかったからです。
しかしこの曲はどうでしょうか…もはや”芸術”の域に達しています。
間違いなくツェッペリンの最高傑作であり、そしてロック界を代表する最も素晴らしい曲だと言えます。
この「天国への階段」が収録されていることで、本作『Led Zeppelin IV』はツェッペリンの全アルバムの中でも不動の1位でしょう!
この4曲が収録された前半(レコードで言うところのA面)があまりにも強力な作品です。
もちろん後半にも不思議な歌メロの”Misty Mountain Hop”やジミー・ペイジのヘヴィなギターリフが光る”Four Sticks”に、マンドリンの音色が優しく鳴る”Going to California”、そしてメンフィス・ミニーが歌った古いブルース曲をバンドのスタイルでアレンジした”When the Levee Breaks”など名曲ばかりが収録されたアルバムです。
本作『Led Zeppelin IV』は、商業的にも大成功を収め、世界中で数千万枚のセールスを記録しています。
全米売上だけでも2,320万枚を超えています。
ハードロックからフォーク、ブルースまで、多様な音楽要素が詰め込まれたこのアルバムは、レッド・ツェッペリンの音楽を理解するための必聴作品です。
ベタな選出で今回のランキングでも第1位に選びましたが、しかし全音楽ファンにとって、『Led Zeppelin IV』は絶対に聴いておきたいアルバムだと断言できます!
以上、【レッド・ツェッペリンのおすすめアルバムを5作品選んでランキング形式でご紹介!】でした。
僕が人生で初めてレッド・ツェッペリンを聴いたのは、高校2年生の時に近所のCDショップで購入したCD2枚組のベスト盤『ベスト・オブ・レッド・ツェッペリン』でした。
当時は既にエアロスミスに大ハマりしていた時期だったのですが、エアロスミスについて調べていると「レッド・ツェッペリンから影響を受けたバンド」とか「ジョー・ペリーはジミー・ペイジを尊敬している。」といった内容を音楽雑誌で読むことがありました。
「エアロスミスに影響を与えたバンドならすごいに決まってる!これは早めに聞かないと!」と高校生だった僕は慌ててバイト代をかき集めて近所のCDショップへ行きました。
そしたら当時としては大容量だったCD2枚組のベスト盤が見つかりました。
『Led Zeppelin II』や『Led Zeppelin IV』も並べられていたのですが、まずは一気に代表曲が聴ける2枚組ベスト盤から購入することにしました。
家に帰って全部を通して聴いてみると…すっかりハマってしまいました!
そして感動的な大作”Stairway to Heaven(天国への階段)“を聴いて、本当に驚きました!
あの衝撃は、まだ10代だったからこそ余計に大きかったのでしょう。
僕のまだ未熟だった感性は大いに刺激され、その日のうちに何度も何度もCD2枚を繰り返して聴き続けました。
すると…自室の窓から朝日が入り込みました。
「あれ?CD聴き始めたのは夜10時じゃなかったっけ?」
徹夜でこのベスト盤を聴き続けていたので頭が混乱していました。
「いつの間にか朝になってる!…まいっか、今日は学校休もう。」
僕は高校時代の3年間にこの時と初めてジョン・コルトレーンのベスト盤を購入した時に2回、CDを徹夜で聴いて学校をズル休みしました。
でも社会的にはズル休みであっても、僕にとってはどちらも「人類の歴史に残る芸術作品に触れて感動出来た貴重な時間」でした。
高校生活の2日間は、今となっては特に影響のないことです。
それどころかその3年間も、その後の海外へ行ったり、バンドでのライブ活動といった人生経験から比べるとほとんど忘れてしまうような印象の薄い人生の1コマでしかありません。
しかし初めてレッド・ツェッペリンを聴いて感動したあの夜のことは今でも鮮明に覚えています。
音楽とは、人間の記憶に最も深く刻まれる「印」なのかもしれません。
レッド・ツェッペリンの4つのシンボルが生み出した「印」は、10代だった僕を一晩のうちに天国へと連れて行ってくれたのです。
「ロックが時代遅れのおっさんの音楽」と言われるようになってかれこれ何年以上が経つのでしょうか。
Z世代と呼ばれる最近の若者は「ロックはダサい音楽!」と考えている子の方が多いようで、そもそもロックに興味がない子がほとんどでしょう。
でも、だからこそ今の若者にレッド・ツェッペリンを聴いてもらいたいと思います。
僕が高校生だった頃は、インターネットも普及しておらず、こういった音楽の情報を雑誌で読む以外手段がありませんでした。
でも今はこうやって僕自身がインターネットを通して自身の経験を発信することが出来ます。
もしこのブログ記事を何かのきっかけで読んでくれている10~20代の若い世代の人は、ぜひこのランキングを参考にレッド・ツェッペリンを聴いてみて下さい。
もちろん僕と同年代や、更に年配の方も久しぶりにレッド・ツェッペリンを聴きなおしてみて下さい。
今回初めてレッド・ツェッペリンを知ったという方にも、ぜひ早めに聴いて欲しいと思うバンドです。
【PR】Amazonギフトカードのご紹介
Amazonギフトカードは、Amazonサイトのお買い物でご利用できるプリペイド式のカードです。
お買い物をする際に現金と同様に利用できるためクレジットカードの登録なしにAmazonでお買い物が出来ます。
クレジットカードの登録をしたくない方や、クレジットカードでのお買い物をしたくない方にもおすすめです。
他に関連するお勧め記事
エアロスミスのブログ記事シリーズまとめ
ローリング・ストーンズのおすすめアルバムを5作品選んでランキング形式でご紹介!
『iPadで描くブルースの偉人シリーズ』⑧ブラインド・ウィリー・ジョンソンとレヴァランド・ゲイリー・デイヴィスを描いてみました。
※このブログに掲載しているイラストや写真、テキスト等の無断引用・無断借用・無断転載・無断使用は固くお断りしております。ご利用はご遠慮ください。