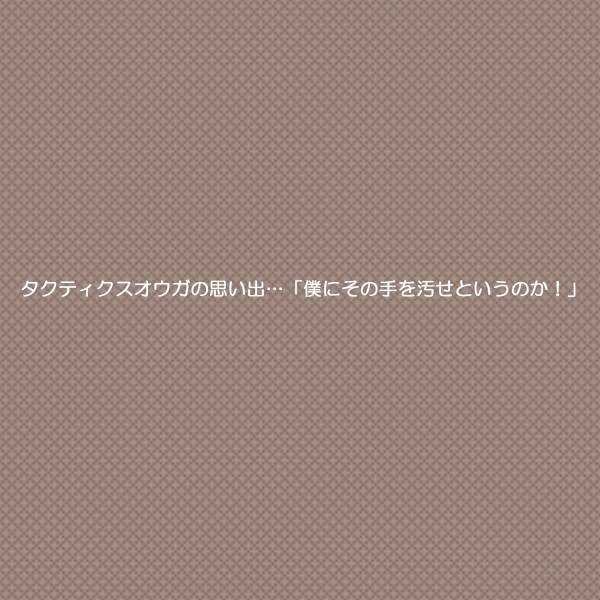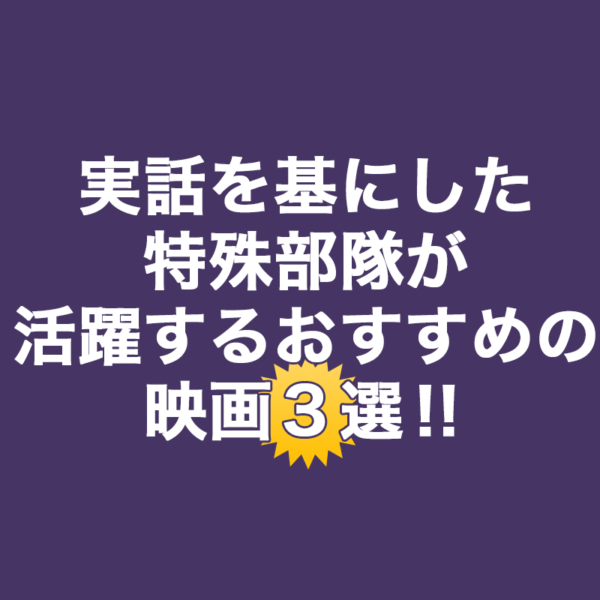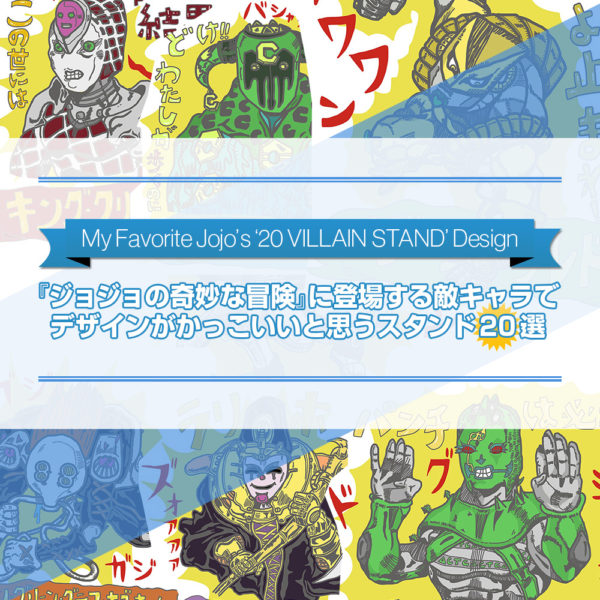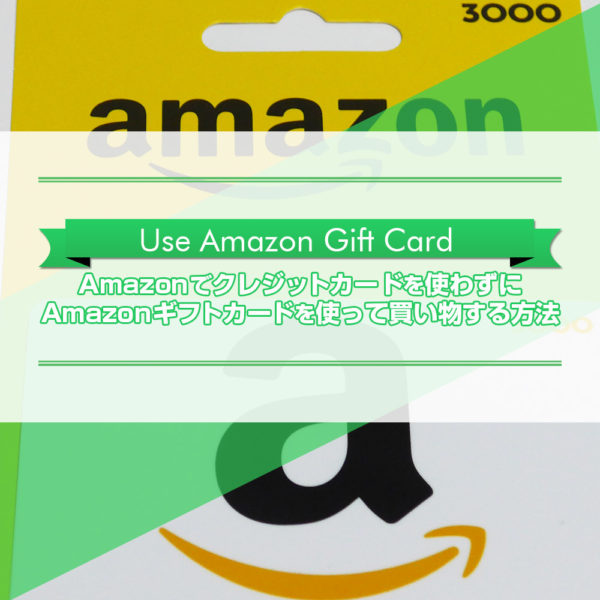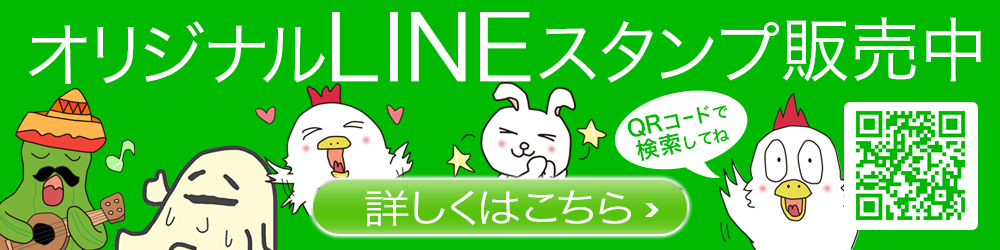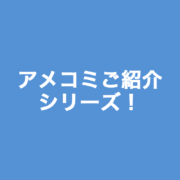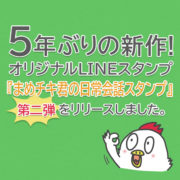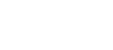2019/11/23
思い出に残るスーパーファミコンの名作ソフト30選

個人的に思い出に残るスーパーファミコンの名作ソフトを30作品選んでみました。
以前、このブログで僕が夢中になったスーパーファミコンの名作シミュレーションRPGゲーム『タクティクスオウガ』をご紹介していました。
タクティクスオウガの思い出…「僕にその手を汚せというのか!」
今回はその続きのようなもので、僕が子供の頃に夢中になったスーパーファミコンのゲームソフトをご紹介したいと思います。
来年で30周年!日本が生んだ世界に誇るゲーム機スーパーファミコン!
さて、僕と同世代ぐらいの人でなくても『スーパーファミコン』というゲーム機のことを知っている人は多いかと思います。

ゲーム&ウオッチの事業で成功した任天堂が、その成功を基にして1983年7月15日に家庭用ゲーム機『ファミリーコンピューター』を発売したのが日本のゲームブームの始まりだと思います。
それを略して『ファミコン』と呼ばれるようになるのですが、このゲーム機があったからこそ今に続く日本のゲーム文化が育ったんだと僕は感じています。
ちなみに驚くことに任天堂は、元は花札を取り扱う老舗の玩具会社でした。
僕の祖父が任天堂の花札を持っているのを子供時代に見た記憶があります。
子供ながらに「ファミコンのメーカーが花札も売ってるの?」とびっくりしたことを覚えています。
その後、父に「花札やトランプを売っていた会社が、いつの間にかゲーム・ウォッチを売るようになったんだ。」と教えてもらいました。
そんな『ファミコン』の上位機種となるハードが7年後に発売されることになります。
それが1990年11月21日に発売された『スーパーファミコン』です。
なんと、このブログを書いている時に気づいたのですが、来年で発売30周年なんですね!
僕も年を取るはずだ…。
この『スーパーファミコン』が発売されたのは、僕が小学生の頃でした。
幸運なことに僕は発売してすぐに手に入れることが出来ました。
それから6年間、僕は『スーパーファミコン』に夢中になりました。
しかし残念ながら、僕が最後にやったゲーム機も『スーパーファミコン』までです。
1997年になると『ファイナルファンタジーVII』がプレイステーションから発売されたことで、任天堂一強だったゲーム機業界が一変したように思います。
そのため僕と同じ世代の人でもプレステ派の人も多かったと思いますが、僕自身は1996年以降ゲームを買わなくなってしまいました。
このブログの”MUSIC”のカテゴリー記事の多さをご覧の通り、ゲームよりも音楽の方に夢中になりました。
1996年の半ば辺りから音楽オタクになっちゃったんです。
音楽CDを集める方にお金を掛けるようになり、ギターを練習することに時間を割くようになったので、ゲームとの両立が難しくなってしまいました。
しかし決してゲームが嫌いなわけでも、やりたくないわけでもありません。
僕の中でのゲームの思い出は『スーパーファミコン』で止まっていますが、その分「子供時代の良い思い出」として残っています。
そんなわけで、今回は僕の思い出に残るスーパーファミコンの名作ゲームを30作品に絞ってご紹介したいと思います。
もちろん全てのスーファミのソフトを遊べたわけではないのですが、僕がリアルタイムで遊べた数少ないソフトの中でも、特に印象に残った作品が幾つかあります。
今回ご紹介する30作品に目を通して、僕と同世代の人には「懐かしいな~」と感じてもらったり、若い世代の人には「こんなレトロゲームもあったんだな~」と知ってもらえたらと思います。
それでは発売順に30作品ご紹介したいと思います。
…の前に、ちょっとした注意点を!
というか、言い訳をさせてください!(笑)
こういったスーパーファミコンの名作ソフトをいくつか挙げる際に必ずと言っていいほど選ばれる『クロノ・トリガー』と『ドラゴンクエストVI 幻の大地』が入っていないのは、僕が遊んだことないからです。
『クロノ・トリガー』をやっていないことに関しては、同世代の友達なんかにも「え、あの名作やってないの⁉」と驚かれてしまうのですが、僕もやっておくべきだったと後悔しています。
当時は『タクティクスオウガ』や『フロントミッション』のようなシミレーションRPGにハマっていたので『クロノ・トリガー』は未体験のまま終わりました。
また『ドラゴンクエスト・シリーズ』はもちろん好きなのですが……『ドラゴンクエストVI 幻の大地』が発売された当時は、『ロマンシング サ・ガ3』にハマっていました。
その後、『ロマンシング サ・ガ3』をクリアしてから『VI 』もやる予定だったのですが、音楽に目覚めてしまいました。
そういったわけで『クロノ・トリガー』と『ドラゴンクエストVI 幻の大地』がランクインしていないことに関しては、あくまでも僕が当時リアルタイムで遊んだソフトの中から選ぶ『個人的名作ソフト選』ということでご了承ください。
それでは改めて『思い出に残るスーパーファミコンの名作ソフト30選』のご紹介です!
()内はリリース日時です。
1.スーパーマリオワールド (1990年11月21日)
当時、スーファミのゲーム機と共にセットでこのソフトを親に購入してもらった僕と同世代の人は多いんじゃないのかな?と思います。
僕もファミコン時代からマリオ・シリーズが好きだったので、まずはハードと同時発売された本作を楽しみにしていました。
もちろん言うまでもなく、クォリティーの高いゲームでした。
今でこそマリオもリアルな3Dになっていますが、当時の僕らにはこの『スーパーマリオワールド』のグラフィックも衝撃的でした!
ファミコンとの違いに驚きました!
またそれまでのマリオと違って、ヨッシーという相棒の恐竜まで出てくるというオモシロ要素も追加されていました。
そのヨッシーが木の実を食べると卵を産んだり、炎を吐く赤ヨッシーに砂埃を放つ黄色ヨッシー、空を飛ぶ青いヨッシーのような特殊なタイプもいるという遊び心も満載でした。
ゲーム内容に関しても簡単すぎず難しすぎず、バランスの良い出来だったので何度も飽きずにプレイすることが出来ました。
それにやり込み要素もありました。
「ネイティブスター」という裏面を攻略すると、それまでのステージの配色や設定などが変わるというやり込み要素は驚きでした。
「ネイティブスター」後の別世界では、カメのノコノコが甲羅を背負わずに、マリオの顔をした被り物を付けるようになります。
これには子供ながらに笑いました。
今遊んでも面白さは変わらないであろう永遠の名作ゲームだと思います。
発売順で最初にご紹介することになりましたが……今回ご紹介する30作品の中でも、文句なしに一番の名作だと言えます。
ぜひ今の世代の若い人にも「出来の良いレトロゲーム」として遊んでもらいたい作品です。
また僕らの世代の人にも「懐かしの名作ゲーム」として忘れないでもらいたいなと思います。
僕も30年ぶりに、またやってみたくなりました。
●ゲームの完成度 : ★★★★★
●グラフィックの綺麗さ : ★★★★★
●飽きないゲーム性 : ★★★★★
●ヨッシーの使い捨て度 : ★★★★★
●ピーチ姫ってさらわれ過ぎじゃね? : ★★★★★
2.ファイナルファイト (1990年12月21日)
俗にいう「横スクロールゲーム(ベルトスクロール・アクションゲーム)」の名作といえば、やはりこの『ファイナルファイト』ですね。
もともとは1989年にカプコンからアーケードゲーム用に制作されていました。
それがスーファミのリリースと共に移植された作品です。
プレイヤーは、バランス型のコーディーとスピード型の忍者ガイ、それにパワー型のハガーの3キャラクターから好きなキャラを選んでゲームを始めます。
それぞれに特技もあって、他キャラとの差別化がきっちりなされています。
例えば、他のキャラだとナイフを拾っても投げる以外の攻撃しか出来ないのですが、コーディーだと何度も敵キャラを刺して使うことが出来ます。
これが卑怯なぐらい強かったりもします!
またガイだと、画面端の壁を使って三角飛びをして敵にキックを食らわすことが出来ます。
そしてハガーだと、敵に近接して捕まえることが出来て、そのままジャンプからパイルドライバーという大技を食らわすことが出来ます。
それぞれに個性的な特技があるのですが、共通してハメ技もありました。
敵を2,3発殴ってそのままレバーを後ろに入れて敵を投げ飛ばすというものです。
これを使うと、敵に囲まれても投げ飛ばした敵に当てて回避することが出来ます。
更には、投げずに一瞬だけ後ろを向いて、また前を向いてパンチを続けると…敵を倒れさせないままで何発もパンチを食らわすことが出来ます。
こうなってくると、卑怯なハメ技になってゲームバランスを壊してしまうことになります。
そういったバグにも似たハメ技が存在していたのも、スーファミ時代の面白さだったと思います。
このゲームも、何度も何度もクリアしてとことん遊んだ思い出です!
●ゲームの爽快感 : ★★★★★
●主人公のかっこよさ : ★★★★
●メトロシティの治安 : ★
●ハガーの娘の美人度 : ★★★★★
●ラスボスが高層ビルから落ちるのは定番? : ★★★★★
3.シムシティ (1991年4月26日)
おそらく僕が人生で初めて遊んだシミュレーションゲームだったと思います。
プレイヤーが市長となり、町を造って都市経営するという画期的なシミレーションゲームです。
「必殺技で敵を倒して世界を救う!」というようなわかりやすいストーリーがあるのではなく、町を俯瞰する地味な視点と、ほぼゴールのないゲーム性には驚きました。
子供だった当時の僕には難しすぎました。
むしろ今の自分の年齢で遊んだ方がより楽しめるんだろうな~といった「大人のゲーム」です。
しかし、わけもわからず当時の僕はかなりの時間を費やしてこのゲームを遊びました。
特に、線路を造って電車が走る様子が好きでした。
意味もなく線路を増やしていって電車だらけにしたこともあります。
また、町に公園を造ることで治安を良くするというアイデアも面白かったです。
でも、海外の映画やドラマを観ていると、強盗やシリアルキラーって夜の公園で人を襲ったりしているシーンもあったりするので、これは必ずしも正しいとは言えませんよね。
でも町の治安を良くして市民からの不満をなくすために公園を造って、そして公園の横に電車の駅を造って、計画性のない無茶苦茶な町が完成しました。
そこで満足していると…急に現実離れした怪獣が現れて町を壊されてしまいます!
これには驚きました!
「そこはリアルじゃないのかよ!」って。(笑)
しかし今にして思えば、画期的なゲームだったと言えます。
●町を造る面白さ : ★★★★
●町を造る難しさ : ★★★★
●町を無茶苦茶にする楽しさ : ★★★★★
●リアリティ : ★★
●これどうやったら終わるの? : ★★★★★
4.がんばれゴエモン~ゆき姫救出絵巻~ (1991年7月19)
ファミコン版でも人気だった『がんばれゴエモン』シリーズのスーファミ版第1弾となった『がんばれゴエモン~ゆき姫救出絵巻~ 』です。
更にパワーアップしたグラフィックにアクション時の細かい動き、そして個性的なボスキャラ等、本当に面白いゲームでした。
プレイヤーは、ゴエモンを使って『ファイナルファイト』と同じような「横スクロール」のゲームを楽しむことが出来ます。
登場するキャラクターがどれもかわいくデザインされているので、女の子でも楽しく遊べる良作だったと思います。
といっても、決して簡単ではないゲームでした。
●江戸時代を舞台にした楽しさ : ★★★★★
●横スクロールゲームの完成度 : ★★★★
●町を駆け巡る楽しさ : ★★★★
●やや分かりにくいストーリー : ★★
●明石の大ダコがかわいいよね? : ★★★★★
5.バトルドッジボール 闘球大激突! (1991年7月20日)
僕らの世代は、まだJリーグも黎明期で、小学生の一番のスポーツといえばドッジボールでした。
僕自身はドッジボールはあまり得意ではなかったのですが、ゲームではハマりました!
この『バトルドッジボール 闘球大激突! 』では、SDディフォルメされたガンダムや仮面ライダーにウルトラマンをプレイアブル・キャラクターとして使うことが出来ました。
俗にいう「コンパチヒーローシリーズ」です。
そんな日本に生まれた男の子であれば誰しもが憧れるようなヒーロー達を使ってドッジボールが出来るという夢のような作品でした。
こういったドッジボールのゲームでは『くにお君シリーズ』の方が人気がありましたが、僕はガンダムが好きだったのでこの『バトルドッジボール 闘球大激突! 』の方にハマりました!
当時は夏休みや冬休みに家族で祖父の田舎に帰った際に、年の近い従兄弟同士でこのゲームを喧嘩になるまでとことん遊んだものです!(笑)
ちなみに僕が一番好きだったキャラクターは、ナイトガンダムチームでした。
●キャラクターの魅力 : ★★★★★
●キャラクターの豊富さ : ★★★★
●ドッジボールゲームの完成度 : ★★★
●外野のザクのかわいさ : ★★★
●対戦すると喧嘩になるよね? : ★★★★★
6.超魔界村 (1991年10月4日)
1988年に発売された横スクロールゲームの名作の一つ、『大魔界村』の続編でスーパーファミコンになった『超魔界村』です。
僕だけでなく、『魔界村』の世界観に魅せられた人は多いかと思います。
ゲーム性だけでなくその世界観が魅力の一つですよね。
ただゲームの難易度はかなり高かったです…。
主人公のアーサーは、歩く速度も遅く2回攻撃を受けただけで倒されてしまいます。
その割にボスキャラは動きが素早く固いのでなかなか倒すことが出来ません。
そこに強敵レッドアリーマーが飛んでくると…腹が立ってしまいます!
小学生の子供にはかなり難しかったゲームでした!
●世界観の素晴らしさ : ★★★★★
●ゲームの難易度 : ★★★★★
●レッドアリーマーの強さ : ★★★★
●ボスキャラの魅力 : ★★★★
●パンツ一丁の時間の方が長いよね? : ★★★
7.ゼルダの伝説 神々のトライフォース (1991年11月21日)
ちょうどスーファミのハードと『スーパーマリオワールド』が発売された1年後に出たゼルダの伝説シリーズのスーファミ第一弾『ゼルダの伝説 神々のトライフォース』です。
グラフィックの美麗さや主人公リンクのアクション時の動きの細かさなど、全てにおいてファミコン版を凌駕していたと思います。
また謎解きに関しても難しく、様々なアイテムを使いこなせないとクリアすることが出来ませんでした。
特に僕は、中盤でヘブラ山から『闇の世界』に行って、そこからまた『光の世界』に戻って通常では行けない場所に辿り着く部分がわからずにかなり悩みました。
めがね岩でマジカルミラーを使うというのをちゃんと他のキャラのセリフから聞いていませんでした…なのでここでかなり手こずりました。
しかしそれ以降は、太っちょの妖精も見つけて武器も最強にするなど、アイテムもほぼコンプリートしてクリアすることが出来ました。
単にアクションRPGゲームとしてだけでなく、パズルゲームのように頭を使って謎解きをしないといけないというやり込み要素満点のゲームでした。
かわいらしいグラフィックの割には、子供には難解なゲームでしたね。
●ゲームとしての完成度 : ★★★★★
●ゲームの難易度 : ★★★★
●キャラクターのかわいさ : ★★★★
●ボスキャラのキモさ : ★★★★
●みんなゼルダが主人公の名前だと勘違いしていたよね? : ★★★★
8.ストリートファイターII (1992年6月10日)
今では5まで出ている『ストリートファイター・シリーズ』の2作目『ストリートファイターII』です。
1991年にアーケードゲームとして稼働していたものが、1992年になってようやくスーファミに移植されて家庭でも楽しめるようになりました。
1作目の『ストリートファイター』の頃は、僕はまだ子供すぎてゲームを楽しむことが出来ませんでした。
ゲームセンターに行っても、年上の子らが「昇竜拳」を出しているのを横から羨ましく眺めているだけでした。
それが小学生になって、自分でも『ストリートファイターII』をやってみたら…案外簡単に「昇竜拳」を出すことが出来ました。
「なんだ、そんな凄いことじゃなかったんだな~」と思いました。
そしてこれ以降、格闘ゲームにハマることになりました。
この後も30作品の中に格闘ゲームが多く登場するのは、この『ストリートファイターII』をきっかけにして僕が格闘ゲームにハマったからでした。
1作目ではリュウしか使うことが出来なかったプレイヤーが、本作では世界中から集まった8人の格闘家を選んで使うことが出来ました。
今では50キャラぐらい普通に登場する格闘ゲームではありますが、当時は8人のキャラでも多くってびっくりしました!
しかもダルシムのような手足が伸びるキャラクターの驚きは相当でした!
このせいで後に日本でも「ヨガ」が流行った頃にダルシムのことを思い出して、「みんな手足を伸ばしたり火を吐く練習するのかな?」と思ったのは僕だけではないですよね?(ですよね?笑)
またザンギエフの座り弱パンチが、当時とんねるずの番組で流行ったブッチョだったのは学校でも流行りました。
ちなみに僕はゲームセンターの対戦で「待ちガイル」をしてダルシム使いにボッコボコにされた悲しい思い出があります。
このゲームが登場した辺りから、プロ級に上手いゲーマーが育っていったんじゃないのかな?と思います。
ゲーム内よりも、ゲームセンターの方が強者が多かったイメージです。
「俺より強い奴に会いに行く」とは、まさにゲームセンターに対戦しに行くことでした!
●キャラクターの魅力 : ★★★★★
●キャラクターの豊富さ : ★★★★
●格闘ゲームとしての完成度 : ★★★★
●「波動拳」というセリフ聞き飽きた度 : ★★★
●弱いと見せかけてダルシムとザンギエフ強すぎじゃね? : ★★★★
9.パロディウスだ! ~神話からお笑いへ~ (1992年7月3日)
僕はシューティングゲームはあまり得意ではなかったので、ほとんどやったことがありませんでした。
でもスターウォーズが好きなので、グラディウスやR-TYPEのような宇宙を舞台にした世界観は大好きでした。
しかしどう頑張ってもシューティングゲームが苦手で、クリアできなかったのでいつもあきらめていました。
そんな中で『パロディウス ・シリーズ』は、お笑い要素がたくさんで楽しめました。
そのままタイトルが示すようにグラディウスのパロディーになった世界観や、タコやペンギンにツインビーが登場するキャラクターの魅力もありました。
ステージ2の「ちちびんたリカ」は、どうやって倒すのか?すごく悩みましたが、単に回避してほっておくだけというのに当時は驚きました。
ゲームにおいて「敵キャラって絶対に倒さなくてはいけないってわけでもないんだ!」というのを学びました。
僕はこのゲームのステージBGMでアラム・ハチャトゥリアンの『剣の舞』という曲を知りました。
お笑い要素が強いながら、色々と勉強になった作品でもあります。
ちなみに僕がメインで使っていたキャラクターは、ツインビーでした。
ロケットパンチが強力で、敵をガンガン倒せるので爽快でした。
しかし今思うと、子供向けのゲームによく「ちちびんたリカ」のようなキャラクターを登場させたものだな~と。(笑)
●お笑い度 : ★★★★★
●ゆでダコ度 : ★★★★★
●ペンギン度 : ★★★
●グラディウス度 : ★★★
●ベルを上手いこと好きな色にするの難しくね? : ★★★★
10.マリオペイント (1992年7月14日)
僕が初めて使ったデジタルお絵描きセットがこの『マリオペイント』です。
小さい頃から絵を描くのが好きだったのですが、ノートや画用紙を使わずにデジタルの画面で絵を描くのはこれが初めてでした。
ゲームというよりもお絵描きアプリのような感じで、色んな絵を描いて遊ぶことが出来ました。
またそれだけでなく、描いた絵からアニメーションを制作したり音楽を作ったり、ハエ叩きゲームで遊ぶことも出来ました。
ゲームとしてのゴールはありませんが、その分延々と遊ぶことが出来るソフトでもあります。
逆に、止め時がわからない危険なゲームでもあります。
●お絵描き度 : ★★★★★
●自由度 : ★★★★★
●ハエ叩き度 : ★★★
●マリオ度 : ★
●絵を描くって難しいよね? : ★★★★
11.キング・オブ・ザ・モンスターズ (1992年7月31日)
この『キング・オブ・ザ・モンスターズ』というゲームは、『餓狼伝説』や『龍虎の拳』のメーカーであるSNKが作った対戦アクションゲームです
1991年からゲームセンターで稼働していたものが1992年にスーファミ化して発売されました。
プレイヤーは、好きな巨大怪獣を選んで町をぶっ壊しながら格闘ゲームのように対戦することが出来ます。
相手にビルを投げつけたり、東京ドームのような建物が爆発してダメージを受けたり…と。特撮の怪獣映画のような楽しさがあるゲームです。
登場人物も、ゴジラのような恐竜型モンスターやキングコングに岩人間、更には巨大カブトムシと様々なキャラクターが登場します。
中にはアメコミのヒーローのような見た目のキャラもいますが、明らかに怪しニヤケ顔をしています。
その怪物達を使って、パイルドライバーやバックドロップのようなプロレス技や、ビーム光線のような必殺技を使って対戦します。
でも、途中から町を破壊することの方が楽しくなってきたりします。(笑)
●怪獣度 : ★★★★★
●ヒーロー度 : ★
●カブトムシ度 : ★★★
●町を破壊する爽快感 : ★★★★
●登場人物全員ヴィラン? : ★★★★
12.初代熱血硬派くにおくん (1992年8月7日)
ファミコン時代から人気の『くにお君シリーズ』のスーファミ版です。
シリーズ初のスーファミソフトとなったこの『初代熱血硬派くにおくん』は、まさかの修学旅行で大阪に来たとこからストーリーが始まります。
梅田・心斎橋・恵美須町など、大阪に生まれた僕には馴染みのある場所が登場するので当時は面白く感じたのですが、大阪はこんなに危険な町ではありません!(…とも言えないか。笑)
このゲームでは、メインの敵の不良たち以外にも町の人が急に喧嘩を売ってきて戦闘が始まります。
まるで大阪の人は誰にでも喧嘩を売って殴り合いするような描写がされたゲームですが……大阪はこんなに危険な町ではありません!(ん~…とも言えないか。笑)
ただゲームとしての面白さはかなりのものです!
基本は横スクロールのアクションゲームなのですが、RPGのような謎解きも必要で、各キャラクターの会話をちゃんと読んで進まないといけません。
またゲーム内で昼と夜が切り替わるという当時としては画期的なシステムが導入されていました。
もちろん夜の方が酔っぱらいも多く、一般人の敵と戦闘になる可能性も高くなります!
でも、実際の大阪の酔っぱらいの人たちはここまで狂暴ではありません!(ん~…そうでもないか。笑)
その他にも、ゲームの後半には甲子園にも行くことが出来ます。
ここでは阪神タイガースのハッピを着たファンが喧嘩を売ってくることになります!
しかもこの阪神ファンがやたら強かったりします!
阪神ファンの細身の女性キャラにビンタ1、2発で不良のくにお君が負けてしまうのは、なんともシュールでした!(笑)
でも、実際の阪神ファンはここまで狂暴ではありません!(ん~…そうでもないのかも⁉笑)
ちなみにくにお君は、レベルアップするとマッハパンチや大技のジャーマンスープレックスなど多彩な技を覚えて強くなっていきます。
ただ、ジャンプキックが一番使い勝手が良いのは最初から最後まで変わりません。
●熱血度 : ★★★★★
●不良度 : ★★★★★
●喧嘩度 : ★★★★
●電車に轢かれる度 : ★★★
●大阪はこんな町じゃない? : ★
13.スーパーパン (1992年8月7日)
おっさんになった今の僕には、こういったじっくり出来るパズルゲームが楽しかったりします。
海外旅行に行く際に、飛行機の座席に付属しているゲームで毎回遊んで暇潰しをしているのですが、その際によく搭載されているのが『アルカノイド』や『キャンディークラッシュ』に『ビリヤード』等のゲームです。
長いフライト時間を使って僕はこういったパズルゲームをすることが多いのですが、いつも思うのがこの『スーパーパン』のようなゲームも搭載してほしいなって…。
1992年当時にこの『スーパーパン』をやって、従来のパズルゲームと違ったゲーム性や、その謎の世界観に魅了されました。
でもよく考えたら、撃つと分裂する謎の球体が空から跳ね落ちてくる不気味なゲームですよね⁉(笑)
●スーパーパン度 : ★★★★★
●パズル度 : ★★★
●球体度 : ★★★★
●分裂度 : ★★★
●あの球体何なの? : ★★★★★
14.マリオカート (1992年8月27日)
ゲームが好きならみんなハマった?
と、言いたくなるような名作中の名作『マリオカート』なくして、スーファミの名作選は作ることが出来ません!
僕はシューティングゲームだけでなく、カーレース系のゲームも苦手なのですが…『マリオカート』にはハマりました!
これは説明の必要がないぐらい有名なゲームですよね。
僕と同世代の人なら、ゲームが好きでなくても遊んだことぐらいはあるんじゃないかな?って。
友達の家でゲーム対戦する際も、大体この『マリオカート』だった気がします⁉
そしてボロ負けして友達の肩にパンチを食らわして喧嘩になる…っていう。(笑)
バナナの皮もムカつきましたが、一番ムカつくのは自動追跡のノコノコの赤い甲羅をブツけられた時!
「こいつ!絶対仕返ししてやる!」と闘志が沸いたものです。
そんな僕がいつも使っていたのは、ノコノコでした。
クッパやドンキーコングのようにパワフルなわけでもなく、ヨッシーのように速くもないのですが、かわいい見た目でノコノコが一番好きでした。
それだけの理由でずっとノコノコを使っていました。
もちろん、ショートカットを使ってクリアしたり、わざと逆走してジュゲムに注意されたり…と、とことん遊びつくしました。
スターロードの難しさなど、やり込み要素も多かったですね。
本当に面白い名作ゲームです!
男の子向けなだけでなく、女の子も安心して楽しめるみんなが遊べるゲームだという点も素晴らしいと思います。
●ゲームの完成度 : ★★★★★
●誰でも楽しめる度 : ★★★★★
●飽きないゲーム性 : ★★★★★
●対戦すると喧嘩になる度 : ★★★
●何で車がジャンプ出来るの? : ★★★★★
15.ドラゴンクエストV 天空の花嫁 (1992年9月27日)
『ドラクエ・シリーズ』初のスーファミソフトとなったシリーズ5作目『ドラゴンクエストV 天空の花嫁』も僕はやりつくしました!
基本的に僕はシューティングやアクションゲームはそこまで得意ではないので、どちらかっていうとRPGやパズルゲームの方が好きでした。
その中でもやはりみんなと同じくドラクエとFFはハマりました!
特にどちらもスーファミ時代の作品にハマったのですが、スーファミのドラクエはこの1作しかやっていません。
上記にも書きましたが、6が発売された頃には僕はゲームよりも音楽に夢中になっていました。
しかしこの5は、かなりやりました。
主人公がそれまでの勇者ではなく、勇者の父親だったのが画期的でした。
またモンスターを仲間に出来るというシステムや、当時みんなが悩みまくった幼馴染のビアンカとお嬢様のフローラのどちかを結婚相手に選ばないといけないという画期的なストーリー展開でも話題になりました。
学校でも「お前どっち選んだ?」と友達の間で会話が弾みました。
僕は…ビアンカを選びました。
ただ、「僕は…」と言いにくそうに書いたのは、選んだ理由が「ロマンスの欠片もないしょうもない理由」だからです。(笑)
普通はビアンカを選ぶ際は、「幼馴染としての思い出を大切にしたい」といったロマンチックな理由からだと思うのですが……僕は「ブロンドが好きだから」というしょうもない理由で選びました。
もしビアンカが青髪で、フローラがブロンドだったら…フローラを選んでいます。
で、でもですね……生物的には「見た目」でパートナーを選ぶのは間違っていないんですよ!!!!と言い訳しておきます。(笑)
ちなみに恋愛下手なくせに、仲間のモンスター選びは「情」で選んでいたりします。
使いやすいスライムナイトや、とにかく強いゴーレムなどの強キャラではなく、最初に仲間になったスライムとブラウニーをずっと使ってました。
敢えて弱いキャラを使ったというよりも、最初に仲間になったという「情」からです。
あと、見た目のかわいさです!
もちろんこの最弱パーティーは序盤は苦労しましたが、育て甲斐のある仲間でもありました。
それに「はかいのてっきゅう」を装備したブラウニーは頼もしかったりします。
また、スライムはレベル99になると「しゃくねつのほのお」を覚えてやたら強くなります。
まぁそこまでが大変なのですが…。
でも楽々レベルアップの裏技もありましたからね。
見た目でビアンカを選んで、その後生まれた勇者が大して強くなかったのはガッカリ要素でした。
その頃には、スライムとブラウニーも十分強くなっていましたからね。
しかし花嫁や仲間モンスターを選べるというシステムは、当時としては斬新でしたね。
●ドラクエ度 : ★★★★★
●ストーリーの完成度 : ★★★★
●システムの画期性 : ★★★★
●ボスがあまり強くない度 : ★★★
●紳士はブロンドがお好き? : ★★★★★
16.ファイナルファンタジーV (1992年12月6日)
ドラクエのライバルと言えば、ファイナルファンタジーですよね。
今ではエニックスとスクエアが合併しましたが、当時の僕ら世代には2大RPGゲームの会社で絶対に相反する存在だと思っていました。
2003年に合併のニュースを聞いた時には、既に僕はゲームをやめていましたが、かなり驚きました!
「あのドラクエとFFが合体してなくなるの?」と思っていましたが、どちらも今でもシリーズが続いていますね。
さて、ドラクエの方は5になって初めてスーファミ化されましたが、FFの方は4からスーファミ化されています。
しかし僕はFFは、5からやり始めました。
その前にファミコン時代の3を友達の家で、そいつの兄貴がプレイしていたのを一緒に何回か見ていたことがあったのですが、僕がFFを自分で始めたのがこの5からです。
ドラクエにはない「ジョブチェンジシステム」が面白かった作品です。
3にもあったシステムではありますが、この「ジョブチェンジシステム」こそが当時のFFの魅力のひとつでしたね。
プレイヤーが使うことが出来る4人のキャラクターは、剣が得意なナイトや回復魔法を操る白魔導士に攻撃魔法を操る黒魔導士、弓矢を使う狩人や素手で格闘するモンク等、様々なジョブに就いて能力を身に着けることが出来ます。
その中でも、敵モンスターの特殊攻撃を覚える青魔道士や、剣に魔法の効果を込めることが出来る魔法剣士が強力でした。
1,000ポイントの固定ダメージを敵に与える「はりせんぼん」や「ゴブリンパンチ」は使い勝手が良い強力な青魔法でした。
また魔法剣は、攻撃魔法よりも状態異常系の魔法剣の方が強力だったりします。
これは「耐性のない敵には100%成功する」というシステム上の穴で、石化耐性のない敵に石化魔法の「ブレイク」の魔法剣を使うと、ボスでも一撃で倒せたりします。
僕は青魔道士と魔法剣士が好きだったのでメインで使っていました。
またキャラの見た目にも、ターバン姿の魔法剣士のバッツやアラビアの踊り子姿のレナやファリスも気に入っていました。
ちなみに本作からその後のFFのお決まりとなるギルガメッシュや、強敵裏ボスのオメガに神竜が登場するようにもなりました。
後続FFの基となる要素が詰められたゲームでもありましたね。
気づいた時には、バッツ以外女性ばかりのパーティーになっていたのも、女性の社会進出が色濃くなった時代性にマッチしていたのかな?って思います。
●FF度 : ★★★★★
●ストーリーの完成度 : ★★★
●システムの画期性 : ★★★★
●ジョブチェンジの楽しみ度 : ★★★★★
●ガラフおじいちゃ~~ん! : ★★★★
17.ドラゴンボールZ 超武闘伝 (1993年3月20日)
自分で持っていたのではなく、友達の家に遊びに行った時に遊ばせてもらったゲームです。
大人気漫画のドラゴンボールZを題材にした『ドラゴンボールZ 超武闘伝』は、通常の格闘ゲームとは違った必殺技の演出が楽しめるゲームでした。
かめはめ波や魔貫光殺砲等を相手から離れた位置で出すと、「デモ必殺技」といった独自の演出画面に切り替わります。
ここで技を受ける側は、タイミング次第で相手の技を避けたり、弾き飛ばしたり、跳ね返したりすることが出来ます。
しかしこのタイミングがシビアで、結局技を直で食らうことが多かったように思います。
また、舞空術を使って空を飛んだ際に画面が分割されて、地上にいる対戦相手との距離感の演出がされていました。
隠し要素としてメテオスマッシュのような強力な連続技もあったり、とやり込み要素も存在していました。
ちなみに僕はベジータをメインで使っていました。
だって友達が悟空を使うから、そこは空気を読んでライバルのベジータでしょう!
本当は魔人ブウが好きなのですが、このゲームの時には登場していませんでした。
●ドラゴンボール度 : ★★★★★
●格闘ゲームとしての完成度 : ★★★
●システムの画期性 : ★★★★
●セルのせいでフリーザが目立たない度 : ★★★★
●ファイナルフラッシュ! : ★★★★★
18.ワールドヒーローズ (1993年8月12日)
元はネオジオ向けに制作された対戦格闘ゲームの『ワールドヒーローズ』も1993年にスーファミ化されました。
基本はストⅡのようなリュウとケンに似た忍者ハンゾウとフウマを中心とした格闘ゲームです。
しかしそのタイトル通りに、フランスを代表するジャンヌダルクやロシアを代表するラスプーチンにハルク・ホーガン風のアメリカのプロレスラーのマッスルパワー等、世界中のヒーロー及びヴィランが登場するゲームです。
上記のハンゾウとフウマ以外にも、ドイツ代表のサイボーグ格闘家ブロッケンの手足がダルシムのように伸びたり、ブランカのような低い姿勢のJ.カーンがいたり…と、もはやパクリレベルのストⅡからの影響が感じられたりもします。
でもストⅡや餓狼伝説等と比べると、独特のチープさが逆に味のあるゲームでした。
何となく動きもモッサリしていたり、当たり判定も曖昧だったりするのですが、そのB級感が『ワールドヒーローズ』の魅力でもあります。
本来なら負の要素となるはずのダメな部分が、返ってこのゲームの魅力に変わった珍しいゲームだと思います。
ちなみに僕はブルース・リー好きなのでドラゴンを使っていました。
ブルース・リーから影響を受けたキャラとしては、先にストリートファイターズのフェイロンもいるので、これまたパク…影響を受けたのでしょう。(笑)
●ヒーロー度 : ★★★★
●格闘ゲームとしての完成度 : ★★★
●主人公の魅力 : ★★
●ナンバーワン度 : ★★★★★
●ラスプーチンのキモさ! : ★★★★★
19.T.M.N.T ミュータントウォーリアーズ (1993年9月4日)
映画でもしょっちゅうリメイクされている人気のアメコミ『忍者タートルズ』の数あるゲームの中でも珍しい1対1の対戦格闘ゲーム『T.M.N.T ミュータントウォーリアーズ』です。
しかしこれがとても面白かったです。
先のワールドヒーローズやストⅡに似た対戦格闘ゲームをタートルズのキャラクターで遊べるゲームです。
レオナルドにラファエロにミケランジェロ、そしてドナテロの4キャラはもちろん、シュレッダーやアスカといったくノ一も使うことが出来ます。
ラファエロとミケランジェロが強かったイメージです。
逆に主人公格のレオナルドがイマイチだったような…。
ちなみに僕はラファエロが好きなので、タートルズのゲームは基本的にはラファエロ使いです。
だって1人(匹?)だけサイとかいう見慣れない武器ですからね!
刀使いやヌンチャク使いに棒使いは他のゲームでも出てきますが、サイ使いは珍しいので使わない手はありません!
それに映画でも短気で怒りっぽいけれども内に秘めた熱い心を持つラファエロが活躍することが多いと思います。
アニメ版の主題歌でラファエロは”Cool and Rude”と紹介されていましたが、「無愛想で粗雑」という意味です。
●カメ度 : ★★★★★
●格闘ゲームとしての完成度 : ★★★★
●アメリカン度 : ★★★★
●レオナル度 : ★★
●ジャ~ンボリ~ : ★★★★★
20.アラジン (1993年11月26日)
あまりディズニー系は詳しくはないのですが、この『アラジン』にはハマりました!
といっても、実はアニメ映画の『アラジン』を観たことはありません。
更には今年上映された実写映画の『アラジン』も観ていません。
でもなぜかこのゲームは遊びました。
多分、FF5の魔法剣士の見た目が気に入ったのと、当時『ジョジョの奇妙な冒険 Part3 スターダストクルセイダース』の最後の決戦の地エジプトを見てアラビアンな要素に興味を持っていた時期だったからこの『アラジン』もやったのでしょう。
『スーパーマリオワールド』のように主人公のアラジンを動かして進めていく横アクションゲームです。
基本はマリオのようにジャンプして相手をかわしたり、踏みつけたりするゲームなのですが、ギリギリで壁の端っこにぶら下げれたり、細かい動きが妙にリアルだったりクォリティーは高かったです。
また終盤で、空飛ぶ魔法の絨毯に乗って背後から迫る溶岩から逃れる洞窟のステージは、かなりの緊迫感とリアリティーでした。
ストーリーは全く知らなかったのですが、それでもゲームとしてのクォリティーが非常に高かったので楽しめるゲームでした。
●ゲームのクォリティーの高さ : ★★★★★
●アクション性能の高さ : ★★★★★
●ディスニー度 : ★★★★
●アラビアンナイト度 : ★★★
●ジーニー・イン・ア・ボトル : ★★★★★
21.す~ぱ~ぷよぷよ (1993年12月10日)
今回ご紹介する30作品の中で、唯一リアルタイムでハマったゲームではありません。
僕は高校生になった頃には音楽にハマっていたので、ゲームをやらなくなってしまいました。
そのためゲーム機を持っていなかったのですが、『ぷよぷよ』に関しては高校生の時に初めて遊びました。
『ぷよぷよ』の存在はそれ以前から知っていたのですが、なぜかやらず仕舞いでした。
それがたまたま高校の頃の友達の家に数人で遊びに行った時に、みんながこの『す~ぱ~ぷよぷよ』を始めたので僕もやってみたんです。
家に上がらせてくれた友達の弟が『す~ぱ~ぷよぷよ』にハマっていたので僕らも弟の相手をしてあげることにしたんです。
その弟はまだ小学校低学年の子供で、僕ら高校生からしてもだいぶ年下なのでみんなで喜ばせるために遊んであげることにしました。
しかしその計画も途中から弟にとっては辛いものとなったことでしょう。(笑)
というのは、その中に家を貸してくれた友達と幼馴染の奴がいて、そいつが調子に乗って弟を『す~ぱ~ぷよぷよ』でボッコボコにしたからでした。
その後、他の友達もみんな手加減なく弟を負かせていきました。
最後に初めて『ぷよぷよ』をやる僕と対戦することになったのですが、一応僕はパズルゲームが得意だということもあったのと、さすがに高校生と小学生の違いもあり、簡単に勝ってしまいました!
本来なら空気を読んで、初心者で最後の僕が負けてあげるべきだったのですが、ここで『ぷよぷよ』の面白さに目覚めた僕は本気で弟をツブしにかかりました!
もちろん弟君は号泣して部屋を出ていきました…今思うとかわいそうなことをしましたが、彼も今ではおっさんになっていると思うので良しとしましょう。(笑)
その後は高校生同士で対決しました!
僕は初心者でしたが謎の才能を発揮して、その中で2番目に上手くなっていました。
さて、その後大学生になり『ぷよぷよ』のことを忘れていたのですが、たまたま一緒にバンドをやっていた1歳上の奴とよくツルむようになっていました。
最初の頃は音楽の話ばかりしていたのですが、いつの間にかそいつの家に深夜遊びに行ってTVを観てくだらない話で一晩中盛り上がっていました。
徐々にTVにも飽きてきた頃に、そいつがスーファミを取り出してきました。
そして『す~ぱ~ぷよぷよ』で対戦することになりました!
今考えれば奇妙な話なのですが、1つ年の離れたバンド仲間以外に友情もない男2人が、朝まで『す~ぱ~ぷよぷよ』で対戦するという夜を何回も過ごしました。
ほんと、何だったんだあの時期は?と思い返すこともありますが、『す~ぱ~ぷよぷよ』はめちゃくちゃ面白かったです!
そんなあまり仲良くない人間と対戦しても面白いというのは、ゲームとして凄いことだと思います。
●パズルゲームの楽しさ : ★★★★★
●初心者歓迎度 : ★★★
●中毒性 : ★★★★★
●ぷよぷよ度 : ★★★★
●げげげっ!やったな~ : ★★★★★
22.スーパーメトロイド (1994年3月19日)
任天堂はちょくちょく難しいゲームを出しますね。
『マリオワールド』も『ゼルダの伝説 神々のトライフォース』も絶妙な難易度で、ゲーム初心者から上級者まで楽しめるつくりでした。
しかしこの『スーパーメトロイド』は、本当に難しかったです。
スターウォーズ好きの僕は、異星を舞台にした近未来SFものならなんでも好きになります。
そのため『メトロイド』の世界観にもすぐに魅了されました。
その世界観もさることながら、主人公の細かいアクションや不気味なBGM等、魅力満点でした!
でもゲームは難しくて、結局僕はクリアできないまま終わりました。
エンディングはYouTube時代になってようやく他の人のプレイ動画を観て知りました。
もしかしたら今の年齢でやった方が、更に楽しめるゲームなのかもしれません⁉
●近未来SFを舞台にした世界観の魅力 : ★★★★★
●難易度 : ★★★★★
●メトロイ度 : ★★★★★
●丸まむ度 : ★★★★
●サムスはブロンド美女だった! : ★★★★★
23.ファイナルファンタジーVI (1994年4月2日)
僕の人生で2番目にハマったゲームがこの『ファイナルファンタジーVI』です。
もちろん一番は『タクティクスオウガ』です。
FF5まで続いたクリスタルを排して、前作で好評だった『ジョブチェンジシステム』までも無くして新たな世界観が構築された作品です。
その後のFFの世界観にも繋がる機械と魔法が交じり合ったスチームパンクの世界観が色濃い作品でした。
当時は、それまでの騎士が剣を振り回す中世ヨーロッパの世界観からイメージを変えたのが話題となりました!
また「魔法が失われた世界」という当初のキャッチフレーズも驚きでした!
ただ「魔法のないRPGゲーム?」と思っていたのですが……蓋を開けてみたら、結局魔法は登場しますし、相変わらず魔法攻撃は強力でした!
他にも『ジョブチェンジシステム』を無くして、キャラクターには個別に『オリジナルコマンド(特技)』が用意されていたのも大きな変更点でしたね。
一応、登場キャラ全てが主人公という触れ込みでしたが、どう考えてもストラゴスやウーマロにゴゴは主人公に程遠いと思います。
それにティナやロックにエドガーにマッシュ、セリスといった序盤からの重要人物5名が、他のキャラと比べてもずっと強いのも全員主人公には無理があります。
ただ使い方次第でガウやストラゴスも強くなります。
また、リルムも『オリジナルコマンド』の「スケッチ」のことは忘れて、魔力の高さを利用した方が強いですからね。
ベヒーモスーツを着用したリルムに、ミネルバビスチェを着用したティナとセリスという女性チームにモグを加えて『魔法使いパーティー』にすると最強クラスに強かったです。
このパーティーでアルテマや、炎属性を吸収できる武具を装備してメルトンで敵に攻撃&味方を回復という戦法を使うとゲームバランスが破壊されます。
といっても、この編成でなくともバニッシュ&デスといったセコ技が当時からリアルタイムで出回っていました。
ネットもない時代でしたが、僕らの中学でも口コミで噂が広まっていました。
ただしこれを使うとゲームが面白くなくなるので、禁止した方が良いですね。
他にも「バリアントナイフ」二刀流乱れうちのロックや「いかさまのダイス」を使ったセッツァーもぶっ壊れ性能でしたね。
それと、ゴツいグラフィックのベヒーモスにカッパーを掛けて間抜けな姿にするという楽しみもありました。(笑)
ちなみに初回はシャドウを助けられることに気づかずに見殺しにしてしまいました。
その後、友達に教えてもらいシャドウを助けることが出来ました。
僕が最終的に使っていたパーティーは…
●ロック
●マッシュ
●シャドウ
●ゴゴ
という男臭く汗臭いパーティーでした。
ロックとシャドウを使った理由は、素早さです。
『タクティクスオウガ』でもそうなのですが、僕は敵よりも先手を打って戦えるキャラが好きです。
もちろんロックはバリアントナイフ使いです。
マッシュを選んだのは、体力が高くなかなか落ちなったからです。
ゴゴを選んだ理由は、「ものまね」で連続して2回ロックの「ぬすむ」を使えたり、シャドウの「投げる」を使えるからです。
でも僕が一番好きなキャラは、セッツァーでした。
見た目やギャンブラーという職業以外にも、セリフがかっこよかったからです。
それにセッツァーとエドガーとセリスだけはクリアに絶対に必要になります。
他のキャラは、最終的に見つけ出さなくてもクリアは出来ます。
クリア後のエンディングもキャラごとに設定されていて、クリア時に揃っているメンバーの数によってエンディングの演出が変わりました。
マッシュやロックがいない状態でクリアすると、エドガーやセリスのシーンがとても悲しいものになります。
またストラゴスがいない状態でクリアすると、リルムが性格の悪い女の子のまま終了してしまうのですが、ストラゴスがいた場合は、涙なしでは見れないような感動物語に変わります。
リルムのことを好きになるシーンですので、絶対にストラゴスは加えておきましょう。
そして苦労して助けたシャドウは、これまたエンディングで号泣です!
エンディングの演出が感動的で本当に素晴らしいゲームでしたが…ラスボスは弱かったですね。
キャラクターそれぞれにテーマソングが作られていたのも好評でした。
そのどれもがクォリティーが高く、各キャラの個性ともマッチしていました。
エンディングでは全員のテーマ曲がメドレー形式になっていたのも感動的でした。
いつかまた最初からやってみたい名作RPGゲームの一ひとつです。
●FF度 : ★★★★★
●登場キャラの魅力 : ★★★★★
●エンディングの感動度 : ★★★★★
●ラスボスの強さ : ★
●今考えていることの逆が正解だ! : ★★★★★

「マヌケなタコ」ではなく「狂暴な番犬」です。
24.幽☆遊☆白書2 格闘の章 (1994年6月10日)
大人気漫画『幽☆遊☆白書』のスーファミ第二弾は1対1の対戦格闘ゲームでした。
1作目がシミュレーションだったのに対して、当時の流行りでもあるストⅡ以降の似た路線の格闘ゲームに変更されています。
この頃はらんま2/1やセーラームーンまでも格闘ゲーム化されていましたね。
まさかセーラームーンの作者さんと『幽☆遊☆白書』の作者さんが後に結婚することになるとは想像もしませんでしたが、当時はどちらも人気の漫画/アニメでしたね。
僕はセーラームーンに関してはほとんど知らないのですが、『幽☆遊☆白書』に関してはそこそこハマりました。
なので、このゲームも遊んでみました。
飛影がやたら強かった印象です。
●キャラゲー度 : ★★★★
●格闘ゲームとしての完成度 : ★★★
●微笑みの爆弾度 : ★★
●霊界探偵度 : ★
●残像だ : ★★★★★
25.餓狼伝説スペシャル (1994年7月29日)
『餓狼伝説』は、初代から『リアルバウト餓狼伝説』までやりました。
その後のシリーズに関しては未体験のままです。
初代が出た時は、子供ながらにストリートファイターズのパクりゲームだと思ってしまいました。
当時のゲーム内のキャラクターボイスは聞き取りにくかったので、アンディ・ボガードの「飛翔拳」も「波動拳」だと思っていました。
それが2になってパワーアップして帰ってきました!
『餓狼伝説2』もかなりハマったのですが、その後出た『餓狼伝説スペシャル』の方がもっとやりこみました!
というのも、僕の好きなギース・ハワードが登場していたからです。
やはり『餓狼伝説』には、ギースが必要です!
『ジョジョ』にDIOが必要なのと同じですね!
烈風拳のかっこよさもさることながら、やはり当て身投げの予想が当たった時の達成感が大きいです!
ただ、雑魚キャラだと思っていたダック・キング が実は強キャラだったのはゲーセンで痛い目にあった出来事でした。
ダック・キング使いの相手は、なぜか最初のうちは僕の攻撃を無防備に受けていたのですが、体力ゲージが赤くなると一気に超必殺技の「ブレイクスパイラル」でハメられました!
まるでザンギエフの吸い込みの如く、ちょっとでも近づけば”You an angel baby!”の連続でした!
やはり格ゲーにおいて、吸い込み系の投げキャラは強いですね。
ちなみに隠しキャラとして龍虎の拳のリョウ・サカザキが登場します。
「気力ゲージ」に関係なく「覇王翔吼拳」を使ってくるので、こちらも「覇王翔吼拳を使う奴が相手ならレイジングストームを使わざるを得ない」状況でした。
●飢えた狼度 : ★★★★
●格闘ゲームとしての完成度 : ★★★★★
●テリー・ボガー度 : ★★★
●ギース・ハワー度 : ★★★★★
●不知火舞の革ジャン&ジーパン姿を覚えてる人は少ない? : ★★★★
26.サムライスピリッツ (1994年9月22日)
格ゲーの中でもトップクラスの面白さを誇る『サムライスピリッツ』も、『餓狼伝説』や『龍虎の拳』のメーカーであるSNKが作った対戦格闘ゲームです。
『餓狼伝説』1作目こそ「ストⅡのパクリ?」と思いましたが、この頃のSNKは神懸かっていました!
『サムライスピリッツ』は、それまでの素手の格ゲーとは違って武器を持った戦いでした。
なので、バルログの爪がせこい!だとか、ビリー・カーンだけ棒持っててせこい!だとか、ジャンヌダルクはなんで剣持ってんだよ!とか、ミスタービッグはドラマーかよ!だとか、ローレンス・ブラッドはちょくちょく剣を出してくるよな!なんて考える必要はありません!
みんな武器でバッサバッサと対戦相手を斬り倒します!
しかも『モータル・コンバット』ばりに残酷な決着を迎えることになります。
まさに「いざ、尋常に!」真剣勝負をすることが出来るんです。
必殺技よりも大パンチで放つ強斬りの方が大ダメージなのも面白い要素でしたね。
一撃で勝負が左右するほどの緊張感がありました。
ちなみに僕は服部半蔵使いでした。
これまで投げキャラにやられてきた経験をもとに、「モズ落とし」野郎に転職しました。
また勝利時の「数奇将星、我にあり!」というセリフがかっこよかったのもあります。
●真剣勝負度 : ★★★★★
●格闘ゲームとしての完成度 : ★★★★★
●サムライ度 : ★★
●つばぜり合い度 : ★★★
●必殺技使うよりも蹴り技を上手く使った方が強い? : ★★★★
27.龍虎の拳2 (1994年12月21日)
引き続きSNKから名作格ゲーの『龍虎の拳2』です。
1から2になって、プレイヤーが使用できるキャラが増えるのはお決まりですね。
前作でMr.カラテだったリョウの親父タクマ・サカザキが使えたり、前作でさらわれてたのは何だったの?といった感じに妹のユリ・サカザキが兄と同じ格闘家になっていたり、そしてもみんなで「覇王翔吼拳を使わざるを得ない」状況になっていたり、極限流空手家達は無茶苦茶ですね。
ただ追加キャラの如月影二が魅力的だったり、1では使うことが出来なかった敵キャラを使用キャラクターとして使えるのは面白い要素です。
軍隊もの好きの僕はジョン・クローリーを使っていました。
「メガスマッシュ」や「フライングアタック」で「口ほどにもない!」相手をボッコボッコに出来る爽快感は最高でした。
ちなみに隠しキャラとして若い頃のギースが登場します。
ガロスペにリョウが出ていたのと同じですね。
こちらのギース様も強かったですね。
何といってもピンチからの「デッドリーレイブ」大逆転は強烈でした!
●各キャラクターの魅力 : ★★★★★
●格闘ゲームとしての完成度 : ★★★★★
●顔がボコボコになる度 : ★★★★
●超必殺技伝授度 : ★★★
●「どないしたんや~?」にムカつく度 : ★★★★★
28.FRONT MISSION (1995年2月24日)
FFシリーズのスクウェアが放つ衝撃の近未来ロボット大戦『フロントミッションシリーズ』の第一作目です。
FF6の頃から取り入れられていたメカ要素が、ここで本格化した形です。
しかもゲームシステムは戦略性が必要なシミュレーションRPGという難しい内容です。
僕は先にこのゲームをしていたので、その後発売された『タクティクスオウガ』にハマるきっかけとなりました。
ゲームシステムに慣れるまでは難しく感じましたが、しかし慣れてしまえば逆に難易度がグッと下がった印象です。
結局こういったシミュレーションRPGゲームは、遠距離攻撃が圧倒的に有利なんだなって。
1作目なのにキャラクターが豊富なのも魅力的でしたが、最終的には仲間が多すぎて戦いの緊張感が薄れていくのが難点です。
特にラスボスとの対戦時には、こちらの味方キャラが多すぎて遠距離からミサイルを飛ばしていたら難なく勝ててしまうので緊張感がありませんでした。
初期の「地獄の壁」の緊張感は何だったの?と終盤に失速していくのがもったいないゲームでもありました。
それと元は単なる民間のフリージャーナリストだったフレデリック・ランカスターが軍人並みに強いのはどうかと…。
●ロボットが活躍する退廃した近未来の世界観 : ★★★★★
●シミュレーションゲームとしての完成度 : ★★★★
●結局遠距離攻撃が強い度 : ★★★★
●ナタリー・F・ブレイクウッ度 : ★★★★
●悲劇のエンディング度 : ★★★★★

フロントミッション の『サウンド・トラック』でした。
29.タクティクスオウガ (1995年10月6日)
僕が一番最後まで遊んでいたゲームでもあり、人生で一番ハマったゲームがこの『タクティクスオウガ』でした。
最後に買ったのは、この後に登場する『ロマンシング サ・ガ3』なのですが、ロマサガ3よりもこちらの『タクティクスオウガ』の方が長くプレイしました。
1996年はずっとこの『タクティクスオウガ』ばかりやっていた思い出です。
その1年間に『タクティクスオウガ』にのめり込み過ぎたのと、1996年の半ばにU2やプリンスを聴いて音楽に目覚めたのがきっかけで、それ以降ゲームをやらなくなりました。
しかしこれほどやり込んだゲームは他にありませんでした。
ちゃんと『死者の宮殿』もクリアして『ファイアクレスト』も入手しています。
もちろん全ての禁術や竜言語魔法の入手に、10種類の必殺技も伝授してもらいました。
全ルートで攻略して、デネブなどすべてのキャラを仲間にもしました。
エンディングに関しては、『ギルバルド・エンディング』以外は全て見たと思います。
『ギルバルド・エンディング』だけはリアルタイムでは知らないままで、その後ネット時代になってから知りました。
というわけで上記にも書いていたように、このブログでも『タクティクスオウガ』に関しては過去に大きく取り上げています。
アロセールの雷神の弓や、石工職人ハボリムのペトロクラウドも多用しましたが、何といってもお気に入りのキャラは、最初から最後まで頼りになるカノープスです。
序盤では主人公の相棒のように見えて、でもLルート以外ではライバル関係になってしまうヴァイスとは違って、どのルートでもずっと頼りになる兄貴分のカノープスは本当に役に立つキャラクターでした。
高低差が重要なこのゲームにおいて、デフォルトで空を飛べるというのは使い勝手が良すぎます!
システィーナ救出もバイアン救出もセリエ救出もハボリム救出も、かのぷ~がいてくれたおかげで達成できたことでしょう。
ただ僕の場合は、序盤のクリザローの町でゴーストを説得して仲間に入れ、ショップでホークマンを1体雇っていたので、合計で3キャラ空を飛ぶことが出来ました。
かのぷ~と自分で育てたホークマンが高台からの弓部隊で、ゴーストが囮兼魔法攻撃を担当していました。
これでかなり攻略が楽になりました。
そこにアロセールとハボリムが加入したら、ゲームバランス崩壊ばりに強くなりすぎてしまいます。
Lルートだとアロセールが仲間になりませんが、改心したヴァイスに弓を持たせれば彼女のいない穴を埋めることが出来ます。
ヴァイスは機動力もあり打たれ強いので、弓を持った鉄砲玉としてはとても役に立ちます。
また初期の頃はヴォルテールというナイトが地味に頑張ってくれていたのに…徐々にフォルカスやジュヌーンにデボルトといった前線キャラが登場すると影が薄くなっていきましたね。
極めつけは素早さもあるホワイトナイトのミルディンが仲間になる頃には、ヴォルテールは「スナップドラゴで犠牲になってもらうか。」と落ち着きます。
しかしスーファミの容量不足のせいか、未完のままエンディングを迎えたのがもったいないところです。
システムが変わりまくったような『運命の輪』ではなく、正統派の『タクティクスオウガ』のリメイクを来年あたりに発売25周年を記念してリリースしてもらいたいところですね。
●カチュアにイラつく度 : ★★★★
●ヴァイスにムカつく度 : ★★★★
●レオナールにイラつく度 : ★★★★
●ロンウェー公爵にムカつく度 : ★★★★
●でも本当は優柔不断なデニムに一番ムカつく度 : ★★★★★
30.ロマンシング サ・ガ3 (1995年11月11日)
最後となりましたが30作品目は『ロマサガ・シリーズ』の名作『ロマンシング サ・ガ3』です。
僕が最後に買ったゲームソフトがこれです。
実はクリアできていません。
難しかったというのもありますが、『タクティクスオウガ』の方にハマりすぎて『ロマンシング サ・ガ3』は途中で止めてしまいました。
しかし魅力的な8名の主役キャラに、マスコンバットや会社経営のような戦略性の必要なミニゲームなどやり込み要素もたくさんあったゲームでしたね。
僕はハリードが一番好きでした。
FF5の魔法剣士や『アラジン』に続くアラビアンな見た目に、「カムシーン」と呼ばれる曲刀のかっこよさ、そして実際に強いキャラだったのが魅力的でした。
どこぞの格ゲーの「どないしたんや~?」が口癖のキャラと同じスティーヴン・セガールな髪形でしたが、エセ関西弁を使わないのは好印象でした。
それと仲間に出来るキャラの多さもこのゲームの魅力でしたね。
でも強引に仲間になって、なかなか外せない詩人にはムカつきました!
ロビンに関しては、スマートな本物よりも、太っちょな体系に反して素早い偽物の方が好きでした。
ハーマンは、苦労してブラックに戻すまでがかなり面倒なのが難点です…。
ブラックになれると斧使いとして最強キャラなんですけどね。
カタリナが本人のシナリオ以外では、ハリードかミカエルの序盤以外では仲間にならないのはもったいないな…と思います。
彼女のシナリオ時のショートカットのグラフィックがとてもよかっただけに、他のキャラが主人公の時にも仲間に出来たらな~って思いました。
ちなみに他のゲームでもキワモノ好きの僕は、ぞうとゆきだるまとボストン(ロブスター)が好きで使っていました。
特にハサミを使って殴りつけるボストンのグラフィックが愉快で好きでした。
●ハリード
●ボストン
●ゆきだるま
●ぞう
●ロビン(偽物)
が、僕の使っていたキワモノ・パーティーです。(笑)
途中で止めたのでクリアこそしていませんが、このパーティーでもかなりの強さでした!
ゆきだるまとぞうを壁にして、ハリードとボストンで敵をタコ殴り!です。
ロビンは、回復役の癒し系(?)です。
キャラに魅力のあるゲームでしたね。
●ロマサガ度 : ★★★★★
●自由度 : ★★★★
●やり込み度 : ★★★★
●詩人ムカつき度 : ★★★★
●ハリー度 : ★★★★★
以上、『思い出に残るスーパーファミコンの名作ソフト30選』のご紹介でした。
久しぶりのブログ更新は、長文でのスーファミご紹介となりましたが、最後まで読んでいただけたら嬉しいことです。
またこのブログ記事以外の、このサイトのメインでもある音楽の記事にも目を通していただけたら幸いです。
ちなみにスーパーファミコンは、海外では”Super Nintendo Entertainment System”の名で発売されているので英語圏の人らには「スーファミ」は通じません。
「スーパーニンテンドゥ」と、なかやまきんに君の「アーノルド・シュワルツェネガー」並みに発音しましょう。(笑)
それと、ヒップホッパーのノトーリアス・B.I.G.の代表曲でもある”Juicy”の歌詞にも”Super Nintendo”が出てきたりします。
MVでも2分40秒らへんでその歌詞が登場して『ストⅡ』のゲームをやっている人物が映し出されています。
アメリカでも人気だったんですね。
それでは日本が誇る世界的なブームを巻き起こした『スーパーファミコン』の魅力を、このブログを通して見直してもらえれば……と思います。
他に関連するお勧め記事